 �@�ǂ��ǂ�ł��y�����B�ǂ�����ǂ�ł��y�����Ȃ�B����́u�������S�N�S�N�A�A���Ȃ�v�͌������Ė��ł���B
�@�ǂ��ǂ�ł��y�����B�ǂ�����ǂ�ł��y�����Ȃ�B����́u�������S�N�S�N�A�A���Ȃ�v�͌������Ė��ł���B �@ 2024�N4��9 ���ɓ��{�C�ۋ�����\�����u4������^�ē��̉\���@�M���ǂ̃��X�N�ɒ��ӂ��v�Ƃ̃v���X�����[�X���ɂ́u���M�����v�ƌ������t���g���Ă����B���ꂪ�_�@�ɂȂ����̂��낤�Ɛ������Ă��邪�A���̌�b���̊Ԃ́u���M�����v�ƌ������t���e���r�ԑg��Ȋ��i�H�j���Ă����B
�@ 2024�N4��9 ���ɓ��{�C�ۋ�����\�����u4������^�ē��̉\���@�M���ǂ̃��X�N�ɒ��ӂ��v�Ƃ̃v���X�����[�X���ɂ́u���M�����v�ƌ������t���g���Ă����B���ꂪ�_�@�ɂȂ����̂��낤�Ɛ������Ă��邪�A���̌�b���̊Ԃ́u���M�����v�ƌ������t���e���r�ԑg��Ȋ��i�H�j���Ă����B �@�ŋ߁A�p�\�R���Ɍ������ĉ�����Ƃ�����Ƃ��ɂ́A���W�J�Z���瓶�w�A���̂���{�̝R��̂𗬂��Ă���B�����͏\���N�O�ɔ����� DVD �W���ō\������Ă���u���������{�̉́v���� 128 �Ȃ��玄�̍D���ȉ� 44 �Ȃ�I�сA�F�l�ɗ���� CD �����Ă���������̂ł���B
�@�ŋ߁A�p�\�R���Ɍ������ĉ�����Ƃ�����Ƃ��ɂ́A���W�J�Z���瓶�w�A���̂���{�̝R��̂𗬂��Ă���B�����͏\���N�O�ɔ����� DVD �W���ō\������Ă���u���������{�̉́v���� 128 �Ȃ��玄�̍D���ȉ� 44 �Ȃ�I�сA�F�l�ɗ���� CD �����Ă���������̂ł���B �@��w�ʐ^�� OB �̒��ԂƖ��N 12 ���ɔ��s���Ă��铯�l�ʐ^�W�����N 25 ��ڂ��}����B���͏���Q�����Ă��邪�A�����`���ő������ꂽ 24 �������I�ɕ���ł���̂��݂�ƃ`���b�g�������Ȃ�B
�@��w�ʐ^�� OB �̒��ԂƖ��N 12 ���ɔ��s���Ă��铯�l�ʐ^�W�����N 25 ��ڂ��}����B���͏���Q�����Ă��邪�A�����`���ő������ꂽ 24 �������I�ɕ���ł���̂��݂�ƃ`���b�g�������Ȃ�B �@���Ă��̗��Ɂu�ŋ߁A������Ƃ������������Ƃ��Ɋ����𐳂��������Ȃ����ƂɋC���t�����B�w�����炸��嫂������炸�x���x�̊������x�X�o������B�����A�ȒP�ȓ��L�Ƃ��������̓��̍s�����R�N���L�Ɏ菑�����Ă���Ȃɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��炵���v�A�����Łu�����Ώۂ̖{�̒��ɁA���ꍞ��ł����w������葍�����K�x�Ƃ̕\���100�ŋ��̖��W���g���Ė����P�ł���35�`37����������ƂƂ����v�Ƃ������e�̕��͂��f�ڂ����������B
�@���Ă��̗��Ɂu�ŋ߁A������Ƃ������������Ƃ��Ɋ����𐳂��������Ȃ����ƂɋC���t�����B�w�����炸��嫂������炸�x���x�̊������x�X�o������B�����A�ȒP�ȓ��L�Ƃ��������̓��̍s�����R�N���L�Ɏ菑�����Ă���Ȃɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��炵���v�A�����Łu�����Ώۂ̖{�̒��ɁA���ꍞ��ł����w������葍�����K�x�Ƃ̕\���100�ŋ��̖��W���g���Ė����P�ł���35�`37����������ƂƂ����v�Ƃ������e�̕��͂��f�ڂ����������B �@�ŋߓڂɒ��ҏ�����ǂޔE�ϗ͂������Ȃ����悤���B�u�t�[�R�[�̐U��q�v��]���̍����T�R��v�V��́u�J���}�[�]�t�̌Z��v�Ȃǂ͂����肪�͂��Ƃ���ɒu���Ă���̂����A�ǂ݂����̏�ԂŎ��Ԃ������߂��Ă���B��Ɏ��{�̓G�b�Z�C�W��Z�ҕ�����W�߂����̂ƂȂ��Ă����B���ʓI�ɂ͑S�Ă̕łɖڂ�ʂ����ƂɂȂ�̂����A�ǂ�����ǂ�ł������悤�ȓ��e�̖{����Ɏ�邱�Ƃ������B
�@�ŋߓڂɒ��ҏ�����ǂޔE�ϗ͂������Ȃ����悤���B�u�t�[�R�[�̐U��q�v��]���̍����T�R��v�V��́u�J���}�[�]�t�̌Z��v�Ȃǂ͂����肪�͂��Ƃ���ɒu���Ă���̂����A�ǂ݂����̏�ԂŎ��Ԃ������߂��Ă���B��Ɏ��{�̓G�b�Z�C�W��Z�ҕ�����W�߂����̂ƂȂ��Ă����B���ʓI�ɂ͑S�Ă̕łɖڂ�ʂ����ƂɂȂ�̂����A�ǂ�����ǂ�ł������悤�ȓ��e�̖{����Ɏ�邱�Ƃ������B �@�O��̂��̗��ŃA���t�H���X�E�h�[�f�́u���ԏ��������v�ɂ��ĐG�ꂽ���͂��������B���ꂪ�_�@�ɂȂ����̂��ǂ����A���ĉp�ĂŁi�x��Ă킪���ł��j��x�X�g�Z���[�ɂȂ����u�앧�v�����@���X�� 12 �����v�i�͏o���[�V�ЁA�s�[�^�[�E���C�����A�r ���Ԗ�j���v���o�����B�Ɠ����ɒN�̂ǂ̖{�œǂ��͎v���o���Ȃ����u���݂���h�[�f�̕��Ԃ́i�ό��p�Ɂj�K���ɑI�ꂽ�B���̕��Ԃ��~�X�g�����ʼn���Ƌ߂��̈�������Ԃ����ꂾ�ƌ������Ƃɂ����v�Ƃ�����|�̕��͂Ƃ����ǂ�Łu�F����Ԃ̂Ȃ炻��ł���������Ȃ����v�Ǝ����v�������Ƃ����̕Ћ�����h�����B�~�X�g�����Ƃ͓~����t�ɂ����ăA���v�X�R�����烍�[�k�k�J��ʂ��Ēn���C�ɐ����~�낷����Ŋ��������k���̂��Ƃł���B
�@�O��̂��̗��ŃA���t�H���X�E�h�[�f�́u���ԏ��������v�ɂ��ĐG�ꂽ���͂��������B���ꂪ�_�@�ɂȂ����̂��ǂ����A���ĉp�ĂŁi�x��Ă킪���ł��j��x�X�g�Z���[�ɂȂ����u�앧�v�����@���X�� 12 �����v�i�͏o���[�V�ЁA�s�[�^�[�E���C�����A�r ���Ԗ�j���v���o�����B�Ɠ����ɒN�̂ǂ̖{�œǂ��͎v���o���Ȃ����u���݂���h�[�f�̕��Ԃ́i�ό��p�Ɂj�K���ɑI�ꂽ�B���̕��Ԃ��~�X�g�����ʼn���Ƌ߂��̈�������Ԃ����ꂾ�ƌ������Ƃɂ����v�Ƃ�����|�̕��͂Ƃ����ǂ�Łu�F����Ԃ̂Ȃ炻��ł���������Ȃ����v�Ǝ����v�������Ƃ����̕Ћ�����h�����B�~�X�g�����Ƃ͓~����t�ɂ����ăA���v�X�R�����烍�[�k�k�J��ʂ��Ēn���C�ɐ����~�낷����Ŋ��������k���̂��Ƃł���B �@�Â��O�t���n�[�h�f�B�X�N�̓��e�����Ă�����A�����̍��ɐV�݂̖@���R������� PR �̂��߂ɁA�Z�����d���̍��Ԃ�D���Ė��T�Q��̕p�x�Ŕ��M���Ă����j���[�X���^�[�̌��e���o�Ă����B��������������A�폜����O�ɂ�����Ɩڂ�ʂ����B���̒��ɃA���t�H���X�E�h�[�f�́u���ԏ��������v�Ɛ������ɂ��ĐG�ꂽ���̂��������B
�@�Â��O�t���n�[�h�f�B�X�N�̓��e�����Ă�����A�����̍��ɐV�݂̖@���R������� PR �̂��߂ɁA�Z�����d���̍��Ԃ�D���Ė��T�Q��̕p�x�Ŕ��M���Ă����j���[�X���^�[�̌��e���o�Ă����B��������������A�폜����O�ɂ�����Ɩڂ�ʂ����B���̒��ɃA���t�H���X�E�h�[�f�́u���ԏ��������v�Ɛ������ɂ��ĐG�ꂽ���̂��������B �@�����ŏ�������Ƃ͉�Ђ�����߂̕��X���ߋ��P�����Ԃ̊������L�^���A��i���ɒ�o���镶���̂��Ƃł͂Ȃ��B���w�S�W�Ȃǂ̘A�����Ċ��s�����o�ŕ��ɁA�ʍ��Ƃ��ĕ\���̌��ɋ��܂�Ă��������̈Ӗ��ł���B
�@�����ŏ�������Ƃ͉�Ђ�����߂̕��X���ߋ��P�����Ԃ̊������L�^���A��i���ɒ�o���镶���̂��Ƃł͂Ȃ��B���w�S�W�Ȃǂ̘A�����Ċ��s�����o�ŕ��ɁA�ʍ��Ƃ��ĕ\���̌��ɋ��܂�Ă��������̈Ӗ��ł���B �u�̗V�����v�Ɩ��t����ꂽ�䂪�Ƃ̋߂��ɂ���E�I�[�L���O��������Ă������̍ȂƂ̂��킢�̂Ȃ���b�ł���B�T��ɐA����ꂽ�T���S�W����N�`�i�V�߂Ȃ���u�t�������Ə���ł���ˁA�������Ă���̂��낤���v�u�́A��ɍ炢�Ă����N�`�i�V�̗t���悭���ɐH���Ă����ˁv�u�T���S�W���͗t�������Â��̂Œ����悭���v�B
�u�̗V�����v�Ɩ��t����ꂽ�䂪�Ƃ̋߂��ɂ���E�I�[�L���O��������Ă������̍ȂƂ̂��킢�̂Ȃ���b�ł���B�T��ɐA����ꂽ�T���S�W����N�`�i�V�߂Ȃ���u�t�������Ə���ł���ˁA�������Ă���̂��낤���v�u�́A��ɍ炢�Ă����N�`�i�V�̗t���悭���ɐH���Ă����ˁv�u�T���S�W���͗t�������Â��̂Œ����悭���v�B �@���������Đ_�Е��t��������鏗���������Ă���A���q�A����K�[���Ȃ錾�t�����邻�����B�����������P�b�g�{�[�����Ԃ̏������A�ŋߗF�l�̉e���Ő����O�\�O���w�ł��n�ߌ����Ղ��Ă��邻���ŁA�܁X�A�w�ł������̎ʐ^�₻�̋߂��̕��i�ʐ^���G�s�\�[�h�Ƌ��Ƀ��C���ő����Ă����B
�@���������Đ_�Е��t��������鏗���������Ă���A���q�A����K�[���Ȃ錾�t�����邻�����B�����������P�b�g�{�[�����Ԃ̏������A�ŋߗF�l�̉e���Ő����O�\�O���w�ł��n�ߌ����Ղ��Ă��邻���ŁA�܁X�A�w�ł������̎ʐ^�₻�̋߂��̕��i�ʐ^���G�s�\�[�h�Ƌ��Ƀ��C���ő����Ă����B �@�ߌ�O���̃r�[���Ƃ͋ɂ߂Ė��͓I�Ȍ��t�ł���B
�@�ߌ�O���̃r�[���Ƃ͋ɂ߂Ė��͓I�Ȍ��t�ł���B �@���͔o���Z�̂���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�ǂނ��Ƃ͍D���ł���B�ƌ����Ă���O�͂�����̂̓���̔o�l��̐l�̋�W�A�̏W�J�ɓǂނ̂ł͂Ȃ��A���퐶���Ŗڂɂ���V���A�G�����̑��Ɍf�ڂ���Ă��邻�̓��̐��Ƃ̍�i����Ƃɂ��I�ꂽ��ʐl�̍�i���Ώۂł���B�I�҂̉����ǂ�Ŋ��S���邱�Ƃ�����A���̉��߂Ƃ͂�����ƈႤ�Ȃ��A�Ǝv�����肸�Ԃ̑f�l�Ƃ��Ċy����ł���B
�@���͔o���Z�̂���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�ǂނ��Ƃ͍D���ł���B�ƌ����Ă���O�͂�����̂̓���̔o�l��̐l�̋�W�A�̏W�J�ɓǂނ̂ł͂Ȃ��A���퐶���Ŗڂɂ���V���A�G�����̑��Ɍf�ڂ���Ă��邻�̓��̐��Ƃ̍�i����Ƃɂ��I�ꂽ��ʐl�̍�i���Ώۂł���B�I�҂̉����ǂ�Ŋ��S���邱�Ƃ�����A���̉��߂Ƃ͂�����ƈႤ�Ȃ��A�Ǝv�����肸�Ԃ̑f�l�Ƃ��Ċy����ł���B �@�}���ق̐V���{�̒I�Ƀ|�c���ƈ���c����Ă����{�����䓴�A�~���[�W�A���Ɠ���A�W�A�l�Êw��̕҂ɂȂ�u����A�W�A�̓��A��Ձv�i�Y�R�t�j�������B���A���Ղɂ͂���قǂ̊S�������Ă���Ƃ�����ł͂Ȃ����A�A�[�g���ň�����ꂽ���̖{����Ɏ���Ă݂�Ɗe�łɈ�Ղ̑S�̎ʐ^��o�y�������X�̎ʐ^�E�֘A����}�\���f�ڂ���Ă���A���߂邾���ł��ʔ������������̂Ŏ�o���葱���������B
�@�}���ق̐V���{�̒I�Ƀ|�c���ƈ���c����Ă����{�����䓴�A�~���[�W�A���Ɠ���A�W�A�l�Êw��̕҂ɂȂ�u����A�W�A�̓��A��Ձv�i�Y�R�t�j�������B���A���Ղɂ͂���قǂ̊S�������Ă���Ƃ�����ł͂Ȃ����A�A�[�g���ň�����ꂽ���̖{����Ɏ���Ă݂�Ɗe�łɈ�Ղ̑S�̎ʐ^��o�y�������X�̎ʐ^�E�֘A����}�\���f�ڂ���Ă���A���߂邾���ł��ʔ������������̂Ŏ�o���葱���������B �@�V���Ђ���u�G�X�g�j�A�I�s�v�Ƃ����{�����s����Ă���B�����ȏ����́u�G�X�g�j�A�I�s�@�X�̑ہE��ؘ̖R����E�C�̈��v�Ƃ����A���҂͎��ɂƂ��Ă͏��߂Ă��ڂɂ����關�؍����Ƃ��������ł���B 1956 �N���܂�̎������w��ƂƏЉ��Ă����B
�@�V���Ђ���u�G�X�g�j�A�I�s�v�Ƃ����{�����s����Ă���B�����ȏ����́u�G�X�g�j�A�I�s�@�X�̑ہE��ؘ̖R����E�C�̈��v�Ƃ����A���҂͎��ɂƂ��Ă͏��߂Ă��ڂɂ����關�؍����Ƃ��������ł���B 1956 �N���܂�̎������w��ƂƏЉ��Ă����B|
�� |
���C�^�[�ʐM�ɂ��ƁA�X�E�F�[�f���̐Ŗ����ǂ� 29 ���A����E��풆�ɑ����̃��_���l���i�`�X�E�h�C�c�̔��Q����~���A�� 71 �N�O�ɍs���s���ƂȂ����X�E�F�[�f���̊O�������E���E�E�H�[�����o�[�O���ɂ��āA���Y�Ǘ��l���玀�S�F��\��������A���N��̍��H�ɂ����S���m�F�����\�������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B |
|
�� |
�E�H�[�����o�[�O�ɋ~��ꂽ���_���l��i�́j�A���u���ۃE�H�[�����o�[�O����v��ݗ����Ď�|��������߁i�Ă��j���B |
|
�� |
�i�s���s����̔ނ́j�����͕s���Łi�ނ́j�u���Ȃ��p�Y�v�Ə̂���Ă���B |
|
�� |
1996 �N�ɂ̓C�X���G�����{�����_���l���~�ς������т��������āA���{�l�O�����E�����琤�Ɠ������i�ނɁj���h�E���@�V�G���܂����B 1979 �N�ɃC�X���G���Łi�ނ́j�����肪����ꂽ�B |
 �@�}���ق���u�\�ꂽ���������܂��v�Ƃ������[���������Ă����B�u�ŋ߂͉����\�Ă��Ȃ��̂Ɂv�Ǝv�������A���e������Ə��� ������́u����v�i����Ёj�������B���҂̏��� ���Ƃ������O�����ċL�����h�����B
�@�}���ق���u�\�ꂽ���������܂��v�Ƃ������[���������Ă����B�u�ŋ߂͉����\�Ă��Ȃ��̂Ɂv�Ǝv�������A���e������Ə��� ������́u����v�i����Ёj�������B���҂̏��� ���Ƃ������O�����ċL�����h�����B|
�� |
�ƂɎ����A�����R���̎��́A�����Ɏ���āA�ׂ��s����菜���B���̍�Ƃ��A���ɂ��܂��܂��Ă���B�c�c��D���ȉ��y���Ȃ���A�R���̎��̂����b������̂́A�����̂ЂƂƂ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�i�H���j |
|
�� |
��l�ɂȂ�A���߂āA�炪�����Ăӂ�ӂ�̑嗱�̔~������H�ׂ����́A�ڂ�������������ɂȂ����B�c�c����͂܂�ŕ�̂悤�ȑ��݊��ŁA���h�ȁu���y���v�������B�i�������j |
|
�Z |
���X���̉ߒ��ŁA���Ɛ����������Ă��鎞�Ԃ��D�����B����C���������₩�ɂȂ��āA�ґz���Ă���悤�ȋC���ɂȂ�B���X�ɂ́A�F���̋�͂ɂ��C�G����A�����̖����h���Ă���B�c�c��x�A���̂������߂����C�����ŁA���X���d�����Ƃ��������B�������o���ėl�q������ƁA�Ȃ�Ƃ��̖��X����̓J�r�������Ă����B�c�c����ς薡�X���������Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�Ɋ������B�i�_�����j |
|
�� |
�R�S�~�́c�c�W�c�ʼn���o���̂ŁA�����͎c���A�O���������̂�悤�ɂ���ƁA���N���������h�ȉ肪��������B�~�����đS����E��ł��܂�����A���N�͕n��ȉ肵���o�Ă��Ȃ��B�i�o�H������ցA�t�A�Ăсj |
 �@�}���ق̏��I��������E�ɏ��ɒ��߂Ă���Ɓu�`�F�R�̏\���v�ƌ����^�C�g���A�u���Ƃ��̍��ɕ�炷�v�Ƃ�������A�����Ē��Җ��́u�o�v���v���ڂɂ����B�u�o�v���v�̉����͐}���̕��ޔԍ��Ǝv����uE�f�N�`�G�v��������ꂽ�V�[��������ꖼ�O�̕������B��Ă���B
�@�}���ق̏��I��������E�ɏ��ɒ��߂Ă���Ɓu�`�F�R�̏\���v�ƌ����^�C�g���A�u���Ƃ��̍��ɕ�炷�v�Ƃ�������A�����Ē��Җ��́u�o�v���v���ڂɂ����B�u�o�v���v�̉����͐}���̕��ޔԍ��Ǝv����uE�f�N�`�G�v��������ꂽ�V�[��������ꖼ�O�̕������B��Ă���B �@�����L�O�����́u���̐X�v�ɂ͖� 100 �i��A 260 �{�̒ւ��A�͂���Ă���B�܂������Βn�̓s�s�Ή��A�����ɂ��u�֎R�v�Ɖ������̒փR�[�i�[�u�J�����A���[���v�̂Q�̒փG���A������B���N���O�܂ł́A�G�߂ɂȂ�ƍȂƂ悭�K��ʐ^���B�����B
�@�����L�O�����́u���̐X�v�ɂ͖� 100 �i��A 260 �{�̒ւ��A�͂���Ă���B�܂������Βn�̓s�s�Ή��A�����ɂ��u�֎R�v�Ɖ������̒փR�[�i�[�u�J�����A���[���v�̂Q�̒փG���A������B���N���O�܂ł́A�G�߂ɂȂ�ƍȂƂ悭�K��ʐ^���B�����B �@���p�i�̈��R���N�V������z������x���̏N�W�i��W�����邽�߂Ɍ��Ă�ꂽ���p�ق͂悭����B�Ⴆ�Ύ��ƉƂ̃A���g���E�N�����[�E�~�����[�Ƃ��̕v�l�w�����ɂ��N�W���ꂽ�������̃S�b�z�̍�i���܂ނP���_�]�̔��p�i��L����N�����[�E�~�����[���p�فA���{�ł͑q�~�̎��ƉƑ匴���O�Y�ɂ��N�W���ꂽ���m���p�A�ߑ���p��W������匴���p�فA������Ѓu���a�X�g���̑n�Ǝ҂ł��������Y�̏N�W�ɂ�鐼�m���p�A���{�ߑ�G��̃A�[�e�B�]�����p�فi���u���a�X�g�����p�فj���X�B
�@���p�i�̈��R���N�V������z������x���̏N�W�i��W�����邽�߂Ɍ��Ă�ꂽ���p�ق͂悭����B�Ⴆ�Ύ��ƉƂ̃A���g���E�N�����[�E�~�����[�Ƃ��̕v�l�w�����ɂ��N�W���ꂽ�������̃S�b�z�̍�i���܂ނP���_�]�̔��p�i��L����N�����[�E�~�����[���p�فA���{�ł͑q�~�̎��ƉƑ匴���O�Y�ɂ��N�W���ꂽ���m���p�A�ߑ���p��W������匴���p�فA������Ѓu���a�X�g���̑n�Ǝ҂ł��������Y�̏N�W�ɂ�鐼�m���p�A���{�ߑ�G��̃A�[�e�B�]�����p�فi���u���a�X�g�����p�فj���X�B �@�ǂ̖{���������A�N�̃G�b�Z�C�����������o���Ă��Ȃ��̂��c�O�����u�V�l�͓Z�߂�����v�Ƃ������Ƃɂ��Ă����ȗ�������āA�ꌩ�_���I�Ɍ�����悤�Ȍ`�Ō�����Ă���y�������͂��L�����Ă���B���̂Ƃ��ɂ͎�����Ȃ݂āu�S�����̂Ƃ���v�u�悭�ώ@����Ă���Ȃ��v�Ǝv�����B���̌�A�����̐Ȃ�G�k�E�Ւk�E���k�̐܂ɂ��̈ӌ����Љ�����A���̏�̑����̎^�����B
�@�ǂ̖{���������A�N�̃G�b�Z�C�����������o���Ă��Ȃ��̂��c�O�����u�V�l�͓Z�߂�����v�Ƃ������Ƃɂ��Ă����ȗ�������āA�ꌩ�_���I�Ɍ�����悤�Ȍ`�Ō�����Ă���y�������͂��L�����Ă���B���̂Ƃ��ɂ͎�����Ȃ݂āu�S�����̂Ƃ���v�u�悭�ώ@����Ă���Ȃ��v�Ǝv�����B���̌�A�����̐Ȃ�G�k�E�Ւk�E���k�̐܂ɂ��̈ӌ����Љ�����A���̏�̑����̎^�����B �@ 10 �����{�̑u�₩�ȌߑO�A�䂪�Ƃ̒�̕Ћ��Ɏ������炢�Ă���̂ɋC���t�����B�Z�\�N���̐̂Ɠ����ʒu�ɍ炢�Ă���B�Ȃ́u�������łɗ����Ƃ����炱���ɍ炢�Ă���v�Ƃ����B
�@ 10 �����{�̑u�₩�ȌߑO�A�䂪�Ƃ̒�̕Ћ��Ɏ������炢�Ă���̂ɋC���t�����B�Z�\�N���̐̂Ɠ����ʒu�ɍ炢�Ă���B�Ȃ́u�������łɗ����Ƃ����炱���ɍ炢�Ă���v�Ƃ����B �@���ɂ͊�����ۛ��� YouTube �ԑg������B���̂����̈�̓E�B�L�y�f�B�A�ł͕]�_�ƁE�ҏW�ҁE�^�����g�E�R�����j�X�g�ƏЉ��Ă���R�c�ܘY�����א��̊G��ɂ��ĕ��L������̍l��������ɂ킩��₷���������� 30 ���́u�R�c�ܘY�I�g�i�̋��{�u���v�ł���B����̂��̔ԑg�ł͑א�����ł͂Ȃ��u���c��ɏ������ʼn�ƁE���q�`�v�v�����グ��ꂽ�B���͂��̎��_�܂ł��̚�܂̔ʼn�Ƃɂ��Ă͑S���m��Ȃ������B
�@���ɂ͊�����ۛ��� YouTube �ԑg������B���̂����̈�̓E�B�L�y�f�B�A�ł͕]�_�ƁE�ҏW�ҁE�^�����g�E�R�����j�X�g�ƏЉ��Ă���R�c�ܘY�����א��̊G��ɂ��ĕ��L������̍l��������ɂ킩��₷���������� 30 ���́u�R�c�ܘY�I�g�i�̋��{�u���v�ł���B����̂��̔ԑg�ł͑א�����ł͂Ȃ��u���c��ɏ������ʼn�ƁE���q�`�v�v�����グ��ꂽ�B���͂��̎��_�܂ł��̚�܂̔ʼn�Ƃɂ��Ă͑S���m��Ȃ������B �@ 2023 �N�W�� 13 ���t�ǔ��V�������ɂ͓��W�L���Ƃ��ĂQ�łɘj��u���s���ɓǂ݂��������𖡂키�{�v�̗����������B
�@ 2023 �N�W�� 13 ���t�ǔ��V�������ɂ͓��W�L���Ƃ��ĂQ�łɘj��u���s���ɓǂ݂��������𖡂키�{�v�̗����������B �@�}���ق̐V���{�R�[�i�[�ɔ��s����̂��́u54���̕���w�v���u����Ă����B����ɂ́u�Ӗ����킩��ƃ]�N�]�N���钴�Z�ҏ����v�Ƃ���B���s����PHP�������A���҂͎��c�Y��B
�@�}���ق̐V���{�R�[�i�[�ɔ��s����̂��́u54���̕���w�v���u����Ă����B����ɂ́u�Ӗ����킩��ƃ]�N�]�N���钴�Z�ҏ����v�Ƃ���B���s����PHP�������A���҂͎��c�Y��B �@�{��ǂ�ł���Ƃ����ɒ��҂������ȈӖ������߂đE�߂Ă�����A���y�����肵�Ă��钘�҈ȊO�̐l���ɂ��{�ɂ��Ă̋L�q�����|���邱�Ƃ�����B���܂ƌ����\���������������t������ł��邱�Ƃ�����B�����Ă�������V�������҂⍡�܂Œm��Ȃ����������Ƃ̕t���������n�܂�B���̂悤�ɂ��Ēm�������������������I�ɕ���ł���B
�@�{��ǂ�ł���Ƃ����ɒ��҂������ȈӖ������߂đE�߂Ă�����A���y�����肵�Ă��钘�҈ȊO�̐l���ɂ��{�ɂ��Ă̋L�q�����|���邱�Ƃ�����B���܂ƌ����\���������������t������ł��邱�Ƃ�����B�����Ă�������V�������҂⍡�܂Œm��Ȃ����������Ƃ̕t���������n�܂�B���̂悤�ɂ��Ēm�������������������I�ɕ���ł���B �@���́u�����Ă��������v�ɂ��ẮA 2020�N11��11 �t�̂��̗��ŁA���́u���̑匙���Ȍ�@�v�Ə����A�ےJ�ˈꎁ���u��������Ȃ�����{��v�̒��Łu������{�l�͂��̜��疳��ɉ��Ӂc�c�\�ԓI��p���̌�@�����������T�ނق��������Ǝv�Ӂv�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��Љ���B
�@���́u�����Ă��������v�ɂ��ẮA 2020�N11��11 �t�̂��̗��ŁA���́u���̑匙���Ȍ�@�v�Ə����A�ےJ�ˈꎁ���u��������Ȃ�����{��v�̒��Łu������{�l�͂��̜��疳��ɉ��Ӂc�c�\�ԓI��p���̌�@�����������T�ނق��������Ǝv�Ӂv�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��Љ���B �@�������v�w�͌��j���̖�� BS ���e���ŕ��f����Ă���u BS ���{�E������̉́v�̃t�@���ł���B�R�[���X�O���[�v�E�t�H���X�^���A���w�E���̂▾�����珺�a���܂ł́u�z���o�̗��s�́v���̂��ԑg�ł���B�]�v�ȃi���[�V�����≉�o�͈�Ȃ��B
�@�������v�w�͌��j���̖�� BS ���e���ŕ��f����Ă���u BS ���{�E������̉́v�̃t�@���ł���B�R�[���X�O���[�v�E�t�H���X�^���A���w�E���̂▾�����珺�a���܂ł́u�z���o�̗��s�́v���̂��ԑg�ł���B�]�v�ȃi���[�V�����≉�o�͈�Ȃ��B �@�Q�N�O�Ɍg�ѓd�b���X�}�[�g�t�H���ɑウ���Ƃ��A�����m������w�ʐ^�� OB ��̌�y�̈�l���ނƓ������ɕ����������Ă����V�`�W�l�ƍ���Ă��郉�C���̃O���[�v�ɎQ������悤���߂Ă��ꂽ�B
�@�Q�N�O�Ɍg�ѓd�b���X�}�[�g�t�H���ɑウ���Ƃ��A�����m������w�ʐ^�� OB ��̌�y�̈�l���ނƓ������ɕ����������Ă����V�`�W�l�ƍ���Ă��郉�C���̃O���[�v�ɎQ������悤���߂Ă��ꂽ�B �@���N��3���̂�����B�����ݏZ�̗F�l���u�{���G�{�܂��Ƃ����{�Ȃ��ǁA���ɂɂǂ�������H�v�ƊG�{���Ă����������B�p�X�e���J���[�̂��킢���G�{�B�u���[�b�A���肪�Ƃ��I�I�v
�@���N��3���̂�����B�����ݏZ�̗F�l���u�{���G�{�܂��Ƃ����{�Ȃ��ǁA���ɂɂǂ�������H�v�ƊG�{���Ă����������B�p�X�e���J���[�̂��킢���G�{�B�u���[�b�A���肪�Ƃ��I�I�v|
�E |
���������܂ꂽ�q�����Y�̏ꍇ�A������������Ŕ��N�قǎ���̌�A���Y���Ƃ��Ďs��ɂ������B�܂��~���N�̏o�������Ȃ��������������Ƃ��Ĉ����邻���ł��B |
|
�E |
���Ƃ��Ɠ��{�ł͓��H�̕��K���Ȃ������B���͎�Ɏg�����Ƃ��Ď��炳��Ă����̂����A�_�Ƃ̋@�B���E�H�����̉��ĉ����i�ނɂ��������āA�g�����������Ƃ��Đ��Y�����悤�ɂȂ�B |
|
�E |
�{�Y���̎��R���ɂ��A�����A����������悤�ɂȂ�A���{�̓����̓u�����h���A�����������̕����ɁB |
|
�E |
���{�̒{�Y�_�ƂɌ���������B�Ȋ��ł̎���ʼnƒ{�ɃX�g���X�̂��߂̕a�C������B���̂��߁A�R�����������ʂɓ��^���ꂽ��A���S���邱�Ƃ�����B |
|
�E |
�ƒ{�̎�����A�q�����Ȃǂ��l�����A����҂��o�ς����łȂ��A�H�̈��S�A�ƒ{�̈��S�ɂ��l�����ׂ��ł���Ƃ����悤�ȃA�j�}���E�F���t�F�A�Ƃ����l����������B |
 �@�����ΏۂƂ����������̌Â����ɖ{�̒����猻�ꂽ�u�������W�v�i��Ô���A�V�����Ɂj�ɂ͂��̉̂��f�ڂ��ꂽ�łɂ����tⳂ��\���Ă����B���\�������A�ǂ̂悤�ȗ��R�œ\�������A�͑S���o���Ă��Ȃ��B
�@�����ΏۂƂ����������̌Â����ɖ{�̒����猻�ꂽ�u�������W�v�i��Ô���A�V�����Ɂj�ɂ͂��̉̂��f�ڂ��ꂽ�łɂ����tⳂ��\���Ă����B���\�������A�ǂ̂悤�ȗ��R�œ\�������A�͑S���o���Ă��Ȃ��B �@���̒Z�ҏW�̍ŏ��́u�Q�R���v�ŁA�h�C�c�̎i�@���x�Ƃ������̂ɕ������^�O���A�c��P�P�҂ɉe�𗎂Ƃ��Ă��܂��܂����B
�@���̒Z�ҏW�̍ŏ��́u�Q�R���v�ŁA�h�C�c�̎i�@���x�Ƃ������̂ɕ������^�O���A�c��P�P�҂ɉe�𗎂Ƃ��Ă��܂��܂����B �@�O��ŏ����G�ꂽ�u�C�M���X�ώ@���T�v�i�� �]�A���}�Ёj�͂ƂĂ��ʔ����i���̎茳�ɂ���̂́u�呝��V�ҏS�Łv�ł���j�B
�@�O��ŏ����G�ꂽ�u�C�M���X�ώ@���T�v�i�� �]�A���}�Ёj�͂ƂĂ��ʔ����i���̎茳�ɂ���̂́u�呝��V�ҏS�Łv�ł���j�B �@�}���ق����o�����u�w�ǂ��ւ��s���Ȃ��x���v�i�����Ёj�̒��҂ł���� �]����́A���ɂƂ��Ă̓G�b�Z�C�X�g�A�����w�҂ł���A�����{�E�搶�ƌ����Ă���l���A�����ɃC�M���X����D���Ȑl���Łu�C�M���X�͂��������v�i���}�Ёj�A�u�C�M���X�͖������v�i���}�Ёj�u�C�M���X�ώ@���T�v�i���}�Ёj�̒��҂ł��邱�ƒ��x�̗����������B�C�M���X�֘A�̂���珑���͎茳�ɂ���܂ɐG��Ċy�����ǂ�ł����B
�@�}���ق����o�����u�w�ǂ��ւ��s���Ȃ��x���v�i�����Ёj�̒��҂ł���� �]����́A���ɂƂ��Ă̓G�b�Z�C�X�g�A�����w�҂ł���A�����{�E�搶�ƌ����Ă���l���A�����ɃC�M���X����D���Ȑl���Łu�C�M���X�͂��������v�i���}�Ёj�A�u�C�M���X�͖������v�i���}�Ёj�u�C�M���X�ώ@���T�v�i���}�Ёj�̒��҂ł��邱�ƒ��x�̗����������B�C�M���X�֘A�̂���珑���͎茳�ɂ���܂ɐG��Ċy�����ǂ�ł����B �@�ŋ߂̎����B��ʐ^�͂��ׂăf�W�^���E�J�����ɂ��J���[�ʐ^�ł���B�ƒ�̋L�O�ʐ^�͌����܂ł��Ȃ��A���ԂƂ̎ʐ^�W��ʐ^�W�ׂ̈̎ʐ^�������ł���B�����̕��X�������ȏ�ʂŎB����ʐ^�����l���낤�B
�@�ŋ߂̎����B��ʐ^�͂��ׂăf�W�^���E�J�����ɂ��J���[�ʐ^�ł���B�ƒ�̋L�O�ʐ^�͌����܂ł��Ȃ��A���ԂƂ̎ʐ^�W��ʐ^�W�ׂ̈̎ʐ^�������ł���B�����̕��X�������ȏ�ʂŎB����ʐ^�����l���낤�B �@�茳�ɒ��҂̋ޒ�T�C��������u�痢�̗��j�Ɠ`���v�i�k�c���O�A�i���j���{�痢�Z���^�[�j�Ƃ����{�Ƃ����ɋ��܂ꂽ�����q�u���y�J���^������v�i���c�s���y���b���邽���y��j������B�߂��̌Ö{���ŏ\���N�O�ɔ��������Ƃ��o���Ă���B�{�������l���Ö{���ɔ������̂��낤�B�ߋ��ɂ����҂̏����̂���ޒ�{���Ö{���Ŕ��������Ƃ�����̂ŁA���̂��Ǝ��̂ɂ͂���قǂ̋����͊����Ȃ��������A�����Ă��ꂽ���҂ɑ��Ă͎���ȑԓx���낤�B
�@�茳�ɒ��҂̋ޒ�T�C��������u�痢�̗��j�Ɠ`���v�i�k�c���O�A�i���j���{�痢�Z���^�[�j�Ƃ����{�Ƃ����ɋ��܂ꂽ�����q�u���y�J���^������v�i���c�s���y���b���邽���y��j������B�߂��̌Ö{���ŏ\���N�O�ɔ��������Ƃ��o���Ă���B�{�������l���Ö{���ɔ������̂��낤�B�ߋ��ɂ����҂̏����̂���ޒ�{���Ö{���Ŕ��������Ƃ�����̂ŁA���̂��Ǝ��̂ɂ͂���قǂ̋����͊����Ȃ��������A�����Ă��ꂽ���҂ɑ��Ă͎���ȑԓx���낤�B �@���N�O�̂ǂ̐V���̉̒d���������A�L���͒肩�ł͂Ȃ����u�S�̕�ɔ��\�̗F�����������s�̕ʂ�̘̉a���v���I��Ă����B�u������s�v�ɂ́u�Ȃ��܂���v�ƃ��r���U���Ă������B
�@���N�O�̂ǂ̐V���̉̒d���������A�L���͒肩�ł͂Ȃ����u�S�̕�ɔ��\�̗F�����������s�̕ʂ�̘̉a���v���I��Ă����B�u������s�v�ɂ́u�Ȃ��܂���v�ƃ��r���U���Ă������B �@�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�V�[���b�n�̒���ɋ����������A�Z�ҏW�Q��i�̌�ɓǂ̂ł����i����i���j�A��������̂�������҂ł����B
�@�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�V�[���b�n�̒���ɋ����������A�Z�ҏW�Q��i�̌�ɓǂ̂ł����i����i���j�A��������̂�������҂ł����B �@�O��ɑ�����Y �����́u����o�[���E�g�D�[�h�v���ꕶ�B
�@�O��ɑ�����Y �����́u����o�[���E�g�D�[�h�v���ꕶ�B �u����w�o�[���E�g�D�[�h�v�i����i�mRound 1�A�`�h�́w��ɉ����Ȃ�x�𗝉��ł��邩�v�n�i������w�o�ʼn�j�́A���Ȃ�ǂݐi��ŁA�ǂ�������ށA���i�̏����Ȃ̂��A����w�̉��ɂ��Ăǂ̂悤�Ȑ���ŏ����ꂽ�{�Ȃ̂������������B
�u����w�o�[���E�g�D�[�h�v�i����i�mRound 1�A�`�h�́w��ɉ����Ȃ�x�𗝉��ł��邩�v�n�i������w�o�ʼn�j�́A���Ȃ�ǂݐi��ŁA�ǂ�������ށA���i�̏����Ȃ̂��A����w�̉��ɂ��Ăǂ̂悤�Ȑ���ŏ����ꂽ�{�Ȃ̂������������B �@�O��Z�F�M����s�����s���Ă����`���[�t���b�g�Ɍf�ڂ���Ă����u�킽����Y�v�̎�܍�i�ɂ���āg������h�Ƃ������t��m�����B�g���Ԃ��h�͒m���Ă��邪�g������h�͒m��Ȃ������B�������l�ɒ��ڕԂ��̂́g���Ԃ��h�A����������̒N���ɑ���Ƃ����̂��g������h���������B
�@�O��Z�F�M����s�����s���Ă����`���[�t���b�g�Ɍf�ڂ���Ă����u�킽����Y�v�̎�܍�i�ɂ���āg������h�Ƃ������t��m�����B�g���Ԃ��h�͒m���Ă��邪�g������h�͒m��Ȃ������B�������l�ɒ��ڕԂ��̂́g���Ԃ��h�A����������̒N���ɑ���Ƃ����̂��g������h���������B �@�O�X��̂��̗��Řa�c���́u�ϓ֔b���v�����グ�����A���̌�u������x�@�ϓ֔b���v�i�i�i���N�Ёj������̂ɋC���t�����B
�@�O�X��̂��̗��Řa�c���́u�ϓ֔b���v�����グ�����A���̌�u������x�@�ϓ֔b���v�i�i�i���N�Ёj������̂ɋC���t�����B �u���҂����̉�L�@��݂�����w���̕����x�v�i���}�Ѓ��C�u�����[�A���r���q�j����Ɏ�����̂ɂ͊i�ʂ̗��R�͂Ȃ��B���̏����ȗ��R�͂�����A�V���̏��ЏЉ�̖ł��g���Ắu���B�lj揄�薳�d�Ȏԗ��v�Ƃ������o���̕��͂������B
�u���҂����̉�L�@��݂�����w���̕����x�v�i���}�Ѓ��C�u�����[�A���r���q�j����Ɏ�����̂ɂ͊i�ʂ̗��R�͂Ȃ��B���̏����ȗ��R�͂�����A�V���̏��ЏЉ�̖ł��g���Ắu���B�lj揄�薳�d�Ȏԗ��v�Ƃ������o���̕��͂������B �@�ǂ��ǂ�ł��ʔ����B�ǂ�����ǂ�ł��ʔ����B
�@�ǂ��ǂ�ł��ʔ����B�ǂ�����ǂ�ł��ʔ����B �@������悤�Ƃ������Ă��Ȃ��}���قŃG�b�Z�C�̒I���̂�т�ƒ��߂Ă���Ɗp�c����Ƃ��������ڂɓ������B���̖��O�͔ޏ������؏܂���܂������ɐV���ɏ����Ă����ӎ��ɂ���ċL�����Ă���B�f���Ȃ������́A�l����\���Ă���悤�ȕ��͂��Ǝv���Ċ��S���ēǂ��Ƃ��o���Ă���B
�@������悤�Ƃ������Ă��Ȃ��}���قŃG�b�Z�C�̒I���̂�т�ƒ��߂Ă���Ɗp�c����Ƃ��������ڂɓ������B���̖��O�͔ޏ������؏܂���܂������ɐV���ɏ����Ă����ӎ��ɂ���ċL�����Ă���B�f���Ȃ������́A�l����\���Ă���悤�ȕ��͂��Ǝv���Ċ��S���ēǂ��Ƃ��o���Ă���B �@���̐l���Љ�ɔ������L�Ƃ̏C���ꂪ���]�_�Ƌ{��N�펁�́u���{�Ƃ��Ă̏㋉��b�v�i�V���I���j���߁X�o�ł���邱�Ƃ�m�����̂� Podcast �ŕ����Ă��������̕����ǂ̃��W�I�ԑg���炾�����B�����ł́u�P�Ɍ��t����ׂ��̈Ӗ��m�ɂ��邾���łȂ��A���������N��̌��t���������߂鏑���v�ƌ����悤�Ȍ��t�ŏЉ��Ă����B
�@���̐l���Љ�ɔ������L�Ƃ̏C���ꂪ���]�_�Ƌ{��N�펁�́u���{�Ƃ��Ă̏㋉��b�v�i�V���I���j���߁X�o�ł���邱�Ƃ�m�����̂� Podcast �ŕ����Ă��������̕����ǂ̃��W�I�ԑg���炾�����B�����ł́u�P�Ɍ��t����ׂ��̈Ӗ��m�ɂ��邾���łȂ��A���������N��̌��t���������߂鏑���v�ƌ����悤�Ȍ��t�ŏЉ��Ă����B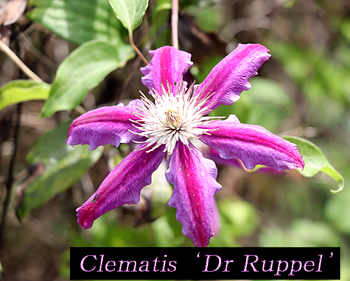 �@�����ɂ��ƁA����Ƃ́u��t�����̂邱�Ɓv�A��t�Ƃ́u�������Ƃ܂��͎Ў��Ȃǂɋ��K�E���i�邱�Ɓv�Ƃ���B Donation �Ƃ́u��t�A�v���Ӗ�����B
�@�����ɂ��ƁA����Ƃ́u��t�����̂邱�Ɓv�A��t�Ƃ́u�������Ƃ܂��͎Ў��Ȃǂɋ��K�E���i�邱�Ɓv�Ƃ���B Donation �Ƃ́u��t�A�v���Ӗ�����B �@�ܓx����ɍl�����ꍇ�A�A���X�J�������A�����J���O���Ɖ��m�������l���������{�Ƃ͑�̓����͈͂ɂ���̂��Ȃ��A�����ƃA�e�l�͂قړ����悤�Ȉܓx�ɂ���Ȃ��A�����h����p���͖k�C���̗y���k�Ɉʒu����̂��Ɓu�傫�ȕ����̒n�}���v�i�鍑���@�j���ڂ��蒭�߂Ȃ���A���{�Ɛ��E�̊���̍��A���{�̓s�s�Ɛ��E�̊���̓s�s�̏��ݒn�̈ܓx�ɂ��čl���Ă����B
�@�ܓx����ɍl�����ꍇ�A�A���X�J�������A�����J���O���Ɖ��m�������l���������{�Ƃ͑�̓����͈͂ɂ���̂��Ȃ��A�����ƃA�e�l�͂قړ����悤�Ȉܓx�ɂ���Ȃ��A�����h����p���͖k�C���̗y���k�Ɉʒu����̂��Ɓu�傫�ȕ����̒n�}���v�i�鍑���@�j���ڂ��蒭�߂Ȃ���A���{�Ɛ��E�̊���̍��A���{�̓s�s�Ɛ��E�̊���̓s�s�̏��ݒn�̈ܓx�ɂ��čl���Ă����B|
�@��e�͔ނ�15�ɂȂ����Ƃ��A�q�t�ɂ������Ő_�w�Z�ɓ��ꂽ�B����͕��̂Ȃ��q������Ŋw����C�߂邱�Ƃ̂ł���B��̓��ł������B�����Ŏ��R�̂Ȃ����ꂵ�����X������������A�`���[�r���Q����w�_�w���i�B���̊w���̐�y�ɂ̓w�[�Q���A�w���_�[�����A���[���P�Ȃǂ����������镶�l�A�N�l���������AWH�͂��̊w��ɂȂ��ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������B�������A�_�w�Z�ł̋K�������������ő̂���v�ɂȂ����̂��K���A�F�l�����Ɠk�����s���y���ނȂNJw�������i�����B |
|
�n�E�t�̕�@ |
�n�E�t�̋����@ |
|
�@�Ƃ���ŁA�u�����v�̑�R�b�g����ꂽ��̘b�h�̎����́A�|���e�E���F�b�L�I�i Ponte �͋��A Vecchio �͌Â��Ƃ����Ӗ��j�ł̐Ԃ��}���g�𒅂��j�Ƃ̏o�����n�܂�B 1993�N �X���A�C�^���A�ŊJ���ꂽ���ۉ�c�ɏo�������@��Ƀt�B�����c�F�ɗ�������Ă��̋�������Ă݂��i�ʐ^�E�j�B |
 �@�킪�s�̎s���}���ق���͖��� 10 ���� 25 ���ɃC���^�[�l�b�g�o�R�Ń��[���}�K�W���������Ă���B
�@�킪�s�̎s���}���ق���͖��� 10 ���� 25 ���ɃC���^�[�l�b�g�o�R�Ń��[���}�K�W���������Ă���B|
�� |
�}���كC���t�H���[�V���� |
|
�� |
�{�̏Љ� �����o��������u�}���ِE�������܂ł̓Ǐ��̌��̒�����Љ���ʂ�1���v |
|
�� |
���ו���`���܂� |
|
�� |
�q�ǂ��̖{���Ă������낢�I ����[�u�b�N�� |
|
�� |
���ԗ\���L���O�i���|�ȊO�j |
|
�� |
�x�فi���j���̂��m�点 |
 �@ 23 �N�Ԃɘj���ăx���M�[�Ɋւ���Ă������҂��x���M�[�Ƃ̐G�ꍇ���̒��Ŋ��������܂��܂��G�b�Z�C�̌`�Ŏ��Z�߂��u���ꂽ���̃x���M�[�v�i�{���쏏�q�A�ۑP�u�b�N�X�j�͂��낢��Ȑ���Ńx���M�[��`���Ă��邪�A���̖{���́u�x���M�[�C���v���������Ƃɂ���̂��낤�B�Z���œǂ݈Ղ��G�b�Z�C�W�������B�܂��A�e�G�b�Z�C�ɓY����ꂽ�M�� �����̃X�P�b�`���f���炵���B
�@ 23 �N�Ԃɘj���ăx���M�[�Ɋւ���Ă������҂��x���M�[�Ƃ̐G�ꍇ���̒��Ŋ��������܂��܂��G�b�Z�C�̌`�Ŏ��Z�߂��u���ꂽ���̃x���M�[�v�i�{���쏏�q�A�ۑP�u�b�N�X�j�͂��낢��Ȑ���Ńx���M�[��`���Ă��邪�A���̖{���́u�x���M�[�C���v���������Ƃɂ���̂��낤�B�Z���œǂ݈Ղ��G�b�Z�C�W�������B�܂��A�e�G�b�Z�C�ɓY����ꂽ�M�� �����̃X�P�b�`���f���炵���B �@��w�ʐ^���̌�y���u�o�[�~�����c�e�v�Ƃ̃^�C�g���̎���̎ʐ^���W�߂��ʐ^�W���Ă��ꂽ�B�ނ͎���萔�ΎႭ��������̎ʐ^�������ł̒��ڂ̐ړ_�͂Ȃ��������A�ŋ߂Ɏ��艽�̃��[���̌����肪�������B
�@��w�ʐ^���̌�y���u�o�[�~�����c�e�v�Ƃ̃^�C�g���̎���̎ʐ^���W�߂��ʐ^�W���Ă��ꂽ�B�ނ͎���萔�ΎႭ��������̎ʐ^�������ł̒��ڂ̐ړ_�͂Ȃ��������A�ŋ߂Ɏ��艽�̃��[���̌����肪�������B �@�t�B�N�V�����A�m���t�B�N�V�������܂߂Ă����ȕ����ǂ�ł���Ƃ����ɖ���̓�������o�Ă��邱�Ƃ�����B���̂��тɎ��́u�Ɛl�̖ړI�͉����낤�v�Ǝv���Ă��܂��B����𓐂Ƃ��Ă��������p�i�s��ł͔���Ȃ��B�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�閧���Ɉ��D�Ƃɔ������Ƃ��Ă��w���҂͑��l�ɂ��̖���������Ď���̏N�W�i���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������n���̏N�W�i�ۊǎ��Ń��C�������݂Ȃ��璭�߂ĂЂƂ�ŗD�z������������ł���B������l���y���ނ��߂����ɋɂ߂Ċ댯�ȓ������Ƃ͎v���Ȃ��B
�@�t�B�N�V�����A�m���t�B�N�V�������܂߂Ă����ȕ����ǂ�ł���Ƃ����ɖ���̓�������o�Ă��邱�Ƃ�����B���̂��тɎ��́u�Ɛl�̖ړI�͉����낤�v�Ǝv���Ă��܂��B����𓐂Ƃ��Ă��������p�i�s��ł͔���Ȃ��B�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�閧���Ɉ��D�Ƃɔ������Ƃ��Ă��w���҂͑��l�ɂ��̖���������Ď���̏N�W�i���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������n���̏N�W�i�ۊǎ��Ń��C�������݂Ȃ��璭�߂ĂЂƂ�ŗD�z������������ł���B������l���y���ނ��߂����ɋɂ߂Ċ댯�ȓ������Ƃ͎v���Ȃ��B �@���͏����ɂ��Ă͋�̓����𗝉����Ă�����x�̐l�Ԃł��邪�A���m�������𗣂�ď������{�͉�������ۗL���Ă���B����ɂ����̐l�̃C���^�r���[�ł̔����Ȃǂ̊���͋L�����Ă���B
�@���͏����ɂ��Ă͋�̓����𗝉����Ă�����x�̐l�Ԃł��邪�A���m�������𗣂�ď������{�͉�������ۗL���Ă���B����ɂ����̐l�̃C���^�r���[�ł̔����Ȃǂ̊���͋L�����Ă���B �@ 2022�N11��26 ���t�̓ǔ��V���[���́u���ܕ��v���ɍ���玟�����u�d�ԃX�}�z�w�V���̂P�x�̓�v�Ƒ肵��
�@ 2022�N11��26 ���t�̓ǔ��V���[���́u���ܕ��v���ɍ���玟�����u�d�ԃX�}�z�w�V���̂P�x�̓�v�Ƒ肵��|
�Z |
����̎������͈�l�����̓Ɨ��������Ԃ���������B������Ƃڂ��肵�悤�B |
|
�Z |
���Ƃ������݂��u���A���Ȏ��v����u�i�l����Z�߂��j�f�W�^���Ȏ��v�ւƓ���ւ���Ă䂭�B |
|
�Z |
���_�o�Ōy���Ȍ��t�ł��ӂꂽ���E�B�l�b�g��ɑ��݂�����̑����ɂ͎������Ȃ��B |
|
�Z |
���オ�Ⴍ�Ȃ�قǁA�R�s�y�����f���p�������Ȃ����肩�A������p�ł���Ƃ����ӎ��������Ȃ��Ă���B�i���͒m�I���L����N�Q����Ƃ�ł��Ȃ��l���A�s�ׂ��ƕ���Ă��邪�j |
|
�Z |
�Ⴂ����ɂȂ�Ȃ�قǁA���ɋL���ꂽ���t�����A�l�b�g��̌��t��M�p���Ă��܂��B |
|
�Z |
���̖{���v�l��b����B�菑�����]��������������B�i�u���̂Ƃ���v�Ǝv���Ȃ�����A���̕��͂̓p�\�R���ɓ��͂��Ă���j |
|
�Z |
�������t���X�g�b�N�A�l�b�g���t���t���[�B�������t���u���v�̒��Ɍ@��ꂽ��˂ɗ��܂��Ă����Ƃ���A�l�b�g���t�́u�F�v�̊Ԃ��̂悤�ɗ���Ă䂭�B�O��������ΖY�ꋎ����B�i�ƌ������̂̒m��Ȃ��Ƃ���ʼn����܂ł��c��̂ł́H�j |
 �@�}���ق̐V���{�ē������Ă�����u���������̐��m���p�v�i�J�� ���A�͏o���[�V�Ёj���ڂɗ��܂����B�����̒��Ɍ���鐼�m���p��_�����{���낤�A�ǂ̂悤�Ȑ��m���p���N�̏����ɂǂ̂悤�ȃV�`���G�[�V�����łǂ̂悤�ɕ`����Ă���̂��ɂ��Ă̖{���낤�A�ƒP���Ɏv�����B
�@�}���ق̐V���{�ē������Ă�����u���������̐��m���p�v�i�J�� ���A�͏o���[�V�Ёj���ڂɗ��܂����B�����̒��Ɍ���鐼�m���p��_�����{���낤�A�ǂ̂悤�Ȑ��m���p���N�̏����ɂǂ̂悤�ȃV�`���G�[�V�����łǂ̂悤�ɕ`����Ă���̂��ɂ��Ă̖{���낤�A�ƒP���Ɏv�����B �@���āu�m�I�����v��u�����̕i�i�v�Ƃ����^�C�g���̏��Ђ����������s����A�悭�ǂ܂ꂽ�B�����u�m�I�����̕��@�v�u���E�m�I�����̕��@�v�i��������n������A�u�k�Ќ���V���j��u���Ƃ̕i�i�v�i�������F�A�V���V���j����͑����̎������B
�@���āu�m�I�����v��u�����̕i�i�v�Ƃ����^�C�g���̏��Ђ����������s����A�悭�ǂ܂ꂽ�B�����u�m�I�����̕��@�v�u���E�m�I�����̕��@�v�i��������n������A�u�k�Ќ���V���j��u���Ƃ̕i�i�v�i�������F�A�V���V���j����͑����̎������B �@�ŋ߂ł́u�����ǂ݁v�ȂǂƂ������t�́A���ɂƂ��ĉ������݂ɂȂ��Ă���B�i�����L�x�Ȓ��̏��X�̌����̌��ʗ����ǂ݂̋@����������Ƃ����邪�A���͂̈��������̎���ł��낤�Ǝv���Ă���B�Ƃ��낪���ŋ߁A�����Ȃ����}���قŁA�����ǂ݂��o�������B
�@�ŋ߂ł́u�����ǂ݁v�ȂǂƂ������t�́A���ɂƂ��ĉ������݂ɂȂ��Ă���B�i�����L�x�Ȓ��̏��X�̌����̌��ʗ����ǂ݂̋@����������Ƃ����邪�A���͂̈��������̎���ł��낤�Ǝv���Ă���B�Ƃ��낪���ŋ߁A�����Ȃ����}���قŁA�����ǂ݂��o�������B �@���ɂ����Ă��āu�V���[���b�N�E�z�[���Y�̔閧�t�@�C���v�i�W���[���E�g���X�����A���c�R�I��A�n���������Ɂj�Ɓu�V���[���b�N�E�z�[���Y���̑f�G�Ȗ`���v�i�� J.H. ���g�X�����m���A�j�R���X�E���C���[�ҁA�c���Z���A�}�K�Ѓ~�X�e���[�j���������B���̂ɂ��̂Q�����c����Ă���̂��A�s�v�c�Ɏv�����B
�@���ɂ����Ă��āu�V���[���b�N�E�z�[���Y�̔閧�t�@�C���v�i�W���[���E�g���X�����A���c�R�I��A�n���������Ɂj�Ɓu�V���[���b�N�E�z�[���Y���̑f�G�Ȗ`���v�i�� J.H. ���g�X�����m���A�j�R���X�E���C���[�ҁA�c���Z���A�}�K�Ѓ~�X�e���[�j���������B���̂ɂ��̂Q�����c����Ă���̂��A�s�v�c�Ɏv�����B �@���͌����_�œd�q���Ђ͈�����ۗL���Ă��Ȃ����A�܂����ʂ܂ŕۗL���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă���B
�@���͌����_�œd�q���Ђ͈�����ۗL���Ă��Ȃ����A�܂����ʂ܂ŕۗL���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă���B �@�X�N���b�v�ƌ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ����A�V���A�G�����̑����X�̈�����ɏ����ꂽ������ƋC�ɂȂ�L���́A�Y���ł����̂܂܃r���r���Ɣj������A�Y���L����蔲�����肵�Ď��n��Ɉ��̏ꏊ�ɕۊǂ��Ă���B�̌n�����������͈���Ă��Ȃ��B���X�������Ă��̎��_�ŕs�v�Ǝv�������̂͏������Ă��邽�ߑ����̈���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
�@�X�N���b�v�ƌ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ����A�V���A�G�����̑����X�̈�����ɏ����ꂽ������ƋC�ɂȂ�L���́A�Y���ł����̂܂܃r���r���Ɣj������A�Y���L����蔲�����肵�Ď��n��Ɉ��̏ꏊ�ɕۊǂ��Ă���B�̌n�����������͈���Ă��Ȃ��B���X�������Ă��̎��_�ŕs�v�Ǝv�������̂͏������Ă��邽�ߑ����̈���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �@���̘V����h���ړI�ł̊����̏��������K���A�Ȃƍ���̕����ł��Ă��āA�C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B�n��Ƃ��ďo�Ă��銿���͒����ɏ�����̂����A�����������P�ǂ݂Ō�����Ɓu��H�v�ƍl���邱�Ƃ������N����B
�@���̘V����h���ړI�ł̊����̏��������K���A�Ȃƍ���̕����ł��Ă��āA�C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B�n��Ƃ��ďo�Ă��銿���͒����ɏ�����̂����A�����������P�ǂ݂Ō�����Ɓu��H�v�ƍl���邱�Ƃ������N����B �@���͎����ɂ��Ȃ�Ȃ����莕�Ȉ�@�ɂ͍s���Ȃ��A�Ƃ������Ȉ�t���猩��Ό��ꓹ�f�Ȋ��҂ł���B�Z��̂悤�Ɉ�����]�킪���Ȉ�t�ł��邽�߂��̂悤�ȑӑĂȑԓx�𑱂��Ă���B
�@���͎����ɂ��Ȃ�Ȃ����莕�Ȉ�@�ɂ͍s���Ȃ��A�Ƃ������Ȉ�t���猩��Ό��ꓹ�f�Ȋ��҂ł���B�Z��̂悤�Ɉ�����]�킪���Ȉ�t�ł��邽�߂��̂悤�ȑӑĂȑԓx�𑱂��Ă���B �@�W���C�A���g�n�ꎁ�i1999�N1��31�������j�ɑ�����2022�N10��1���Ƀv�����X���[�̃A���g�j�I���؎����S���Ȃ����B�}�X���f�B�A�̓v�����X���[�Ƃ��ẮA�܂������ƂƂ��Ă̎��̊���E���т���B
�@�W���C�A���g�n�ꎁ�i1999�N1��31�������j�ɑ�����2022�N10��1���Ƀv�����X���[�̃A���g�j�I���؎����S���Ȃ����B�}�X���f�B�A�̓v�����X���[�Ƃ��ẮA�܂������ƂƂ��Ă̎��̊���E���т���B �@���ēǂ݂����ȈӖ��Ŋ��������{�����N����ɓǂƂ���A�u�������Ƃ͏����Ă��邪�A����قǂł��Ȃ��ȁv�u���ɂ��Ċ��������̂��낤�v�u�ǂ������Đl�ɑE�߂��̂��낤�v�Ǝv�����Ƃ���ɂ���B
�@���ēǂ݂����ȈӖ��Ŋ��������{�����N����ɓǂƂ���A�u�������Ƃ͏����Ă��邪�A����قǂł��Ȃ��ȁv�u���ɂ��Ċ��������̂��낤�v�u�ǂ������Đl�ɑE�߂��̂��낤�v�Ǝv�����Ƃ���ɂ���B �@������R�Z���`�̕��ɖ{�u��ケ�ƂΎ��T�v�i�q���j�z�ҁA�u�k�Њw�p���Ɂj������B���̖{�͎��T�ł����莖�T�ł�����B���t�̈Ӗ���p��Ȃǂ�m�邽�߁i���T�j�����łȂ��A������\����̉���i���T�j�����Ă����B���܂��Ɂu�����̌����͔��������O���Ă͐������Ȃ��B��ケ�Ƃ̔������A�ʂ�������ł��邾�����m�ɓ`���邽�߁v�Ƃ̍l������S�Ă̌��t�ɃA�N�Z���g�������t����Ă���B
�@������R�Z���`�̕��ɖ{�u��ケ�ƂΎ��T�v�i�q���j�z�ҁA�u�k�Њw�p���Ɂj������B���̖{�͎��T�ł����莖�T�ł�����B���t�̈Ӗ���p��Ȃǂ�m�邽�߁i���T�j�����łȂ��A������\����̉���i���T�j�����Ă����B���܂��Ɂu�����̌����͔��������O���Ă͐������Ȃ��B��ケ�Ƃ̔������A�ʂ�������ł��邾�����m�ɓ`���邽�߁v�Ƃ̍l������S�Ă̌��t�ɃA�N�Z���g�������t����Ă���B �@�������ł͕����V�N�x�ȍ~���N�S����16�Έȏ�̒j����ΏۂɁu����Ɋւ��鐢�_�����v�����{���Ă���B���̖ړI�́u���{�l�̍���Ɋւ���ӎ��◝���̌���ɂ��Ē������C����{��̗��ĂɎ�����ƂƂ��ɁC�����̍���Ɋւ��鋻���E�S�����N����v���Ƃɂ���Ƃ����B
�@�������ł͕����V�N�x�ȍ~���N�S����16�Έȏ�̒j����ΏۂɁu����Ɋւ��鐢�_�����v�����{���Ă���B���̖ړI�́u���{�l�̍���Ɋւ���ӎ��◝���̌���ɂ��Ē������C����{��̗��ĂɎ�����ƂƂ��ɁC�����̍���Ɋւ��鋻���E�S�����N����v���Ƃɂ���Ƃ����B �@�ǂ��œǂ̂��낤���A�V�g�̏���ɂ��ď����ꂽ���͂��L�����Ă���B�L����H��Ƃ����ɂ́u���[���b�p�G��ő����`����Ă�����̂̈�ɓV�g����������B��\�I�Ȃ��̂Ƃ��Ắw��ٍ��m�x�̑�V�g�K�u���G���ł��낤�v�Ƃ���A��������V�g�����̃q�G�����L�[�ɘb���y�ԁB
�@�ǂ��œǂ̂��낤���A�V�g�̏���ɂ��ď����ꂽ���͂��L�����Ă���B�L����H��Ƃ����ɂ́u���[���b�p�G��ő����`����Ă�����̂̈�ɓV�g����������B��\�I�Ȃ��̂Ƃ��Ắw��ٍ��m�x�̑�V�g�K�u���G���ł��낤�v�Ƃ���A��������V�g�����̃q�G�����L�[�ɘb���y�ԁB|
�Z |
���҂̓p�E���ɏ]���M�ɓ������l���ł���A���̒����́u�f�B�I�j���V�I�X�����v�ƌĂ�A�L���X�g���W�̕����̂Ȃ��Łu�����Ɏ������Ёv�������Ă����B |
|
�Z |
�������A19���I������20���I�����ɂ����ĂȂ��ꂽ���ؓI�Ȍ����ɂ���Ă���當���͋I��500�N���ɏ����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��m���ꂽ�B�������A�����_�ł́A�^�̒��҂��N�ł��邩�Ƃ������Ƃ��m�肳��Ă��Ȃ����߂��̒��҂��u�U�f�B�I�j���V�I�X�x�ƌĂ�ł���B |
|
�Z |
�u�V��ʊK�_�v�͓V�g�̒����g�D�Ƌ@�\��̌n�I�ɉ���������̂ł���B |
|
�Z |
�V�g�́A��ʁA���ʁA���ʂ̎O�K���ɕ������A�e�K�����O���ɕ������Ă���B�ŏ�ʂ̊K���ɂ����V�g�i���Ăj�A�q�V�g�i���Ăj�A���V�g�i���Ăj�������A���ʂ̊K���ɂ͎�V�g�i����Ăj�A�͓V�g�i�肫�Ăj�A�\�V�g�i�̂��Ăj�������A�ʼn��ʂ̊K���ɂ͌��V�g�i����Ăj�A��V�g�A�V�g�������Ă���B�i���ɂ͓V�g���X�ɕ��ނ���Ă���Ƃ������ƈȊO�ɂ͑S�������ł��Ȃ��j |
|
�Z |
�ʼn��ʂ̒m�������Ɂu�V�g�v�ƌĂ��̂́A���̊K���̒m���������l�Ԃɍł��߂��ʒu�ɂ��Đ_�̐_��������ɓ`�B���铭�����A�����̕����猩��Ƃ��ɂ܂��Ɂu�g�ҁv�Ƃ��Ă̓����ł��邩��ł���B |
 �@���Ԃ���킹�Ă��� ChatGPT ���g���Ă݂悤�ƃ\�t�g���C���X�g�[�������B�h�s���e���V�[�̒Ⴂ���Ƃ����F���Ă��鎄�ł��邩��A�p�\�R���ɃA�b�v���[�h����Ă��邢���ȋL���Ŏ��O�ɃC���X�g�[���̕��@������Ă������B���̌��ʁA�g���u�����Ȃ����������B
�@���Ԃ���킹�Ă��� ChatGPT ���g���Ă݂悤�ƃ\�t�g���C���X�g�[�������B�h�s���e���V�[�̒Ⴂ���Ƃ����F���Ă��鎄�ł��邩��A�p�\�R���ɃA�b�v���[�h����Ă��邢���ȋL���Ŏ��O�ɃC���X�g�[���̕��@������Ă������B���̌��ʁA�g���u�����Ȃ����������B �@���p�W�Ŕ����������̐}�^�ׂ̗ɓ����傫���̂P���̉�W�����ׂ��Ă���B�����̍��m���E�F�[�E�I�X���x�O100�L���̃��X�Ƃ��������Ȓ��ɂ������A���镪��ł͐��E���̋Z�p��L�����ЂƂ̋Z�p��g���������ɏI���A�I�X���s�X�ɖ߂�����̎U���̎��ɂӂ���Ɨ�����������X�Ŕ��������Ƃ��o���Ă���B
�@���p�W�Ŕ����������̐}�^�ׂ̗ɓ����傫���̂P���̉�W�����ׂ��Ă���B�����̍��m���E�F�[�E�I�X���x�O100�L���̃��X�Ƃ��������Ȓ��ɂ������A���镪��ł͐��E���̋Z�p��L�����ЂƂ̋Z�p��g���������ɏI���A�I�X���s�X�ɖ߂�����̎U���̎��ɂӂ���Ɨ�����������X�Ŕ��������Ƃ��o���Ă���B �@����O�V����́u�̉����t�v�i�u�k�Ёj��112�łɔ������Y���W���E�Ƒ肵�����͂�����B���W�̃p���t���b�g�ɏ����ꂽ���͂̂悤���B
�@����O�V����́u�̉����t�v�i�u�k�Ёj��112�łɔ������Y���W���E�Ƒ肵�����͂�����B���W�̃p���t���b�g�ɏ����ꂽ���͂̂悤���B �@�g�{�V�쌀�̉e�����낤���A���o�g�̎��^�����g�Ɍ���������̂��낤���A�e���r�ő��قƏ̂��Ďg���Ă���i�̂Ȃ��A�ΎG�Ȍ��t���C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��B�����������قȂ錾�t����������̂��낤���B�������ƌ����Ă��A�ےÁA�͓��A��B�ł͌��t�������傫���قȂ�B�b����l�͏��Ȃ��Ȃ������A���̒��S�ł���D��̒U�߂���₲���͂�̌��t�͂ƂĂ��������̂��B
�@�g�{�V�쌀�̉e�����낤���A���o�g�̎��^�����g�Ɍ���������̂��낤���A�e���r�ő��قƏ̂��Ďg���Ă���i�̂Ȃ��A�ΎG�Ȍ��t���C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��B�����������قȂ錾�t����������̂��낤���B�������ƌ����Ă��A�ےÁA�͓��A��B�ł͌��t�������傫���قȂ�B�b����l�͏��Ȃ��Ȃ������A���̒��S�ł���D��̒U�߂���₲���͂�̌��t�͂ƂĂ��������̂��B �@�C�y�ɓǂ�ł���]�ˎ����ΏۂƂ��������ɂ͐痼���Ƃ��������悭�����B�ŋ߂̃h���}�ł͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��m��Ȃ����A���Ă͐痼����S���������̎p���e���r��ʂł悭�������̂ł���B
�@�C�y�ɓǂ�ł���]�ˎ����ΏۂƂ��������ɂ͐痼���Ƃ��������悭�����B�ŋ߂̃h���}�ł͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��m��Ȃ����A���Ă͐痼����S���������̎p���e���r��ʂł悭�������̂ł���B �@�C�U���E�x���_�T�����`�ŏ����ꂽ�x�X�g�Z���[�u���{�l�ƃ��_���l�v�i�R�{���X�j���܂߂Ď茳�ɂ���R�{�������i1991�N�v�j�̏�����S�ď������悤�Ɛ������Ă���B
�@�C�U���E�x���_�T�����`�ŏ����ꂽ�x�X�g�Z���[�u���{�l�ƃ��_���l�v�i�R�{���X�j���܂߂Ď茳�ɂ���R�{�������i1991�N�v�j�̏�����S�ď������悤�Ɛ������Ă���B �@�}�X���f�B�A�́u�����J���Ȃ́i 2022 �N�X���j16���A�S���� 100 �Έȏ�̍���҂� 15 �����_�ŁA�O�N�� 4,016 �l����9�� 526 �l�ɂȂ����Ɣ��\�����B�c�c��������9����8�� 161 �l�ŁA�j����1�� 365 �l�������B�w�h�V�̓��x�i19���j��O�ɁA���J�Ȃ��W�v�����v�ƕ��B
�@�}�X���f�B�A�́u�����J���Ȃ́i 2022 �N�X���j16���A�S���� 100 �Έȏ�̍���҂� 15 �����_�ŁA�O�N�� 4,016 �l����9�� 526 �l�ɂȂ����Ɣ��\�����B�c�c��������9����8�� 161 �l�ŁA�j����1�� 365 �l�������B�w�h�V�̓��x�i19���j��O�ɁA���J�Ȃ��W�v�����v�ƕ��B �@ 2022�N9��10 ���̃}�X���f�B�A�́u���{�l���܂� 2,977 �l���]���ƂȂ��� 2001 �N�̕ē����e������11����21�N���}����B������m��Ȃ����オ�����钆�A�W�����{�ɂ͈⑰�炪�^�c���Ă����j���[���[�N�E�}���n�b�^���́w 9�E11 �g���r���[�g�����فx���������B�W�҂���͋L���̕�������Ԃސ����オ���Ă���v�ƕ��B
�@ 2022�N9��10 ���̃}�X���f�B�A�́u���{�l���܂� 2,977 �l���]���ƂȂ��� 2001 �N�̕ē����e������11����21�N���}����B������m��Ȃ����オ�����钆�A�W�����{�ɂ͈⑰�炪�^�c���Ă����j���[���[�N�E�}���n�b�^���́w 9�E11 �g���r���[�g�����فx���������B�W�҂���͋L���̕�������Ԃސ����オ���Ă���v�ƕ��B �u�c�ɂ̕�n�ɂĉr�߂�߉́v�Ɠ��{��ŏ����ꂽ�g�[�}�X�E�O���C�� ELEGY �����ɂ̕Ћ�����o�Ă����B���҂͑��c���V�����A���s���͌����Ђł���B�\���ɍd�������g��ꂽ�͂� 43 �ł̍��q�͏��a36�N���s�Œ艿��130�~�B
�u�c�ɂ̕�n�ɂĉr�߂�߉́v�Ɠ��{��ŏ����ꂽ�g�[�}�X�E�O���C�� ELEGY �����ɂ̕Ћ�����o�Ă����B���҂͑��c���V�����A���s���͌����Ђł���B�\���ɍd�������g��ꂽ�͂� 43 �ł̍��q�͏��a36�N���s�Œ艿��130�~�B �@���e�����������肵���o�܂₻�̍ۂɏ��X��ƌ��킵�����낢��Șb���v���o������{������B
�@���e�����������肵���o�܂₻�̍ۂɏ��X��ƌ��킵�����낢��Șb���v���o������{������B �@�P��ł����p����ƒʐM�̔���Ђ���͂��̌�͌p���I�ɂ��Ȃ蕪�����J�^���O�������Ă���B���s�㗝�X����̈ē��������ł���B���݉䂪�ƈ��ɂ͂��ꂼ��R�Ђ���̑��t������B���ʂ��Ȃ��Ǝv�����ʁA���ʓI�ɂ͌����I�ȉc�ƂȂ̂��낤�ƌ��_�t����̂͒����T�����[�}�������̐����B
�@�P��ł����p����ƒʐM�̔���Ђ���͂��̌�͌p���I�ɂ��Ȃ蕪�����J�^���O�������Ă���B���s�㗝�X����̈ē��������ł���B���݉䂪�ƈ��ɂ͂��ꂼ��R�Ђ���̑��t������B���ʂ��Ȃ��Ǝv�����ʁA���ʓI�ɂ͌����I�ȉc�ƂȂ̂��낤�ƌ��_�t����̂͒����T�����[�}�������̐����B �@�ǂ����u�������w�v�Ƃ������t�����̂ǂ����ɏZ�ݒ������悤���B�}���قʼn���T���Ƃ������Ă��Ȃ��A�I�����ɒ��߂Ă���Ɓu�������w����i�J�{�����A�����Џo�Łj�u�����T�[�r�X�_�v�i�ҏW�F�A����v�E��؉��c�A�����[�j�u�q�ǂ��Ɩ{�v�i�������q�A��g�V���j���ڂɎ~�܂����B
�@�ǂ����u�������w�v�Ƃ������t�����̂ǂ����ɏZ�ݒ������悤���B�}���قʼn���T���Ƃ������Ă��Ȃ��A�I�����ɒ��߂Ă���Ɓu�������w����i�J�{�����A�����Џo�Łj�u�����T�[�r�X�_�v�i�ҏW�F�A����v�E��؉��c�A�����[�j�u�q�ǂ��Ɩ{�v�i�������q�A��g�V���j���ڂɎ~�܂����B �@�V�������s���ꂽ�{�ɂ��Ă��������A�悭����Ă���{�ɂ��Ă��������A�ǂ̂悤�ȗ��ɏ�����Ă������͑S���o���Ă��Ȃ����A�V���̐��s�̋L���ł��̖{���Љ��Ă����B�u�m��Ȃ���p���������I�H�v�Ƃ̕���̕t���ꂽ��c�܂肦���u���{��h�����v�i�˓`�Љ������Ɂj�ł���B���҂͌��A�i�E���T�[���������B
�@�V�������s���ꂽ�{�ɂ��Ă��������A�悭����Ă���{�ɂ��Ă��������A�ǂ̂悤�ȗ��ɏ�����Ă������͑S���o���Ă��Ȃ����A�V���̐��s�̋L���ł��̖{���Љ��Ă����B�u�m��Ȃ���p���������I�H�v�Ƃ̕���̕t���ꂽ��c�܂肦���u���{��h�����v�i�˓`�Љ������Ɂj�ł���B���҂͌��A�i�E���T�[���������B �@���ɂ����Ă������쐽�꒘�́u�����ƃp���_�������v�i�^���[�j���ڂɕt�����B���N�O�ɔp�Ƃ����߂��̌Ö{����30�N�قǑO�ɔ��������Ƃ͊o���Ă���B���Ƃ����ɂ͒��҂̐��E�ɂ���ЂƁA���҂Ƃ̌�V�W�ɂ���ЂƂ́u�l���_�߂������́A�l�����A��V�^�A�����ă��N�C�G�������S�ł���v�Ə�����Ă����B
�@���ɂ����Ă������쐽�꒘�́u�����ƃp���_�������v�i�^���[�j���ڂɕt�����B���N�O�ɔp�Ƃ����߂��̌Ö{����30�N�قǑO�ɔ��������Ƃ͊o���Ă���B���Ƃ����ɂ͒��҂̐��E�ɂ���ЂƁA���҂Ƃ̌�V�W�ɂ���ЂƂ́u�l���_�߂������́A�l�����A��V�^�A�����ă��N�C�G�������S�ł���v�Ə�����Ă����B �@���e���Șb�����A�{�̓ǂݕ����N��ɂ���āA�l���o���ɂ���ĕς��A�Ƃ���������O�̂��ƂɋC���t�����B
�@���e���Șb�����A�{�̓ǂݕ����N��ɂ���āA�l���o���ɂ���ĕς��A�Ƃ���������O�̂��ƂɋC���t�����B �@���܂łɐ������̊ω����܂ɂ��ڂɂ������Ă����B�v���o�������ł����낢��Ȃ�����W����Ŕq�ς������ω��A���ω��A�\��ʊω��A�@�ӗ֊ω�������A��O���ł͗k�M�܊ω��A���ܖ�̓��[�ł͂����ƒu���ꂽ�n���ω��ɂ��ڂɂ��������B
�@���܂łɐ������̊ω����܂ɂ��ڂɂ������Ă����B�v���o�������ł����낢��Ȃ�����W����Ŕq�ς������ω��A���ω��A�\��ʊω��A�@�ӗ֊ω�������A��O���ł͗k�M�܊ω��A���ܖ�̓��[�ł͂����ƒu���ꂽ�n���ω��ɂ��ڂɂ��������B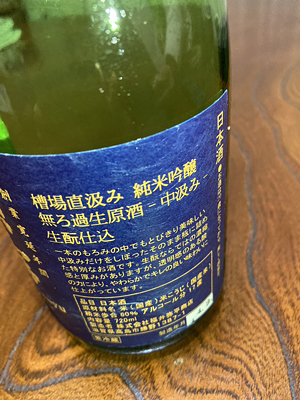 �@���I�̕Ћ����當�ɖ{�̑傫���̏��a52�N���s�u�z���o�̗��s�́v�i�V���y���o�ŎЁj���o�Ă����B���t�ɂ͓��{���y���쌠����F�恛���Z�Ԃ̋L�ڂƋ���JASRUC���؎����\���Ă���A���쌠�����͂�������ƂȂ���Ă��邱�Ƃ��M�킹��B���e�͂ƌ����Ώ��a�R�N�́u�o�D�v�u�g���̍`�v���珺�a35�N�́u���J�������Ă�ł���v�u�����炢�v�܂�438�̗̉w�Ȃ̉̎�����������ł���B���a52�N�������Ŕ��s�Ƃ���B
�@���I�̕Ћ����當�ɖ{�̑傫���̏��a52�N���s�u�z���o�̗��s�́v�i�V���y���o�ŎЁj���o�Ă����B���t�ɂ͓��{���y���쌠����F�恛���Z�Ԃ̋L�ڂƋ���JASRUC���؎����\���Ă���A���쌠�����͂�������ƂȂ���Ă��邱�Ƃ��M�킹��B���e�͂ƌ����Ώ��a�R�N�́u�o�D�v�u�g���̍`�v���珺�a35�N�́u���J�������Ă�ł���v�u�����炢�v�܂�438�̗̉w�Ȃ̉̎�����������ł���B���a52�N�������Ŕ��s�Ƃ���B �@�ȂƂ̉��̉�b���炾�������낤���A�R�N���R�Ƃ������t��������o���B�����ɁA�w������ɗF�l���K�˂����ɁA�������̕ꓰ���o���ĉ��������P�[�L�̔��ɏ�����Ă����R�N���R�Ƃ����X���Ɓu�N���R�N���R�A�����R�N���R�v�Ƃ����t���[�Y���A���̒��ɑh�����B�u�R�N���R�v�Ƃ́u�ЂȂ����i���H�q�A��㠈��j�v�̂��Ƃł���B
�@�ȂƂ̉��̉�b���炾�������낤���A�R�N���R�Ƃ������t��������o���B�����ɁA�w������ɗF�l���K�˂����ɁA�������̕ꓰ���o���ĉ��������P�[�L�̔��ɏ�����Ă����R�N���R�Ƃ����X���Ɓu�N���R�N���R�A�����R�N���R�v�Ƃ����t���[�Y���A���̒��ɑh�����B�u�R�N���R�v�Ƃ́u�ЂȂ����i���H�q�A��㠈��j�v�̂��Ƃł���B �@���N�O����C���t���Ă����̂����A�A���o���ɓ\��ꂽ�ʐ^�Ȃǂ̉ƒ�ʐ^������̖{�ɂ��邱�Ƃ����߂�L�����p�\�R����ʂɂ悭�����B���̌��ۂ̓f�W�^���J������X�}�[�g�t�H���̕��y�Ə��X�̃f�W�^�����̐i���ɑ傢�ɊW�����肻�����B
�@���N�O����C���t���Ă����̂����A�A���o���ɓ\��ꂽ�ʐ^�Ȃǂ̉ƒ�ʐ^������̖{�ɂ��邱�Ƃ����߂�L�����p�\�R����ʂɂ悭�����B���̌��ۂ̓f�W�^���J������X�}�[�g�t�H���̕��y�Ə��X�̃f�W�^�����̐i���ɑ傢�ɊW�����肻�����B �@�ŋ߂ł͐V����G���͂قƂ�Ǔǂ܂Ȃ����A����ł��l�ɋ�����ꂽ��A�ڂɕt�����肵�����͂͐���A���s���ŃN���A�t�@�C���ɋ��ݍ���ł���B���N�̐����낤�Ƌ������Ȃ��B
�@�ŋ߂ł͐V����G���͂قƂ�Ǔǂ܂Ȃ����A����ł��l�ɋ�����ꂽ��A�ڂɕt�����肵�����͂͐���A���s���ŃN���A�t�@�C���ɋ��ݍ���ł���B���N�̐����낤�Ƌ������Ȃ��B �@�}���ق���Z�o�X�e�B�A���E�u�����g�́u����D�v�㉺�i���萷�i��A����v���V�Ёj����o�����B���̍��܂őS���m��Ȃ��������҂̂��̖{����o�����̂ɂ͎��̂悤�Ȍo�܂�����B
�@�}���ق���Z�o�X�e�B�A���E�u�����g�́u����D�v�㉺�i���萷�i��A����v���V�Ёj����o�����B���̍��܂őS���m��Ȃ��������҂̂��̖{����o�����̂ɂ͎��̂悤�Ȍo�܂�����B �g���{�̃V���h���[�h�Ə̂���Ă��鐙���琤���g�A�j�A�̎��㗝�̗L���ȁu���̃r�U�v�Ɋւ���b�͒m���Ă���B���̃r�U�̔��s�Ɋւ��Ď��������Ă����̋^��̉����Ɛ����琤���g�₻�̍s���ɂ��Ă������������̐�����Ɗ֘A�t���ĕ����悤�Ƃ̎v���ŁA����ł������L�̂S����ǂB
�g���{�̃V���h���[�h�Ə̂���Ă��鐙���琤���g�A�j�A�̎��㗝�̗L���ȁu���̃r�U�v�Ɋւ���b�͒m���Ă���B���̃r�U�̔��s�Ɋւ��Ď��������Ă����̋^��̉����Ɛ����琤���g�₻�̍s���ɂ��Ă������������̐�����Ɗ֘A�t���ĕ����悤�Ƃ̎v���ŁA����ł������L�̂S����ǂB �@�J�� ���̒���͐V���ДŁu�J�� ���S�W�v�S22���Ɏ��߂��Ă���B�����Ɏ��߂��Ă��Ȃ��G�b�Z�C�������A���ɏo�����̂��J��i��E�R�씎�j���҂́u�J�� ���@����̊l���́A��H�̌���v�iKK�����O�Z���[�Y�j�ł���B
�@�J�� ���̒���͐V���ДŁu�J�� ���S�W�v�S22���Ɏ��߂��Ă���B�����Ɏ��߂��Ă��Ȃ��G�b�Z�C�������A���ɏo�����̂��J��i��E�R�씎�j���҂́u�J�� ���@����̊l���́A��H�̌���v�iKK�����O�Z���[�Y�j�ł���B �Ζk�̖쒹�Z���^�[�ɃI�I�q�V�N�C�����ɍs���āA���łɋߍ]�ǖH佂Ɋ���āA���X���c�̍g�t�߂Ȃ���A���Ă��܂����B�Ƃ̎G�p���I���APC���J���āA�����̂悤��
�Ζk�̖쒹�Z���^�[�ɃI�I�q�V�N�C�����ɍs���āA���łɋߍ]�ǖH佂Ɋ���āA���X���c�̍g�t�߂Ȃ���A���Ă��܂����B�Ƃ̎G�p���I���APC���J���āA�����̂悤�� �u�{�͎����Ŕ������̂��v�Ƃ����ӎ��������������́A�}���ق̖�����Ӌ`�ɂ��čl���邱�Ƃ͖w�ǂȂ������B
�u�{�͎����Ŕ������̂��v�Ƃ����ӎ��������������́A�}���ق̖�����Ӌ`�ɂ��čl���邱�Ƃ͖w�ǂȂ������B �u�{�I��������̐l��������v�ƌ������̂͒N���������낤���B���̕����́u���Ȃ��̖{�I������A���Ȃ����ǂ̂悤�Ȑl�����Ă邱�Ƃ��ł���v�����������m��Ȃ��B
�u�{�I��������̐l��������v�ƌ������̂͒N���������낤���B���̕����́u���Ȃ��̖{�I������A���Ȃ����ǂ̂悤�Ȑl�����Ă邱�Ƃ��ł���v�����������m��Ȃ��B �@����|�}����́u��h���킹�݁v�i���t���Ɂj34����ǂݏI�����Ȃɂ���͂ǂ����ƒr�g�����Y����́u���q�����v�i�V���Ёj�S16������n�����B
�@����|�}����́u��h���킹�݁v�i���t���Ɂj34����ǂݏI�����Ȃɂ���͂ǂ����ƒr�g�����Y����́u���q�����v�i�V���Ёj�S16������n�����B �@�d���̊W�ő��m��A���̌���d���𗣂�Đe�������Ă��铌���݂̎Ⴂ�F�l���烁�[�����������B�d���ő��ɗ���Ƃ����B�u�����艓����藈����܂��y�����炸��v�Ƃ������ƂŒ��H�����ɂ��A���낢��Ƙb�����B
�@�d���̊W�ő��m��A���̌���d���𗣂�Đe�������Ă��铌���݂̎Ⴂ�F�l���烁�[�����������B�d���ő��ɗ���Ƃ����B�u�����艓����藈����܂��y�����炸��v�Ƃ������ƂŒ��H�����ɂ��A���낢��Ƙb�����B �@�Ȉ��ɑ����Ă������鍑���w��̉��ɕ��䌧���}���قŒ��N�i���Ƃ��ē����Ă����l�����A���炪�͂����Ă���Ɩ��Ƃ��Ẵ��t�@�����X�E�T�[�r�X�ɂ��Ă̒Z�����Ă����B
�@�Ȉ��ɑ����Ă������鍑���w��̉��ɕ��䌧���}���قŒ��N�i���Ƃ��ē����Ă����l�����A���炪�͂����Ă���Ɩ��Ƃ��Ẵ��t�@�����X�E�T�[�r�X�ɂ��Ă̒Z�����Ă����B �@���Ă��̗��ɁA���N�u�q�ǂ��̖{�v�̐��E�Ɋւ���Ă��������u�������w�Ƃ����ʒu�Â��͑���Ǝv���Ă���v�Ƃ��A�u�q�ǂ�������ɐ����������Ă����l���A�q�ǂ��̎��̕�������t�ɕϊ����Ă���邱�ƂŁA�q�ǂ������͕����ǂނ��ƂŁA����̒��Ő����A�`�������A�q�ǂ�����B�����āA�����i��l�ɂȂ��Ă�����j��M���Ĉ������Ɛ����̊K�i������Ă����B�l���ɕK�v�Ȍ��t���l�����A�����킹�Ȍ��������߂āA����̐��E�ɔ�э���ōs����[���������������w��I��ŁA�q�ǂ������̑O�ɍ����o�������Ǝv���̂ł��v�Ə����ꂽ�B
�@���Ă��̗��ɁA���N�u�q�ǂ��̖{�v�̐��E�Ɋւ���Ă��������u�������w�Ƃ����ʒu�Â��͑���Ǝv���Ă���v�Ƃ��A�u�q�ǂ�������ɐ����������Ă����l���A�q�ǂ��̎��̕�������t�ɕϊ����Ă���邱�ƂŁA�q�ǂ������͕����ǂނ��ƂŁA����̒��Ő����A�`�������A�q�ǂ�����B�����āA�����i��l�ɂȂ��Ă�����j��M���Ĉ������Ɛ����̊K�i������Ă����B�l���ɕK�v�Ȍ��t���l�����A�����킹�Ȍ��������߂āA����̐��E�ɔ�э���ōs����[���������������w��I��ŁA�q�ǂ������̑O�ɍ����o�������Ǝv���̂ł��v�Ə����ꂽ�B �@�ŋ߂̖ڂ̐������������낤�Ə���Ɏ���ɓs���̂������R��t���Ă��邪�A���Ђ�V���̕��͂ɂ��ēǂ�ł���̂ł͂Ȃ��A�P�ɒ��߂Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ə����C�ɂȂ��Ă���B
�@�ŋ߂̖ڂ̐������������낤�Ə���Ɏ���ɓs���̂������R��t���Ă��邪�A���Ђ�V���̕��͂ɂ��ēǂ�ł���̂ł͂Ȃ��A�P�ɒ��߂Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ə����C�ɂȂ��Ă���B �@�ߑ�o��ɂ��Ă�����ƒm�肽�����Ƃ�����A�茳�́u���{�̎��́v30���̔o��W����Ɏ�����B�m�肽�����Ƃ͒����ɉ����������A���̊��̏������m��̕łɕtⳂ������Ă����̂��C�ɂȂ����B��������11���傪����ł����B�������m��Ƃ������O�͒m���Ă��������̋�ɂ��ĉ������ׂ��Ƃ����L���͂Ȃ��B
�@�ߑ�o��ɂ��Ă�����ƒm�肽�����Ƃ�����A�茳�́u���{�̎��́v30���̔o��W����Ɏ�����B�m�肽�����Ƃ͒����ɉ����������A���̊��̏������m��̕łɕtⳂ������Ă����̂��C�ɂȂ����B��������11���傪����ł����B�������m��Ƃ������O�͒m���Ă��������̋�ɂ��ĉ������ׂ��Ƃ����L���͂Ȃ��B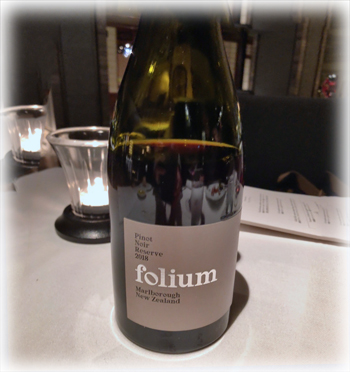 �@�C���̂����̂ł���B���\�N���O�ɐV���̉̒d�Ō����B���Ȃɐ�����Ă������A�I�҂̖������̕]���S���o���Ă��Ȃ��B���̂Ƃ��A�x����O�̓����ŏt�����y���ނ̂��������A���Ȃ甖��̔����̓������Ȃ��A�Ǝv�����L��������B���̂Ƃ������͗x�炸�Â��ɒ[�����A�h���̎��������Ɖ��߂Ă��邾�낤�Ƃ��B
�@�C���̂����̂ł���B���\�N���O�ɐV���̉̒d�Ō����B���Ȃɐ�����Ă������A�I�҂̖������̕]���S���o���Ă��Ȃ��B���̂Ƃ��A�x����O�̓����ŏt�����y���ނ̂��������A���Ȃ甖��̔����̓������Ȃ��A�Ǝv�����L��������B���̂Ƃ������͗x�炸�Â��ɒ[�����A�h���̎��������Ɖ��߂Ă��邾�낤�Ƃ��B �@�茳�ɂ͐}���ق����o�����u���E ����̗��v�i�����V���Ёj�T��������B���v��124�̖��悪���߂��A���̖���Ɋւ���A���邢�͂��̖���Ɉ��i���ȁj�ޗl�X�ȕ��ꂪ�I�s���Ǝʐ^�ŏЉ��Ă���B1984�N�H����1987�N�t�܂łQ�N���ɘj���Ē����V�����j�łɘA�ڂ��ꂽ���̂����Љ��������̂ł���B
�@�茳�ɂ͐}���ق����o�����u���E ����̗��v�i�����V���Ёj�T��������B���v��124�̖��悪���߂��A���̖���Ɋւ���A���邢�͂��̖���Ɉ��i���ȁj�ޗl�X�ȕ��ꂪ�I�s���Ǝʐ^�ŏЉ��Ă���B1984�N�H����1987�N�t�܂łQ�N���ɘj���Ē����V�����j�łɘA�ڂ��ꂽ���̂����Љ��������̂ł���B �g�����ׂ��Ǐ��ʂƖڗ����Œm����h���� �q����́u�{�̂Ȃ��̖{�v�i�����V���Ёj�Ɓu�{�̑D�v�i�����V���Ёj���A���ɂ�����o�����B�O�҂ł͌��䂳�D��������ۂ����{150���A��҂ł͎���̍D�݂őI�{138���ɂ���1000����̕������ňӂ�s�������]������Ă���B
�g�����ׂ��Ǐ��ʂƖڗ����Œm����h���� �q����́u�{�̂Ȃ��̖{�v�i�����V���Ёj�Ɓu�{�̑D�v�i�����V���Ёj���A���ɂ�����o�����B�O�҂ł͌��䂳�D��������ۂ����{150���A��҂ł͎���̍D�݂őI�{138���ɂ���1000����̕������ňӂ�s�������]������Ă���B �u�X�����䂭�v�́A�i�n�ɑ��Y����̑S43�����琬��I�s���W�ł���B25�N�Ԃ́u�T�������v�̘A�ڂ�Z�߂����̂ł���A�����͖k�C�����牫��܂ŁA�����ĊC�O�ł̓A�C�������h�A�I�����_�A�����S���A��p�Ȃǂ̓�������B
�u�X�����䂭�v�́A�i�n�ɑ��Y����̑S43�����琬��I�s���W�ł���B25�N�Ԃ́u�T�������v�̘A�ڂ�Z�߂����̂ł���A�����͖k�C�����牫��܂ŁA�����ĊC�O�ł̓A�C�������h�A�I�����_�A�����S���A��p�Ȃǂ̓�������B �@2022�N4��10���t�ǔ��V�������̏��]���Ɍf�ڂ���Ă������鏑�]���ڂɎ~�܂����B�e���r��ʂł�������݂̌��V���L�ҁA���ǔ��V�����ʕҏW�ψ��ő�ςȓǏ��Ƃł����鋴�{�ܘY����ɂ��u�G���[�g�Ƌ��{�@�|�X�g�R���i�̓��{�l�v�i����z��Y�A�����V�����N���j�̏��]�ł���B
�@2022�N4��10���t�ǔ��V�������̏��]���Ɍf�ڂ���Ă������鏑�]���ڂɎ~�܂����B�e���r��ʂł�������݂̌��V���L�ҁA���ǔ��V�����ʕҏW�ψ��ő�ςȓǏ��Ƃł����鋴�{�ܘY����ɂ��u�G���[�g�Ƌ��{�@�|�X�g�R���i�̓��{�l�v�i����z��Y�A�����V�����N���j�̏��]�ł���B �@����O�V����̐��M�W��ǂ�ł�����A�J��i�ꂳ��́u�������ՐS���v�i�V���I���j�̏Љ���f�ڂ���Ă���̂ɋC���t�����B���̓��̒��ł͂��̂���l�̐ړ_�͑S�����݂��Ȃ������̂ŁA�ǂ̂悤�ȗ��R�A�o�܂ň��삳�������ɂȂ����̂��͒m��Ȃ����������ł��Ȃ��B
�@����O�V����̐��M�W��ǂ�ł�����A�J��i�ꂳ��́u�������ՐS���v�i�V���I���j�̏Љ���f�ڂ���Ă���̂ɋC���t�����B���̓��̒��ł͂��̂���l�̐ړ_�͑S�����݂��Ȃ������̂ŁA�ǂ̂悤�ȗ��R�A�o�܂ň��삳�������ɂȂ����̂��͒m��Ȃ����������ł��Ȃ��B �@�䂪���̍�����ۂ̏ے��̂悤�ɖ����̐V���ɂ͒����ȘV��҂����҂ƂȂ��Ă��鏑�Ђ̍L��������ł���B
�@�䂪���̍�����ۂ̏ے��̂悤�ɖ����̐V���ɂ͒����ȘV��҂����҂ƂȂ��Ă��鏑�Ђ̍L��������ł���B �@�����M�͎�͂̑��Ƃł��鈢��O�V����̏�����ǂL���́A�p�������Ȃ��疳���A���ɂ͖@���Ƃ̈��쏮�V����A�G�b�Z�C�X�g�̈��썲�a�q����̕��N�Ƃ��Ă̕����e�����B
�@�����M�͎�͂̑��Ƃł��鈢��O�V����̏�����ǂL���́A�p�������Ȃ��疳���A���ɂ͖@���Ƃ̈��쏮�V����A�G�b�Z�C�X�g�̈��썲�a�q����̕��N�Ƃ��Ă̕����e�����B �@���̗��Łu���̉��q���܁v�i���ҁG�T���E�e�O�W���y���A��ҁF���� ��A��g���X�j�����グ��̂͂ƂĂ�����B���̖{�ɐ[���v����v����Ă�����A���x���ǂݕԂ��ꂽ���A�����ȈӖ��ň��Ǐ��Ƃ���Ă�����������钆�A�����ȕ��͂͋ɂ߂Ċ댯�ł���B����ȕ��͂͏����Ȃ��B�����ł�����Ǝ߂̕������珑�����ƂƂ����B
�@���̗��Łu���̉��q���܁v�i���ҁG�T���E�e�O�W���y���A��ҁF���� ��A��g���X�j�����グ��̂͂ƂĂ�����B���̖{�ɐ[���v����v����Ă�����A���x���ǂݕԂ��ꂽ���A�����ȈӖ��ň��Ǐ��Ƃ���Ă�����������钆�A�����ȕ��͂͋ɂ߂Ċ댯�ł���B����ȕ��͂͏����Ȃ��B�����ł�����Ǝ߂̕������珑�����ƂƂ����B �@�S�g�ɔ�����Z���A�_���ƌ������₠�邢�͐Βi�ɍ���a���Ă���B���̖T��̐��Ղɂ͘@�̉Ԃ�������ł���B���̏����̂�����܂߂đS�̂̊����͓�����҂̊ω����ɋ߂��B�Ƃ��������ω������̂��̂ł���B��҂��u���g�̐l�Ԃ��畧�̐��E�ւƈڍs���čs���ړ_�ɂ����i�v�ƌ����Ă���B
�@�S�g�ɔ�����Z���A�_���ƌ������₠�邢�͐Βi�ɍ���a���Ă���B���̖T��̐��Ղɂ͘@�̉Ԃ�������ł���B���̏����̂�����܂߂đS�̂̊����͓�����҂̊ω����ɋ߂��B�Ƃ��������ω������̂��̂ł���B��҂��u���g�̐l�Ԃ��畧�̐��E�ւƈڍs���čs���ړ_�ɂ����i�v�ƌ����Ă���B �@�ߕ����ɂ��āu�����ȗ��̋ߑ㉻�̂Ȃ��Ő��܂ꂽ���{�Ǝ��̕��w�W�������v�Ə�����Ă���̂�ǂL��������B���̂悤�Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ����������{�Y���́u�����ߕ����v��쑺�ӓ��́u�K�`�����ߕ��T�v�Ȃǂ̊���͒������̍��ɓǂ悤���B
�@�ߕ����ɂ��āu�����ȗ��̋ߑ㉻�̂Ȃ��Ő��܂ꂽ���{�Ǝ��̕��w�W�������v�Ə�����Ă���̂�ǂL��������B���̂悤�Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ����������{�Y���́u�����ߕ����v��쑺�ӓ��́u�K�`�����ߕ��T�v�Ȃǂ̊���͒������̍��ɓǂ悤���B �@�Ƃ��ǂ��}�X���f�B�A�́u�@���̕��͂����ɂ킩��ɂ����v�u��������v�Ɣ���B��Ɩ@���̗���Œ��N�@���ɕt�������Ă����g�ɂ͏ꍇ�ɂ���ẮA���@�S���҂ɑ����āu�����Ȃ������v���ƌ��������Ȃ邱�Ƃ�����B
�@�Ƃ��ǂ��}�X���f�B�A�́u�@���̕��͂����ɂ킩��ɂ����v�u��������v�Ɣ���B��Ɩ@���̗���Œ��N�@���ɕt�������Ă����g�ɂ͏ꍇ�ɂ���ẮA���@�S���҂ɑ����āu�����Ȃ������v���ƌ��������Ȃ邱�Ƃ�����B �@�F��ቤ�q�_�БO�̗��ʎቤ�q������A��t�����̍��o��ʋ�t�����܂ł̓��R�R�[�̔��i�Α`���ɉ�����1.5km�̎U�����́A�N�w�ҁE���c�����Y��c�ӌ��炪�D��ŎU�A�v�Ă����炵���Ƃ����B
�@�F��ቤ�q�_�БO�̗��ʎቤ�q������A��t�����̍��o��ʋ�t�����܂ł̓��R�R�[�̔��i�Α`���ɉ�����1.5km�̎U�����́A�N�w�ҁE���c�����Y��c�ӌ��炪�D��ŎU�A�v�Ă����炵���Ƃ����B �@���̂S���ɃA���u���A�M�̎�s�A�u�_�r�̓��{�l�w�Z�ɕ��C�����F�l����u�A�u�_�r�ʐM�v�������Ă���B
�@���̂S���ɃA���u���A�M�̎�s�A�u�_�r�̓��{�l�w�Z�ɕ��C�����F�l����u�A�u�_�r�ʐM�v�������Ă���B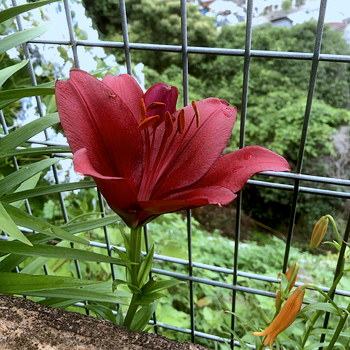 �@�����s��w�����E�ԙ����|�w�҂̌̒˖{�m���Y����Ɂu���̉Ԕ��p�فv�i�����I���j�Ƃ������|�Ƃ��ẲԂƂ�����ނɂ����G��ɂ��Ă̈��������B�������ł͔��`���Ԃ́u���q�Ԑ}�v�A�������ɂ��Ă̓��l�́u���A�v�A�Ђ܂��̓S�b�z�́u�Ђ܂��v�Ƃ�������ɊG��Ɖ��|�w�̊ϓ_���珔�X���y����������Ă���B
�@�����s��w�����E�ԙ����|�w�҂̌̒˖{�m���Y����Ɂu���̉Ԕ��p�فv�i�����I���j�Ƃ������|�Ƃ��ẲԂƂ�����ނɂ����G��ɂ��Ă̈��������B�������ł͔��`���Ԃ́u���q�Ԑ}�v�A�������ɂ��Ă̓��l�́u���A�v�A�Ђ܂��̓S�b�z�́u�Ђ܂��v�Ƃ�������ɊG��Ɖ��|�w�̊ϓ_���珔�X���y����������Ă���B �@���j���̒���E�e���ԑg�Łu�j�[�v�ɂ��Ă̕��f���������B�r�����猩�����Ƃ�����A�S�̂��ǂ̂悤�ȍ\�����������͕�����Ȃ����A�j�[����Ŋ뜜��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ┪�d��̋j�[�A�i��̉Ԃ��炭�j�[���Љ��Ă����B�����ċj�[�̈�ĕ����B
�@���j���̒���E�e���ԑg�Łu�j�[�v�ɂ��Ă̕��f���������B�r�����猩�����Ƃ�����A�S�̂��ǂ̂悤�ȍ\�����������͕�����Ȃ����A�j�[����Ŋ뜜��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ┪�d��̋j�[�A�i��̉Ԃ��炭�j�[���Љ��Ă����B�����ċj�[�̈�ĕ����B �u��Îs�@���̐}���فE���z�̐}���فv�̘b�肪�^�c��c�Řb����Ă���B���́A�_�̏�̘b�łȂ��A�����Ȗ�����肽���Ǝv���B
�u��Îs�@���̐}���فE���z�̐}���فv�̘b�肪�^�c��c�Řb����Ă���B���́A�_�̏�̘b�łȂ��A�����Ȗ�����肽���Ǝv���B �@���̈����o���̉����珺�a53�N7��28���t�̓��{�o�ϐV���L���̐蔲�������������B�u�N�����߂̗��̒Q���v�Ƒ肳�ꂽ�A�����a���،��햱���������{�a�j���ɂ�邱��203�s�̋L���́A�Ώ�I�q�́u�����v�Ƃ����⏥�Ŏn�܂�A�ޏ��ɓZ��鏔�X�ɂ��Ă̒O�O�Ȓ����̌��ʂ��L�q����Ă���B
�@���̈����o���̉����珺�a53�N7��28���t�̓��{�o�ϐV���L���̐蔲�������������B�u�N�����߂̗��̒Q���v�Ƒ肳�ꂽ�A�����a���،��햱���������{�a�j���ɂ�邱��203�s�̋L���́A�Ώ�I�q�́u�����v�Ƃ����⏥�Ŏn�܂�A�ޏ��ɓZ��鏔�X�ɂ��Ă̒O�O�Ȓ����̌��ʂ��L�q����Ă���B �@�������Ƃ������w�E���Z�j�q��эZ��OB�������Ă����B���Ƃ������_�ŏI�g�����x�����Ă����̂Ō��݂ł����V�ɑ����Ă���Ă���̂��낤�B
�@�������Ƃ������w�E���Z�j�q��эZ��OB�������Ă����B���Ƃ������_�ŏI�g�����x�����Ă����̂Ō��݂ł����V�ɑ����Ă���Ă���̂��낤�B �@�Q�O�N���炢�O�̂��Ƃ������ł��傤���H���ɒ��Ԃ̎Ⴂ�F�l���A���s�O���͌����ɂ�����������X�ɘA��čs���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B
�@�Q�O�N���炢�O�̂��Ƃ������ł��傤���H���ɒ��Ԃ̎Ⴂ�F�l���A���s�O���͌����ɂ�����������X�ɘA��čs���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B �@���c��������ɂ��ď����B���ă}���\���Ⓑ�������ňꐢ���r�������c����A���݂̓X�|�[�c�E�W���[�i���X�g�̌����������}���\������ł����Ă��鑝�c����ɂ��ď����̂ł͂Ȃ��B�ǔ��V���̐l���ē��̗��̉҂Ƃ��āA���A�X���[�g�Ƃ͈�����ʂ���X�Ɍ����Ă��鑝�c����ɂ��Ă̏����ł���B
�@���c��������ɂ��ď����B���ă}���\���Ⓑ�������ňꐢ���r�������c����A���݂̓X�|�[�c�E�W���[�i���X�g�̌����������}���\������ł����Ă��鑝�c����ɂ��ď����̂ł͂Ȃ��B�ǔ��V���̐l���ē��̗��̉҂Ƃ��āA���A�X���[�g�Ƃ͈�����ʂ���X�Ɍ����Ă��鑝�c����ɂ��Ă̏����ł���B �@�l�̑㖼���i�ɂ傤�����߂����j����ʓI�ȗp�ꂾ�Ǝv���Ă������A�茳�̍L�����������Ɓu�l�㖼���ɓ����v�Ƃ���ł͂Ȃ����B�����������B�l�㖼���́u�����߂����v�Ɠǂ݁A�u�㖼���̂����A�����E�ꏊ�E�������w������w���㖼���ɑ��A�b����Ƃ̊W�T�O��\�����A�l���w��������́B�u���v�u�킽�����v�i���l�́j�A�u�Ȃv�u���Ȃ��v�i���l�́j�A�u����v�u���̂����v�i��O�l�́j�A�u����v�u�ǂȂ��v�i�s��́j�Ȃǂ̗ށv�Ɛ������Ă���B
�@�l�̑㖼���i�ɂ傤�����߂����j����ʓI�ȗp�ꂾ�Ǝv���Ă������A�茳�̍L�����������Ɓu�l�㖼���ɓ����v�Ƃ���ł͂Ȃ����B�����������B�l�㖼���́u�����߂����v�Ɠǂ݁A�u�㖼���̂����A�����E�ꏊ�E�������w������w���㖼���ɑ��A�b����Ƃ̊W�T�O��\�����A�l���w��������́B�u���v�u�킽�����v�i���l�́j�A�u�Ȃv�u���Ȃ��v�i���l�́j�A�u����v�u���̂����v�i��O�l�́j�A�u����v�u�ǂȂ��v�i�s��́j�Ȃǂ̗ށv�Ɛ������Ă���B �@�ȑO�AKEI���u�{��I�ԁv�Ƃ����^�C�g���ł��̃y�[�W�ɏ����Ă�������Ⴂ�܂����B
�@�ȑO�AKEI���u�{��I�ԁv�Ƃ����^�C�g���ł��̃y�[�W�ɏ����Ă�������Ⴂ�܂����B �@�h���X�f���̍����ÓT�G��قŌ����u���ӂŎ莆��ǂޏ��v�́A���̍ł��D���ȃt�F�����[����i�ł���B���͂��̊G�̃|�X�g�J�[�h���ʐ^���ɓ���ď��ւ̈֎q�̌��ɂ���{�I�ɏ����Ă���B
�@�h���X�f���̍����ÓT�G��قŌ����u���ӂŎ莆��ǂޏ��v�́A���̍ł��D���ȃt�F�����[����i�ł���B���͂��̊G�̃|�X�g�J�[�h���ʐ^���ɓ���ď��ւ̈֎q�̌��ɂ���{�I�ɏ����Ă���B �@���Ȃ�̘̂b�ł���B�e���r�́u�J�^�I�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�����Ă�����A�Q�X�g�Ƃ��ď����ꂽ�����̓c���ЕF��i�����ď����̎w�������Ă����̓c���p�h���̐F�����Ӓ�Ώەi�Ƃ��Ď��Q���Ă����B�����Ȃ���Ă������A���̐F���ɂ͉��\���~���̊Ӓ茋�ʂ��o���ꂽ�B
�@���Ȃ�̘̂b�ł���B�e���r�́u�J�^�I�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�����Ă�����A�Q�X�g�Ƃ��ď����ꂽ�����̓c���ЕF��i�����ď����̎w�������Ă����̓c���p�h���̐F�����Ӓ�Ώەi�Ƃ��Ď��Q���Ă����B�����Ȃ���Ă������A���̐F���ɂ͉��\���~���̊Ӓ茋�ʂ��o���ꂽ�B �@�ؗF���u���O�ŃW���[�t�E�~�b�`�F���́u�}�N�\�[���[�̑f�G�Ȏ���v�i�����[�j���u�j���[���[�N�ɐ�����A���ŁA���������ŁA�����Ăǂ���������̂���A�͂����肢���Ă��ꂼ��^�C�v�̈Ⴄ��l�̂悤�Ȑl�����ɁA���������܂�Ă��܂������ȕ`�����v��1,000�����̕��͂ŏЉ�Ă����B���̕��͂Ɏ䂩��āA���̑f�G�Ȏ����}���ق����o���A�����Ɋ܂܂�Ă���10�̒Z�҂��y���B
�@�ؗF���u���O�ŃW���[�t�E�~�b�`�F���́u�}�N�\�[���[�̑f�G�Ȏ���v�i�����[�j���u�j���[���[�N�ɐ�����A���ŁA���������ŁA�����Ăǂ���������̂���A�͂����肢���Ă��ꂼ��^�C�v�̈Ⴄ��l�̂悤�Ȑl�����ɁA���������܂�Ă��܂������ȕ`�����v��1,000�����̕��͂ŏЉ�Ă����B���̕��͂Ɏ䂩��āA���̑f�G�Ȏ����}���ق����o���A�����Ɋ܂܂�Ă���10�̒Z�҂��y���B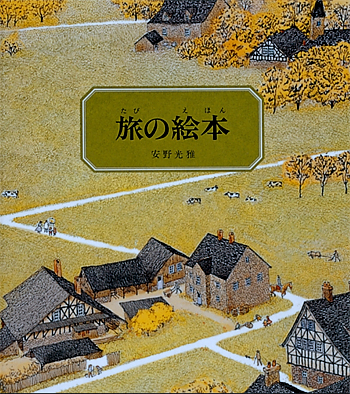 �@�����ɂ��A�G���ɂ��B�����̎U���͂�߁I�Ƃ������Ƃ������Ă������ł����A�Q�C�R�O�N�O�́A�܂��A�������������������B
�@�����ɂ��A�G���ɂ��B�����̎U���͂�߁I�Ƃ������Ƃ������Ă������ł����A�Q�C�R�O�N�O�́A�܂��A�������������������B �@�}���ق���u�\�������܂��v�Ƃ������[�����͂����B���e������ƁA�Q�悤������́u�����Ƃ��ǂ��Г�v�i�W�p�Ёj�Ƃ���B���̎��_�ł͎��͂��̖{��\�����Ƃ�\�����R����������Y��Ă����B
�@�}���ق���u�\�������܂��v�Ƃ������[�����͂����B���e������ƁA�Q�悤������́u�����Ƃ��ǂ��Г�v�i�W�p�Ёj�Ƃ���B���̎��_�ł͎��͂��̖{��\�����Ƃ�\�����R����������Y��Ă����B �@�S�n�悢�u�₩�Ȃ��V�C�̈���B�F�B��U���āA�O��̘a�v�B�̐X�A���������p�قɍs���Ă��܂����B
�@�S�n�悢�u�₩�Ȃ��V�C�̈���B�F�B��U���āA�O��̘a�v�B�̐X�A���������p�قɍs���Ă��܂����B �@�ŋ߃o���g�R���ɂ��Đ�����IT�Z�p�̊֘A�ł��낢��ƕ���A�}�X���f�B�A��ʂ��Ă��̖������Ƃ������Ȃ����B���̓��̒��ɂ���o���g�R���̃C���[�W�́A�o���g�C�����ɂ���R�̏����A1990�N���邢��1991�N�Ƀ\�A����Ɨ��������X�ƌ������̂������B�k�����փG�X�g�j�A�A���g�r�A�A���g�A�j�A�ƕ���ł���̂����A���̈ʒu�W���͂�����Ɨ������Ă����킯�ł͂Ȃ������B
�@�ŋ߃o���g�R���ɂ��Đ�����IT�Z�p�̊֘A�ł��낢��ƕ���A�}�X���f�B�A��ʂ��Ă��̖������Ƃ������Ȃ����B���̓��̒��ɂ���o���g�R���̃C���[�W�́A�o���g�C�����ɂ���R�̏����A1990�N���邢��1991�N�Ƀ\�A����Ɨ��������X�ƌ������̂������B�k�����փG�X�g�j�A�A���g�r�A�A���g�A�j�A�ƕ���ł���̂����A���̈ʒu�W���͂�����Ɨ������Ă����킯�ł͂Ȃ������B �@�����炭���ɂȂ�Ƃ����������Ă��āA���������o���������Ȃ�B
�@�����炭���ɂȂ�Ƃ����������Ă��āA���������o���������Ȃ�B �@�F�l���S���Ȃ�͎̂₵���B���N�����s�̓��l�ʐ^�W�̃����o�[�������F���S���Ȃ����B�ʐ^�W�ɂ͔ނ̉ߋ��̌���ɕ����ē����̒��Ԃɂ��Ǔ������ڂ���ꂽ�B
�@�F�l���S���Ȃ�͎̂₵���B���N�����s�̓��l�ʐ^�W�̃����o�[�������F���S���Ȃ����B�ʐ^�W�ɂ͔ނ̉ߋ��̌���ɕ����ē����̒��Ԃɂ��Ǔ������ڂ���ꂽ�B �@����}���قɗ\�Ă����{�����ɍs���āA���łɋC�ɂȂ��Ă����{��T���ɓ��{���w�̒I��T���B
�@����}���قɗ\�Ă����{�����ɍs���āA���łɋC�ɂȂ��Ă����{��T���ɓ��{���w�̒I��T���B �@2021�N11��24���t�̓ǔ��V���[���́u���X���I�ԓ��ʂȈ���v�Ƃ������o���Łu�ڗ����̏��X���Ɏ����ɂ҂�����̖{��T���Ă��炤�w�I���x�T�[�r�X���l�C���W�߂Ă���v���Ƃɂ��ĎЉ�ʋL���ł̓̈�ȏ�̎��ʂ��g���ĕ��Ă����B
�@2021�N11��24���t�̓ǔ��V���[���́u���X���I�ԓ��ʂȈ���v�Ƃ������o���Łu�ڗ����̏��X���Ɏ����ɂ҂�����̖{��T���Ă��炤�w�I���x�T�[�r�X���l�C���W�߂Ă���v���Ƃɂ��ĎЉ�ʋL���ł̓̈�ȏ�̎��ʂ��g���ĕ��Ă����B �@�����炫�n�߂邩�ȁH�ł��A�܂������Ȃ����B
�@�����炫�n�߂邩�ȁH�ł��A�܂������Ȃ����B �@�u�l�ׂ̈Ə����ċU��Ɠǂނ̂͂Ȃ�������@�l�̖��Ə����ęR�Ȃ��Ɠǂނ̂͂Ȃ�������@���Ƃ������ɂ͐S�������Ɛ^�ɂ���Ƃ����̂Ɂ@���Ƃ������ɂ͐S�����ɂ���͉̂��S�̂����H�v
�@�u�l�ׂ̈Ə����ċU��Ɠǂނ̂͂Ȃ�������@�l�̖��Ə����ęR�Ȃ��Ɠǂނ̂͂Ȃ�������@���Ƃ������ɂ͐S�������Ɛ^�ɂ���Ƃ����̂Ɂ@���Ƃ������ɂ͐S�����ɂ���͉̂��S�̂����H�v �@�ꂩ���Ɉ��A�F�B�̂����e���c���ꂽ���ƂɏW�܂��āA�Ǐ�������Ă���B
�@�ꂩ���Ɉ��A�F�B�̂����e���c���ꂽ���ƂɏW�܂��āA�Ǐ�������Ă���B �@�茳�ɂ͑咆�������āA�܂��q�����g���Ă������̂��܂���11���̉p�a���T�E�p�p���T������B�������̂����邪�A����͉�Зp�Ǝ���p�ɔ��������̂Ń��^�C�A�������_�ʼn�Ђ��玝���A�菑�I�ɕ��ׂ����ʂł���B�����̎����̓��r���O�̏��I�A���ւ̏��I�ɕ����Ēu���Ă���B�g�����ꂽ����͊��̏�ɍ��ꎫ�T�A���a���T�ƕ���Œu����Ă���B
�@�茳�ɂ͑咆�������āA�܂��q�����g���Ă������̂��܂���11���̉p�a���T�E�p�p���T������B�������̂����邪�A����͉�Зp�Ǝ���p�ɔ��������̂Ń��^�C�A�������_�ʼn�Ђ��玝���A�菑�I�ɕ��ׂ����ʂł���B�����̎����̓��r���O�̏��I�A���ւ̏��I�ɕ����Ēu���Ă���B�g�����ꂽ����͊��̏�ɍ��ꎫ�T�A���a���T�ƕ���Œu����Ă���B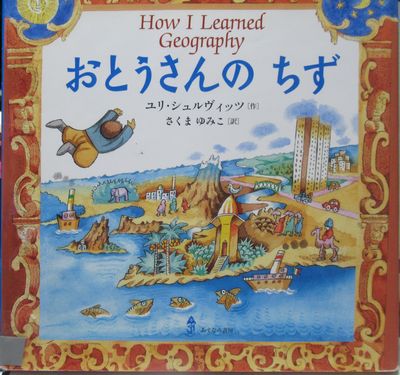 �w�ڂ��̂������́@�Ȃɂ����������Ȃ��ā@���̂����炪��@�ɂ��������B
�w�ڂ��̂������́@�Ȃɂ����������Ȃ��ā@���̂����炪��@�ɂ��������B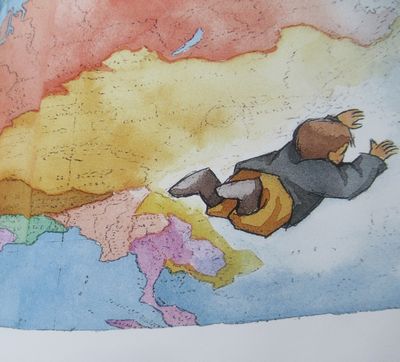 �w���̂ЁA���Ƃ�����́@���ׂɁ@�������͂����B�������@���ׂ����߂�ɂЂ낪��ƁA
�w���̂ЁA���Ƃ�����́@���ׂɁ@�������͂����B�������@���ׂ����߂�ɂЂ낪��ƁA �@���ɂŏ������ׂ��{��I�яo���Ă����Ƃ���A���q�p����́u���t�̏����v�i�o�t�Ёj���ڂɎ~�܂����B�����ɉ��V�����������͊o���Ă��Ȃ����V���̏��]���Œm�蔃�����߂����Ƃ�A�V�����Ԓ��ŋ����[���ǂ��Ƃ��v���o�����B
�@���ɂŏ������ׂ��{��I�яo���Ă����Ƃ���A���q�p����́u���t�̏����v�i�o�t�Ёj���ڂɎ~�܂����B�����ɉ��V�����������͊o���Ă��Ȃ����V���̏��]���Œm�蔃�����߂����Ƃ�A�V�����Ԓ��ŋ����[���ǂ��Ƃ��v���o�����B �@���ɂ₢���ȂƂ���ŁA�ǂݕ������Ɏ��X�o�ꂷ��u�O�т��̂€�̂��炪��ǂ�v�A������ƊG���|���B�ł��A��x�ǂ�ł��炤�Ɓu�������A�������v�Ɖ��x�ł��ǂ�ł��炢������܂��B�����āA�|���g�����̏o�Ă���Ƃ���ł́A�ڂ�傫�����J���āA�����ƒ����Ă��܂��B���������€�̂��炪��ǂA�g������������ĎR�ɂ̂ڂ��Ă����āA�����������ς��H�ׂĂӂƂ�A�u�����Ń`���L���A�p�`���A�X�g���B�͂Ȃ��́@�����܂��B�v�ŁA�ق��Ƃ���������āA�u�������ǂ�Łv�ƂȂ�̂ł��B
�@���ɂ₢���ȂƂ���ŁA�ǂݕ������Ɏ��X�o�ꂷ��u�O�т��̂€�̂��炪��ǂ�v�A������ƊG���|���B�ł��A��x�ǂ�ł��炤�Ɓu�������A�������v�Ɖ��x�ł��ǂ�ł��炢������܂��B�����āA�|���g�����̏o�Ă���Ƃ���ł́A�ڂ�傫�����J���āA�����ƒ����Ă��܂��B���������€�̂��炪��ǂA�g������������ĎR�ɂ̂ڂ��Ă����āA�����������ς��H�ׂĂӂƂ�A�u�����Ń`���L���A�p�`���A�X�g���B�͂Ȃ��́@�����܂��B�v�ŁA�ق��Ƃ���������āA�u�������ǂ�Łv�ƂȂ�̂ł��B �@���݂̎��͎������肾�A�Ƃ������Ƃ͔F�����Ă���B���������͏K�����K���A����Ȃ�̎��������Ă����B���w�Z�T�N���̎����u�s���痢�̓��v�Ƒ发���A�\�����ꂽ�|�����c���Ă���B���ꂪ�N����d�˂�ɏ]���ĉ���ɂȂ�A��Ј��̍��͐�y����u�R�~���j�P�[�V�����ɂ͍����x���Ȃ����v�Ɨ�₩�����܂łɗ����Ԃꂽ�B
�@���݂̎��͎������肾�A�Ƃ������Ƃ͔F�����Ă���B���������͏K�����K���A����Ȃ�̎��������Ă����B���w�Z�T�N���̎����u�s���痢�̓��v�Ƒ发���A�\�����ꂽ�|�����c���Ă���B���ꂪ�N����d�˂�ɏ]���ĉ���ɂȂ�A��Ј��̍��͐�y����u�R�~���j�P�[�V�����ɂ͍����x���Ȃ����v�Ɨ�₩�����܂łɗ����Ԃꂽ�B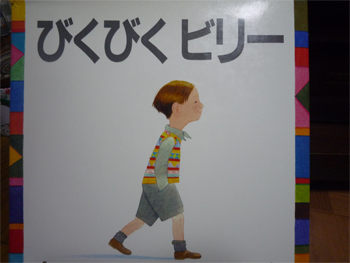 �u�т��т��r���[�v�i�A���\�j�[�E�u���E���� �D������� �]�_�Ёj
�u�т��т��r���[�v�i�A���\�j�[�E�u���E���� �D������� �]�_�Ёj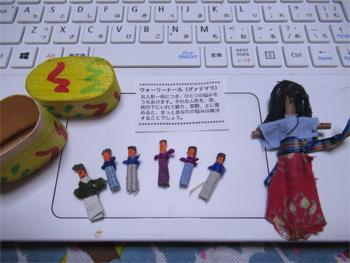 ���N�U�N���ɂȂ鑷���P�N���̎��A�ЂƂ肨�����łR�����܂����B���̎��̈���A���̖��������A���������w�����ق��E������s�����ɍs���܂����B�u�A��ɁA�~���[�W�A���V���b�v�ň�����v���[���g���Ă������v�ƌ�������A�Ȃ�Ɣޏ��A�u�������ɂ́A���E�̃R�[�q�[�A�ꂿ���́A�g�����������ȁH���Ƃ����́A�J�X�e���E�E�E�E�v�o�A�o�́A�ޏ��ɂ̂��肾�����̂ɁA����Ԃ݂̂�ȂɈ���B�����Ĕޏ��������̂��߂ɑI�̂́A�����ȃ}�g�����[�V�J�����Ԃ������ȃu���[�`�ł����B
���N�U�N���ɂȂ鑷���P�N���̎��A�ЂƂ肨�����łR�����܂����B���̎��̈���A���̖��������A���������w�����ق��E������s�����ɍs���܂����B�u�A��ɁA�~���[�W�A���V���b�v�ň�����v���[���g���Ă������v�ƌ�������A�Ȃ�Ɣޏ��A�u�������ɂ́A���E�̃R�[�q�[�A�ꂿ���́A�g�����������ȁH���Ƃ����́A�J�X�e���E�E�E�E�v�o�A�o�́A�ޏ��ɂ̂��肾�����̂ɁA����Ԃ݂̂�ȂɈ���B�����Ĕޏ��������̂��߂ɑI�̂́A�����ȃ}�g�����[�V�J�����Ԃ������ȃu���[�`�ł����B �@�K�c�^������͌o�Ϗ����Ƃł���A���I��c�̈ψ�����Ƃ̎ЊO�����̌o��������B�}���ق���K�c�^���̌o�σz���[�����u�����Ȃ̊K�i�v�i�p�쏑�X�j����o�����B6�̒Z�ҏ����ō\�����ꂽ�ǂ݂₷���{�������B
�@�K�c�^������͌o�Ϗ����Ƃł���A���I��c�̈ψ�����Ƃ̎ЊO�����̌o��������B�}���ق���K�c�^���̌o�σz���[�����u�����Ȃ̊K�i�v�i�p�쏑�X�j����o�����B6�̒Z�ҏ����ō\�����ꂽ�ǂ݂₷���{�������B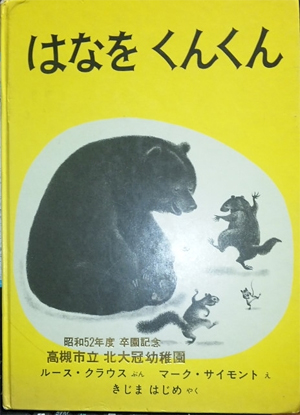 �@����ȋG�߂̊G�{�����Љ�����܂��傤�B����́A�����O�Z���[�̃V�[�}�[��A�u�͂Ȃ�����v�B��������܂������A���炵�������ł��B�����č�҂̃V�[�}�[����ɂ�������܂������A���N�̂悤�Ȃ��Ă��Ȃ���������ł����B
�@����ȋG�߂̊G�{�����Љ�����܂��傤�B����́A�����O�Z���[�̃V�[�}�[��A�u�͂Ȃ�����v�B��������܂������A���炵�������ł��B�����č�҂̃V�[�}�[����ɂ�������܂������A���N�̂悤�Ȃ��Ă��Ȃ���������ł����B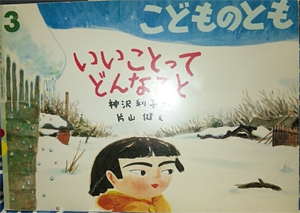 �@�������� �䂫�̂����ɂ����āA�����Ƃ������������ȂȂ���ɂȂ��� �������܂����B
�@�������� �䂫�̂����ɂ����āA�����Ƃ������������ȂȂ���ɂȂ��� �������܂����B �@�S���t�ɂ���قǂ̊S�͕����Ă��Ȃ����ł͂��邪�A2021�N4��12���i���{���ԁj�A�����J���O���W���[�W�A�B�̃I�[�K�X�^�E�i�V���i���E�S���t�N���u�ŊJ����Ă���}�X�^�[�Y�E�g�[�i�����g�̍ŏI���E���h�ɂ��ẮA���̍s�����e���r��ʂ�ʂ��Ď�Ɋ��������Č��Ă����B
�@�S���t�ɂ���قǂ̊S�͕����Ă��Ȃ����ł͂��邪�A2021�N4��12���i���{���ԁj�A�����J���O���W���[�W�A�B�̃I�[�K�X�^�E�i�V���i���E�S���t�N���u�ŊJ����Ă���}�X�^�[�Y�E�g�[�i�����g�̍ŏI���E���h�ɂ��ẮA���̍s�����e���r��ʂ�ʂ��Ď�Ɋ��������Č��Ă����B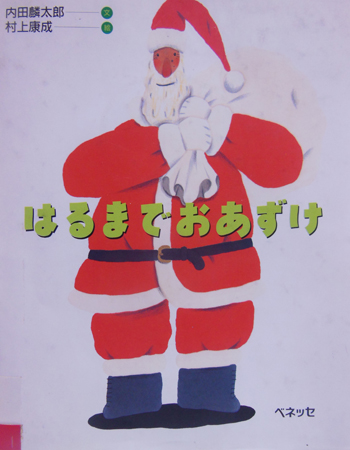 ���コ��̂ق�킩�Ƃ����G����D���ŁA�N���X�}�X�̍��̂Ȃ�Ƃ悭�o�ꂷ�����u�͂�܂ł��������i���c�ّ��Y�j�v�ł��B
���コ��̂ق�킩�Ƃ����G����D���ŁA�N���X�}�X�̍��̂Ȃ�Ƃ悭�o�ꂷ�����u�͂�܂ł��������i���c�ّ��Y�j�v�ł��B �@�u���� �Ȃ��� �����傤 �͂��ׂ� �قƂ��̂� ������ �������� ���ꂼ�����v�͏t�̎����ł��邪�A�H�̎����͂ǂ��o��������̂��B
�@�u���� �Ȃ��� �����傤 �͂��ׂ� �قƂ��̂� ������ �������� ���ꂼ�����v�͏t�̎����ł��邪�A�H�̎����͂ǂ��o��������̂��B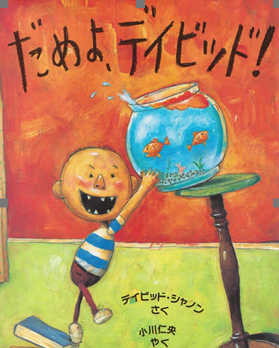 �@�悭���܂��A�q�ǂ������Ƃ����̂́A�����玟�Ƃ����Ȃ���������v�������̂ł��B�����A���������Еt�����Ǝv������A�܂�������E�E�E���������傫���Ȃ�܂��B
�@�悭���܂��A�q�ǂ������Ƃ����̂́A�����玟�Ƃ����Ȃ���������v�������̂ł��B�����A���������Еt�����Ǝv������A�܂�������E�E�E���������傫���Ȃ�܂��B �@�ꂩ��\�܂ł̐��̐������ɂ́A�a��n���̂ЂƂA�ӂ��A�݂��E�E�E�ȂȂA����A�����̂A�Ƃ��A�Ƃ����̂ƁA����n���̂����A�ɁA����E�E�E�����A�͂��A���i�������͂��イ�j�A���イ�A�Ƃ̓�ʂ肪���邱�Ƃ͉���͂悭�m���Ă���B
�@�ꂩ��\�܂ł̐��̐������ɂ́A�a��n���̂ЂƂA�ӂ��A�݂��E�E�E�ȂȂA����A�����̂A�Ƃ��A�Ƃ����̂ƁA����n���̂����A�ɁA����E�E�E�����A�͂��A���i�������͂��イ�j�A���イ�A�Ƃ̓�ʂ肪���邱�Ƃ͉���͂悭�m���Ă���B �@���N�O�̂��Ƃł����A10���̂���[�ׁA���Ƃ�20�l���ƊG�{�̎��Ԃ��������B
�@���N�O�̂��Ƃł����A10���̂���[�ׁA���Ƃ�20�l���ƊG�{�̎��Ԃ��������B �@�s���}���ق̃z�[���y�[�W�̐V���}�����߂Ă�����u49�Δ铒�ЂƂ藷�v�i���{�p�q�A�����V���o�Łj���ڂɕt�����B�V�^�R���i�E�C���X������������ǂ�������֍s�������ȁA�Ǝv���Ă������Ƃ�����A�Q�l�}���̂���Œ����Ɏ؏o�葱��������B�Y�ꂽ���ɑݏo�\�̘A�����������B
�@�s���}���ق̃z�[���y�[�W�̐V���}�����߂Ă�����u49�Δ铒�ЂƂ藷�v�i���{�p�q�A�����V���o�Łj���ڂɕt�����B�V�^�R���i�E�C���X������������ǂ�������֍s�������ȁA�Ǝv���Ă������Ƃ�����A�Q�l�}���̂���Œ����Ɏ؏o�葱��������B�Y�ꂽ���ɑݏo�\�̘A�����������B �@�ݘa�c�̕P�A�ƕ����Ē����ɕ���|�}����́u��h���킹�݁v���v���o���ꂽ�������������肻�����B
�@�ݘa�c�̕P�A�ƕ����Ē����ɕ���|�}����́u��h���킹�݁v���v���o���ꂽ�������������肻�����B �@��������}���قɁu���t�@�����X�����f�[�^�x�[�X�v�Ƃ����f�[�^�x�[�X������B���̃f�[�^�x�[�X�́A��������}���ق��S���̐}���قƋ����ō\�z���Ă��钲�ו��̂��߂̃f�[�^�x�[�X�ŁA���t�@�����X����A���ו��}�j���A�����̃f�[�^��~�ς��A�������C���^�[�l�b�g��ʂ��Ē��Ă���B���͐}���̃��t�@�����X�Ɋւ��Ă͌����_�ł͈�Ԗ��ɗ��f�[�^�x�[�X���낤�A�Ə���Ɏv���Ă���B
�@��������}���قɁu���t�@�����X�����f�[�^�x�[�X�v�Ƃ����f�[�^�x�[�X������B���̃f�[�^�x�[�X�́A��������}���ق��S���̐}���قƋ����ō\�z���Ă��钲�ו��̂��߂̃f�[�^�x�[�X�ŁA���t�@�����X����A���ו��}�j���A�����̃f�[�^��~�ς��A�������C���^�[�l�b�g��ʂ��Ē��Ă���B���͐}���̃��t�@�����X�Ɋւ��Ă͌����_�ł͈�Ԗ��ɗ��f�[�^�x�[�X���낤�A�Ə���Ɏv���Ă���B �@�{����D���ȖÂƂ���܂��{��D���l�Ԃ̏f���Ƃ̉�b�ł���B�ǂ̖{�ɏ�����Ă����̂��A�ǂ�ł��ĂƂĂ��y���������̂ŁA���ł����e���o���Ă���B
�@�{����D���ȖÂƂ���܂��{��D���l�Ԃ̏f���Ƃ̉�b�ł���B�ǂ̖{�ɏ�����Ă����̂��A�ǂ�ł��ĂƂĂ��y���������̂ŁA���ł����e���o���Ă���B �@�^�ӕ����̋�Ɂu�h�����Ɠ������o���ᐁ�i�ӂԂ��j�Ɓv������B���̏�̏�i���ڂɕ����Ԃ悤�ȋ�ł���B�i������ƒ��ׂ��Ƃ���ł́A�Â��́u�ᐁ�v����ʓI�ŁA���݂̂悤�ȁu����v��������̂͋ߐ��ɂȂ��Ă��炾�Ƃ��j
�@�^�ӕ����̋�Ɂu�h�����Ɠ������o���ᐁ�i�ӂԂ��j�Ɓv������B���̏�̏�i���ڂɕ����Ԃ悤�ȋ�ł���B�i������ƒ��ׂ��Ƃ���ł́A�Â��́u�ᐁ�v����ʓI�ŁA���݂̂悤�ȁu����v��������̂͋ߐ��ɂȂ��Ă��炾�Ƃ��j �@�L�����ł͞x���u�ǂ݂����̏����̊Ԃɂ͂���Ŗڈ�Ƃ�����́B�Â��͖ؕЁA�|�ЂȂǂł�������v�Ɛ������Ă���B
�@�L�����ł͞x���u�ǂ݂����̏����̊Ԃɂ͂���Ŗڈ�Ƃ�����́B�Â��͖ؕЁA�|�ЂȂǂł�������v�Ɛ������Ă���B �@�o�v���B�Y����͌Ï��X��ł���B�����Ē��؏܍�Ƃł�����B���̏o�v������Ɂu�{�̂����悲���ł����v�i�u�k�Ёj�Ƃ����D�ꂽ�G�b�Z�C�W������B�k�C���V�����j�łɁu�Ï������v�Ƃ���1987�N9������1990�N9���܂ł̊ԂɘA�ڂ��ꂽ���͂�Z�߂����̂ł���B
�@�o�v���B�Y����͌Ï��X��ł���B�����Ē��؏܍�Ƃł�����B���̏o�v������Ɂu�{�̂����悲���ł����v�i�u�k�Ёj�Ƃ����D�ꂽ�G�b�Z�C�W������B�k�C���V�����j�łɁu�Ï������v�Ƃ���1987�N9������1990�N9���܂ł̊ԂɘA�ڂ��ꂽ���͂�Z�߂����̂ł���B �@�X�[�p�[�C���|�[�Y�Ƃ����̂��낤���A����Ƃ��e���b�v���������̂��A�e���r�̃j���[�X�ԑg�Ȃǂł��̓��e�┭���҂̌��t���ʼn�ʕ\�����Ă���̂��悭��������B���o�ɖ�肪����l�����łȂ��A���o���������̕����������₷���l�ɂƂ��Ă͗L���ȕ��Ǝv���Ă��邪�A���ɂ͌�����������g���Ă���ꍇ������A�u�I�C�I�C�v�ƌ����������Ȃ�B
�@�X�[�p�[�C���|�[�Y�Ƃ����̂��낤���A����Ƃ��e���b�v���������̂��A�e���r�̃j���[�X�ԑg�Ȃǂł��̓��e�┭���҂̌��t���ʼn�ʕ\�����Ă���̂��悭��������B���o�ɖ�肪����l�����łȂ��A���o���������̕����������₷���l�ɂƂ��Ă͗L���ȕ��Ǝv���Ă��邪�A���ɂ͌�����������g���Ă���ꍇ������A�u�I�C�I�C�v�ƌ����������Ȃ�B �@���͓����{���Q�������悤�ȕs���ӂȐl�Ԃł͂Ȃ��Ǝv���Ă����B�{�����ɂ͖ړI���͂�����Ƃ��Ă���A�u���̖{���̂��v�Ƃ�������ƈӎ����Ă���ƐM���Ă����B�Ƃ��낪���ɂ����Ă��ē����{���Q������P�[�X�ɉ��x���Ԃ������B
�@���͓����{���Q�������悤�ȕs���ӂȐl�Ԃł͂Ȃ��Ǝv���Ă����B�{�����ɂ͖ړI���͂�����Ƃ��Ă���A�u���̖{���̂��v�Ƃ�������ƈӎ����Ă���ƐM���Ă����B�Ƃ��낪���ɂ����Ă��ē����{���Q������P�[�X�ɉ��x���Ԃ������B �@���ɖʔ����B�{�̒��͉p����bookworm���������A���́u�{�̒��̖{�v�i�n���Ёj�̒��҂���bookworms���� �N�v���ق��S���ʼn�ƁA�V�����X���A�Ö{���X��A�t���[���C�^�[�A�W���[�i���X�g�ƏЉ��Ă���B���ꂼ��̕����A�R�O�ґO��̃G�b�Z�C�Ƃ���������Ƃ��R�������邢�͐��M�Ƃ����̂��������̂��A�P�łQ�i�łS�i�قǂ̒Z����������Ă���B
�@���ɖʔ����B�{�̒��͉p����bookworm���������A���́u�{�̒��̖{�v�i�n���Ёj�̒��҂���bookworms���� �N�v���ق��S���ʼn�ƁA�V�����X���A�Ö{���X��A�t���[���C�^�[�A�W���[�i���X�g�ƏЉ��Ă���B���ꂼ��̕����A�R�O�ґO��̃G�b�Z�C�Ƃ���������Ƃ��R�������邢�͐��M�Ƃ����̂��������̂��A�P�łQ�i�łS�i�قǂ̒Z����������Ă���B �@���ɖʔ����B���߂Ă��ĖO���邱�Ƃ��Ȃ��B�u�n�}�̔����}�Ӂv�i���o�W�I�O���t�B�b�N�ЁA�x�b�c�C�E���C�\���A�O���b�O�E�~���[���A���䗯����j�́A�c28�p�A��23.3�p�A�d��1.35�s�ł���A���̌`��d�ʂɌ������m����y���݂���Ă��ꂽ�B
�@���ɖʔ����B���߂Ă��ĖO���邱�Ƃ��Ȃ��B�u�n�}�̔����}�Ӂv�i���o�W�I�O���t�B�b�N�ЁA�x�b�c�C�E���C�\���A�O���b�O�E�~���[���A���䗯����j�́A�c28�p�A��23.3�p�A�d��1.35�s�ł���A���̌`��d�ʂɌ������m����y���݂���Ă��ꂽ�B �@�H�n���Ƃ͖��͓I�Ȍ��t�ł���B�\�ʂ�̉₩���⌖���Ƃ͖����́A�����ɖ����������������������ʘH�Ƃ����ɂ��邿����Ƃ����L�������������B�����ł͒n��ɍ��t�����l�X�̓��퐶�����_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B
�@�H�n���Ƃ͖��͓I�Ȍ��t�ł���B�\�ʂ�̉₩���⌖���Ƃ͖����́A�����ɖ����������������������ʘH�Ƃ����ɂ��邿����Ƃ����L�������������B�����ł͒n��ɍ��t�����l�X�̓��퐶�����_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B �@�G�b�Z�C�̒��Łu�����ƐV�����]���C�ɂȂ�A���̗�����V����ǂݎn�߂�v�Ə�����Ă����̂́A�ǂȂ��������낤���B���̍����炩�����]��ǂނ悤�ɂȂ������A���ӎ��Ɏ��g�̔N��Ɣ�r���Ă���悤���B
�@�G�b�Z�C�̒��Łu�����ƐV�����]���C�ɂȂ�A���̗�����V����ǂݎn�߂�v�Ə�����Ă����̂́A�ǂȂ��������낤���B���̍����炩�����]��ǂނ悤�ɂȂ������A���ӎ��Ɏ��g�̔N��Ɣ�r���Ă���悤���B �@�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���Ԃʂɂ��Ă͂����Ȃ��A�Ǝv����������C�͂��������炾��Ǝ��Ԃ�ׂ��悤�ȓ����������Ƃ�����B���̂悤�Ȏ��ɂ́A�ǂ݂₷���Z�ҏW��G�b�Z�C�W����Ɏ��Ɍ���B���ꂪ��������Ƃ������́A�z�Ƃ������͂ŏ�����Ă���Ό������Ƃ͂Ȃ��B
�@�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���Ԃʂɂ��Ă͂����Ȃ��A�Ǝv����������C�͂��������炾��Ǝ��Ԃ�ׂ��悤�ȓ����������Ƃ�����B���̂悤�Ȏ��ɂ́A�ǂ݂₷���Z�ҏW��G�b�Z�C�W����Ɏ��Ɍ���B���ꂪ��������Ƃ������́A�z�Ƃ������͂ŏ�����Ă���Ό������Ƃ͂Ȃ��B �u�{�Ƃ킽���v�Ƃ����e�[�}�ŗ��Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A�{�̏����ł���B�Â��ǂ�����ɂ����ẮA���X�X�̕Ћ����w�̋߂��ɌÖ{��������A����炪�n���ł͂��邪�Ö{�̔������n�߂Ƃ���Ï��̗��ʂɑ傫�ȗ͂�݂��Ă����B�����̓X�Ƌq�Ƃ̊Ԃ̐l����ӂ�鏔�X�����������͂�����ǂL�������邵�A���̌Ö{�����发�������Ï���̎�l�̌o���k���������������̖{�͈ꎞ�����̈��Ǐ��������B
�u�{�Ƃ킽���v�Ƃ����e�[�}�ŗ��Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A�{�̏����ł���B�Â��ǂ�����ɂ����ẮA���X�X�̕Ћ����w�̋߂��ɌÖ{��������A����炪�n���ł͂��邪�Ö{�̔������n�߂Ƃ���Ï��̗��ʂɑ傫�ȗ͂�݂��Ă����B�����̓X�Ƌq�Ƃ̊Ԃ̐l����ӂ�鏔�X�����������͂�����ǂL�������邵�A���̌Ö{�����发�������Ï���̎�l�̌o���k���������������̖{�͈ꎞ�����̈��Ǐ��������B �@�ؗF������u���O�̃R�����ł��̖{�u�����̎d���v�i���� ���A��g�V���j�̂��Ƃ������[�������Ă����̂ŁA�ނɕ���Ď�����Ɏ�����B��g���X�Łu�L�����v�u��g���ꎫ�T�v���̕ҏW��Ƃɂ���������l�����A����̌o���܂��Ď������߂��邳�܂��܂Ȃ��Ƃ�f�l�ɕ�����悤�ɉ������������{�ł���B
�@�ؗF������u���O�̃R�����ł��̖{�u�����̎d���v�i���� ���A��g�V���j�̂��Ƃ������[�������Ă����̂ŁA�ނɕ���Ď�����Ɏ�����B��g���X�Łu�L�����v�u��g���ꎫ�T�v���̕ҏW��Ƃɂ���������l�����A����̌o���܂��Ď������߂��邳�܂��܂Ȃ��Ƃ�f�l�ɕ�����悤�ɉ������������{�ł���B �@�����̍��A���s�ɒP�g���C���Ă����y�ɗU���ċ��s������i���j�܂ł̓��C���̈ꕔ����������Ƃ�����B�^�Ă̓��j���A�y�b�g�{�g�������{����ɂ��A�i�q���s�w���o���_�ɗ��h�A�����h���߂��Ăi�q���Ήw�܂ŕ������B��y�͎�ɂ������������Ȃ��炢�낢��Ɛ������Ă��ꂽ���A����̐Ί_�ȊO�͉����o���Ă��Ȃ��B
�@�����̍��A���s�ɒP�g���C���Ă����y�ɗU���ċ��s������i���j�܂ł̓��C���̈ꕔ����������Ƃ�����B�^�Ă̓��j���A�y�b�g�{�g�������{����ɂ��A�i�q���s�w���o���_�ɗ��h�A�����h���߂��Ăi�q���Ήw�܂ŕ������B��y�͎�ɂ������������Ȃ��炢�낢��Ɛ������Ă��ꂽ���A����̐Ί_�ȊO�͉����o���Ă��Ȃ��B �@�ߓ��f�ڂ����������u�H��̕����v�ŁA�{���\�����Ă��镶���ɂ��ď������B����͓������{���\�����镶�╶�͂ɂ��Ă�����ƍl���Ă݂悤�Ǝv���B
�@�ߓ��f�ڂ����������u�H��̕����v�ŁA�{���\�����Ă��镶���ɂ��ď������B����͓������{���\�����镶�╶�͂ɂ��Ă�����ƍl���Ă݂悤�Ǝv���B �@�}���ق֖{��Ԃ��ɍs�������łɁA���I���`���b�ƒ��߂��B���ɉ�����悤�Ƃ������Ă��Ȃ��A���ׂ��Ă���G�b�Z�C�W�̕\���ڂŒǂ��Ă����B
�@�}���ق֖{��Ԃ��ɍs�������łɁA���I���`���b�ƒ��߂��B���ɉ�����悤�Ƃ������Ă��Ȃ��A���ׂ��Ă���G�b�Z�C�W�̕\���ڂŒǂ��Ă����B �@���ĕS�ڋS���O�Y����̖���m�����Ƃ��ɂ́A�g�ǂ��߂����傤���Ԃ낤�h�Ɛ������ǂ߂Ȃ������B���ɂɂ͑S�Ăł͂Ȃ������̒��삪����������B���̒��̉������͓����ɒP�g���C���Ă���Ƃ��ɔ������̂��낤�B����{�ɂ͞x����ɑ�J���p�قƋ��Ð�뉀�̓��ꌔ�̔��������܂�Ă����B
�@���ĕS�ڋS���O�Y����̖���m�����Ƃ��ɂ́A�g�ǂ��߂����傤���Ԃ낤�h�Ɛ������ǂ߂Ȃ������B���ɂɂ͑S�Ăł͂Ȃ������̒��삪����������B���̒��̉������͓����ɒP�g���C���Ă���Ƃ��ɔ������̂��낤�B����{�ɂ͞x����ɑ�J���p�قƋ��Ð�뉀�̓��ꌔ�̔��������܂�Ă����B �@������x�̔N��ɂȂ藈������U��Ԃ�]�T���o�Ă����Ƃ��A�l�͎���̐l����Z�߂����Ȃ�̂��낤���B�����Ă�����q�������⑷�����ɓǂ�ł��炢�����Ȃ�̂��낤���B
�@������x�̔N��ɂȂ藈������U��Ԃ�]�T���o�Ă����Ƃ��A�l�͎���̐l����Z�߂����Ȃ�̂��낤���B�����Ă�����q�������⑷�����ɓǂ�ł��炢�����Ȃ�̂��낤���B �@���Â̐l�X�̈ߑ��ɂ��āA���сi���������j�͑��瑕�ő�畞�̂悤�Ȃ��́A��߁i���肬�ʁj�̓��[�j���O���x�̗畞�A�����i�Ђ�����j�͔w�L�ɂ�����A���Ƃ��Ƃ͐g���̌y�������̒����ł������f���i�������j�͕��m�̒ʏ핞�ɂȂ����A�Ƃ������m���Ƃ��ꂼ��̓��e�⒅�鏇���ȂǍׂ������Ƃ�m�����̂́A�w�K�Q�l���́u�Õ������@�v�i���z�Ёj�̐��������炾�����B
�@���Â̐l�X�̈ߑ��ɂ��āA���сi���������j�͑��瑕�ő�畞�̂悤�Ȃ��́A��߁i���肬�ʁj�̓��[�j���O���x�̗畞�A�����i�Ђ�����j�͔w�L�ɂ�����A���Ƃ��Ƃ͐g���̌y�������̒����ł������f���i�������j�͕��m�̒ʏ핞�ɂȂ����A�Ƃ������m���Ƃ��ꂼ��̓��e�⒅�鏇���ȂǍׂ������Ƃ�m�����̂́A�w�K�Q�l���́u�Õ������@�v�i���z�Ёj�̐��������炾�����B �@����Ɂg���q�����ꕔ���������Ƃ��h�Ƃ�����傪�t���ꂽ�A2020�N6�����s�̏����u�M�l�D�ҁv�i�ɓ��S���A�V���Ёj��m�����̂́A���N�W�����̃��W�I�ԑg���炾�����B�ǂ̗l�ȏЉ�������͍��ł͑S���o���Ă��Ȃ����A�����ɐ}���ق̏������������A�\���̂����牽�������鏊���������̂��낤�B
�@����Ɂg���q�����ꕔ���������Ƃ��h�Ƃ�����傪�t���ꂽ�A2020�N6�����s�̏����u�M�l�D�ҁv�i�ɓ��S���A�V���Ёj��m�����̂́A���N�W�����̃��W�I�ԑg���炾�����B�ǂ̗l�ȏЉ�������͍��ł͑S���o���Ă��Ȃ����A�����ɐ}���ق̏������������A�\���̂����牽�������鏊���������̂��낤�B �@�e���r��ʂ���u���������������v�Ƃ��������������ė�����A��ʂ̐l�����u���������������v�Ɛ������������Ă���̂ɁA��ʂ̕����ł́u���������������v�ƂȂ��Ă����肷��̂�����ƁA���͔��Ɉ�a�����o����B
�@�e���r��ʂ���u���������������v�Ƃ��������������ė�����A��ʂ̐l�����u���������������v�Ɛ������������Ă���̂ɁA��ʂ̕����ł́u���������������v�ƂȂ��Ă����肷��̂�����ƁA���͔��Ɉ�a�����o����B �@2020�N11��3����NHK�̃��W�I�[��փA�[�J�C�u�X�u�l�ԍ���ɕ����v�ōu�k�t�E�_�c����u�j�̔��w�v�Ƃ����e�[�}�Řb������Ă����B�u�k�ł悭�o�Ă���g�`���S�h��g����Y��Ȃ��h�Ƃ������Ƃ��܂ߋ����[���b���������A���͕ςȂ��Ƃ��C�ɂȂ��Ă����B����́u�j�̔��w�v�Ƃ������t�ɂ��Ă������B
�@2020�N11��3����NHK�̃��W�I�[��փA�[�J�C�u�X�u�l�ԍ���ɕ����v�ōu�k�t�E�_�c����u�j�̔��w�v�Ƃ����e�[�}�Řb������Ă����B�u�k�ł悭�o�Ă���g�`���S�h��g����Y��Ȃ��h�Ƃ������Ƃ��܂ߋ����[���b���������A���͕ςȂ��Ƃ��C�ɂȂ��Ă����B����́u�j�̔��w�v�Ƃ������t�ɂ��Ă������B �@�����̒ʊw���Ԃ��g���A����1���R�O�~�������V�O�őO��̃A�e�l���Ɂi�O�����̊w�p�n���ɁA1948�N�n���A301���������Ċ��s�x�~�A2010�N���ꕔ�ɂ������Ŋ��s�j���W���������킸�����P���ǔj���Ă����������������B���e�𗝉����Ă������ۂ��͋ɂ߂ċ^��ł��邪�A�������{�͑S�ēd�ԓ��œǂݒʂ������Ƃ����͊ԈႢ���Ȃ��B
�@�����̒ʊw���Ԃ��g���A����1���R�O�~�������V�O�őO��̃A�e�l���Ɂi�O�����̊w�p�n���ɁA1948�N�n���A301���������Ċ��s�x�~�A2010�N���ꕔ�ɂ������Ŋ��s�j���W���������킸�����P���ǔj���Ă����������������B���e�𗝉����Ă������ۂ��͋ɂ߂ċ^��ł��邪�A�������{�͑S�ēd�ԓ��œǂݒʂ������Ƃ����͊ԈႢ���Ȃ��B �@�}�X�R�~�Œ��쌠�N�Q��肪����A�c�_����Ă���̂��݂�ƁA�������˓I�Ɉ꓁���f�̉����͓�����낤�ȁA�Ǝv���Ă��܂��B�Η����Ă���o���̈ӌ��〈�����ƁA�O��Ȃ���ł͂��邪�A���ꂼ��ɂ��āu������������v�u���̂悤�ȍl����������Ȃ��v�Ɠ������A����̓����҂̗���ɗ����A������̌����ɕ��S�����肷��B
�@�}�X�R�~�Œ��쌠�N�Q��肪����A�c�_����Ă���̂��݂�ƁA�������˓I�Ɉ꓁���f�̉����͓�����낤�ȁA�Ǝv���Ă��܂��B�Η����Ă���o���̈ӌ��〈�����ƁA�O��Ȃ���ł͂��邪�A���ꂼ��ɂ��āu������������v�u���̂悤�ȍl����������Ȃ��v�Ɠ������A����̓����҂̗���ɗ����A������̌����ɕ��S�����肷��B �@���́u�r�g�����Y�̂��������������v�i��\�F�A���}�Ёj�͌Ö{���Ō������B
�@���́u�r�g�����Y�̂��������������v�i��\�F�A���}�Ёj�͌Ö{���Ō������B �@���ɖ{�͏������ׂ����Ђ̕M���ɂ������邾�낤�A�Ƃ͎��̓ƒf�ł���B���R�͂��낢��Ǝv�������A���ꂼ��Ɉ٘_���o�����Ɏv����̂ŁA�����ł́u�c�_�͔�����ɔ@�����v���x�X�g�̑I�����B
�@���ɖ{�͏������ׂ����Ђ̕M���ɂ������邾�낤�A�Ƃ͎��̓ƒf�ł���B���R�͂��낢��Ǝv�������A���ꂼ��Ɉ٘_���o�����Ɏv����̂ŁA�����ł́u�c�_�͔�����ɔ@�����v���x�X�g�̑I�����B �@�����̍��A���܂ɎႢ�F�l���炠�����̃e�[�}�ɂ��ēǂނׂ��{�A���邢�͎Q�l�ɂ��ׂ������̏Љ�𗊂܂�邱�Ƃ��������B���̂悤�ȂƂ��́A�������̖{��I�сA��{�I�ȏ����͂���A�����葁���T�v��m��ɂ͂��̖{�A�ŋ߂̌������ʂ͂��̘_���W�ȂǂƂ��̓����܂��Ęb���Ă����B
�@�����̍��A���܂ɎႢ�F�l���炠�����̃e�[�}�ɂ��ēǂނׂ��{�A���邢�͎Q�l�ɂ��ׂ������̏Љ�𗊂܂�邱�Ƃ��������B���̂悤�ȂƂ��́A�������̖{��I�сA��{�I�ȏ����͂���A�����葁���T�v��m��ɂ͂��̖{�A�ŋ߂̌������ʂ͂��̘_���W�ȂǂƂ��̓����܂��Ęb���Ă����B �@�ŋ߁A�u�L����V�l�v�ƌ������t���ȑO�ɑ����ĕ������Ƃ������Ȃ����B�c�O�Ȃ���X���i�܂��Ȃ��j�ł����̐l��ڂɂ��邱�Ƃ�����B���Ƃ͂��̌��������낢��������Ă����B
�@�ŋ߁A�u�L����V�l�v�ƌ������t���ȑO�ɑ����ĕ������Ƃ������Ȃ����B�c�O�Ȃ���X���i�܂��Ȃ��j�ł����̐l��ڂɂ��邱�Ƃ�����B���Ƃ͂��̌��������낢��������Ă����B|
�� |
���l���A�������u�����v���ƁA�u���Ă���邱�Ɓv�����҂��Ă͂����Ȃ��B���̂悤�Ȏ�g�̎p���́A�Ⴂ���ɂ͗c�����A�N�Ƃ��Ă���͘V�N���Ɩ��ڂȊW�������̂�����ł���B |
|
| �@�]�삳��͕ʒ��u�ӔN�̔��w�����߂āv�i�����V���Ёj�Łu����Ȃ��v���ƌ����^�C�g���Łu�����̐��_���ǂꂾ���V�����Ă��邩��ʂ�ɂ́A�ǂꂭ�炢�̕p�x�Łw����Ȃ��x�i�u�N�X�����X�����Ă���Ȃ��v�ƌ������t�j���邩�ׂĂ݂�Ƃ����v�Ƃ������Ă���B | ||
|
�� |
�Ⴓ�Ɏ��i���Ȃ����ƁB�Ⴂ�l�𗧂Ă邱�ƁB |
|
| �@���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����B�����ɑ�l�C�i���ƂȂ��j�̂Ȃ��s�����������ɂȂ�B | ||
|
�� |
���邭���邱�ƁB�S�̒��͂����łȂ��Ă��A�O�������ł����邭���邱�ƁB |
|
| �@�]�삳��́u�V���̍ˊo�v�i�x�X�g�V���j�ɂ���u�����ɂȂ��Ă��w���_�̂�����ꂪ��x�Ƃ��ꖬ���ʂ���̂��낤���B | ||
|
�� |
�R�����ʂ��ƁB |
|
| �@����ɂ́A�����v�肻�����B�]�삳��́u���{�l�ɂ͉����Ƃ����\���@�����邩��A���̉R���A�����Ĉ��ӂ���ł��̂ł͂Ȃ��̂ł���v�Ə����A�u�ނ��날���炳�܂ɁA�����̖]�݂��������Ƃ̂ق����A�͂����猩�Ă��킢�炵���V�l�Ɍ�����v�Ə����Ă���B�����Ƃ������̉R�̈ӂł���B | ||
|
�� |
�U���I�ł��邱�Ƃ���߂邱�ƁB�N���́A�ێ�I�ǂ��납�A�j��I�A�U���I�ł���B�������A�l����̂̈���������Ȃ����ƁB |
|
| �@�]�삳��́u�{��A�̂̂��邱�Ƃ́A������������Ȃ��Ȃ邱�Ƃɑ��锪�����肾�Ǝ����������B�c�c�ǂ����Ă��S�⓯�������ĂȂ�������A�����Â��ɉ�����������v�Ə����B���_�q��������̕��������Ǝ����v���B | ||
|
�� |
���l�̎����鎞�́A�E�ƂƂ��Ċ��肫���Ă���Ă����l���g�����ƁB���l�̍D�ӂ����܂����p���悤�Ƃ��邳�����������͂����Ȃ��B |
|
|
�@����҂Ɏ��݂����Ǝ��̂���т��ƍl���A���s����l�тƂ����������݂���B���̐g�߂ɂ�����������B�u���������l�v�Ɓu�������l�v�Ƃ̊W���O�삩�猩�Ă���Ə�肭�͐����ł��Ȃ����A���ɗ��z�I�̂悤�Ɏv����B |
||
 �@�}���ق̏��I�߂Ă���Ɓu�����̉�Ɓ@�t�F�����[���̓�Ɩ��́v�i���i �T�A�G�a�V�X�e���j���ڂɕt�����B�t�F�����[�������������������Ă���̂��A���������������o�����B
�@�}���ق̏��I�߂Ă���Ɓu�����̉�Ɓ@�t�F�����[���̓�Ɩ��́v�i���i �T�A�G�a�V�X�e���j���ڂɕt�����B�t�F�����[�������������������Ă���̂��A���������������o�����B �@���������̍����������A�u�t�Ƃ͐l���̂�����Ԃł͂Ȃ��A�S�̎��������������v��u�N���d�˂������Ől�͘V���Ȃ��B���z�������Ƃ����߂ĘV����v�Ƃ�����傪�܂܂�Ă���T���G���E�E���}���̎��u�t�v�́A�����̊�Ɛl�Ɋ�����^���A�����Ȉ��A�̏�Ō���A�V������A�Г����ŕ��Ă����B�T���������W��g�B
�@���������̍����������A�u�t�Ƃ͐l���̂�����Ԃł͂Ȃ��A�S�̎��������������v��u�N���d�˂������Ől�͘V���Ȃ��B���z�������Ƃ����߂ĘV����v�Ƃ�����傪�܂܂�Ă���T���G���E�E���}���̎��u�t�v�́A�����̊�Ɛl�Ɋ�����^���A�����Ȉ��A�̏�Ō���A�V������A�Г����ŕ��Ă����B�T���������W��g�B �@������x�̐��̐l���b���Ă��錾��Ƃ��āA���ݐ��E�ɂ�1,000���̌��ꂪ���邻�����B�܂��A���̓��ōł��g�p����Ă��錾��͉p��ł���A�P�T���l���p���b���Ƃ����B
�@������x�̐��̐l���b���Ă��錾��Ƃ��āA���ݐ��E�ɂ�1,000���̌��ꂪ���邻�����B�܂��A���̓��ōł��g�p����Ă��錾��͉p��ł���A�P�T���l���p���b���Ƃ����B �@�Y�o�V���[���̈�ʉ��i�Ɂu���̈���@�r�u���I�G�b�Z�[�v�Ƃ����ǎғ��e��������B�����ɂ�600�����x�ɓZ�߂�ꂽ�A�{�ɂ��Ă̂��܂��܂Ȑ������̕��͂��f�ڂ���Ă���B�u���e�̓y���l�[���v�Ƃ���Ă��邪�A�����̕��͎����ŏ�����Ă���B
�@�Y�o�V���[���̈�ʉ��i�Ɂu���̈���@�r�u���I�G�b�Z�[�v�Ƃ����ǎғ��e��������B�����ɂ�600�����x�ɓZ�߂�ꂽ�A�{�ɂ��Ă̂��܂��܂Ȑ������̕��͂��f�ڂ���Ă���B�u���e�̓y���l�[���v�Ƃ���Ă��邪�A�����̕��͎����ŏ�����Ă���B �@�ؗF���u���O�Łu���Ă���ǂނ��v�u�ǂ�ł��猩�邩�v�Ɩ����N���Ă����B�f��Ƃ��̌���ɂ��Ăł���B
�@�ؗF���u���O�Łu���Ă���ǂނ��v�u�ǂ�ł��猩�邩�v�Ɩ����N���Ă����B�f��Ƃ��̌���ɂ��Ăł���B �@�����̋@��ɐ搶��Ǐ��D���̗F�l�ɑE�߂�ꂽ��A�����̒��Ō��܂���Ă����肵�Ă����{��T�����v���o�b�ł���B
�@�����̋@��ɐ搶��Ǐ��D���̗F�l�ɑE�߂�ꂽ��A�����̒��Ō��܂���Ă����肵�Ă����{��T�����v���o�b�ł���B �@�������̖{�A���� �A����́u�M���̊��v�i�㉺�A���t���Ɂj�����̂ɂ́A���v���o���ƁA�ǂ������҂ɗ��R���������悤���B
�@�������̖{�A���� �A����́u�M���̊��v�i�㉺�A���t���Ɂj�����̂ɂ́A���v���o���ƁA�ǂ������҂ɗ��R���������悤���B �@�C�����̂����t�̈���A�����̃E�I�[�L���O�̃��[�g�������ς��āAJR���C���������̗ΖL���ȗV������������B���̂Qkm���̗V���������ɂ͍�N���ɐV�����J�ق����s���}���ق�����B���܂Ŕ`�������Ƃ͂Ȃ��������A������Ɨ�������Ă݂悤�Ǝv�����B���s�̍Ȃ͂��̊ԁA�r���Ō������y�M��E��ł���ƌ����B
�@�C�����̂����t�̈���A�����̃E�I�[�L���O�̃��[�g�������ς��āAJR���C���������̗ΖL���ȗV������������B���̂Qkm���̗V���������ɂ͍�N���ɐV�����J�ق����s���}���ق�����B���܂Ŕ`�������Ƃ͂Ȃ��������A������Ɨ�������Ă݂悤�Ǝv�����B���s�̍Ȃ͂��̊ԁA�r���Ō������y�M��E��ł���ƌ����B �@���]����m��Ȃ������{��m��A���̌セ�̖{�����Ǐ��̈���ƂȂ����o���͉��x������B�܂��t�Ɂu���]���x���ꂽ�v�u���ԖJ�߁v�Ǝv�������Ƃ�����B�������l�ɏ��]���������Ƃ͂ƂĂ�����B���̋ɒv�Ƃ������錩���ȏ��]�ɏo������B
�@���]����m��Ȃ������{��m��A���̌セ�̖{�����Ǐ��̈���ƂȂ����o���͉��x������B�܂��t�Ɂu���]���x���ꂽ�v�u���ԖJ�߁v�Ǝv�������Ƃ�����B�������l�ɏ��]���������Ƃ͂ƂĂ�����B���̋ɒv�Ƃ������錩���ȏ��]�ɏo������B �@�������ʐ^���ԓ��ł͈�ĒʐM����K�v��������̘A���̂��߂Ƀ��[�����O���X�g���g���Ă���B���̕��͂������Ă��鎞�_�ł̍ŐV���[���̔ԍ���5,939�ƂȂ��Ă����B
�@�������ʐ^���ԓ��ł͈�ĒʐM����K�v��������̘A���̂��߂Ƀ��[�����O���X�g���g���Ă���B���̕��͂������Ă��鎞�_�ł̍ŐV���[���̔ԍ���5,939�ƂȂ��Ă����B �@�V�^�R���i�E�C���X���ŊO�o�����l���Ă������ԂɁA�������j����́u�m�Ԕ���V���v�i�}�����[�j��ǂB���̖{�́A��������ɓǏ��̎t�Ǝv���Ă��邠��Ǐ��l�̏����Ō��܂���Ă���A���Ȃ�ȑO�ɔ��������̂ł���B�w���㒼���ɓǂݎn�߂����A�ŏ��̂Q�`�R���ǂƂ���ŁA�ƂĂ����̒m����\�͂͋y�Ȃ��A�R�ł��Ȃ��A�ǂ݉������Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƒ��߂��L��������B
�@�V�^�R���i�E�C���X���ŊO�o�����l���Ă������ԂɁA�������j����́u�m�Ԕ���V���v�i�}�����[�j��ǂB���̖{�́A��������ɓǏ��̎t�Ǝv���Ă��邠��Ǐ��l�̏����Ō��܂���Ă���A���Ȃ�ȑO�ɔ��������̂ł���B�w���㒼���ɓǂݎn�߂����A�ŏ��̂Q�`�R���ǂƂ���ŁA�ƂĂ����̒m����\�͂͋y�Ȃ��A�R�ł��Ȃ��A�ǂ݉������Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƒ��߂��L��������B �u���S�v�u�B��S�v�Ƃ������t��m���ċv�����B���̎���ɂ��A�V��j���ɍS��炸�A�S���ɏ�邱�Ƃ�S����Ԃ̎ʐ^���B�邱�Ƃ��y���ޓS���t�@�������݂���B
�u���S�v�u�B��S�v�Ƃ������t��m���ċv�����B���̎���ɂ��A�V��j���ɍS��炸�A�S���ɏ�邱�Ƃ�S����Ԃ̎ʐ^���B�邱�Ƃ��y���ޓS���t�@�������݂���B �@�C�O�o����C�O���s�ɍs���ɍۂ��Ă͊C�O���s�ی���t�ۂ��邱�Ƃ͏펯�ł��낤�B�����������t�ۂ����{�l�͎��炪���ɑ������邱�Ƃ͂܂��l���Ă��Ȃ��B���������ł���g�ی��͂����h���x�̔F���ł���B
�@�C�O�o����C�O���s�ɍs���ɍۂ��Ă͊C�O���s�ی���t�ۂ��邱�Ƃ͏펯�ł��낤�B�����������t�ۂ����{�l�͎��炪���ɑ������邱�Ƃ͂܂��l���Ă��Ȃ��B���������ł���g�ی��͂����h���x�̔F���ł���B �@�ŋ߂̓��W�I���悭�����悤�ɂȂ����B���X���q����Ƃ���1968�N���܂�̃m���t�B�N�V�����E���C�^�[��m�����̂́A�Q�X�g�Ƃ��ČĂꎩ��̍�i�ɂ��Ă̘b������Ă������郉�W�I�ԑg��ʂ��Ă������B
�@�ŋ߂̓��W�I���悭�����悤�ɂȂ����B���X���q����Ƃ���1968�N���܂�̃m���t�B�N�V�����E���C�^�[��m�����̂́A�Q�X�g�Ƃ��ČĂꎩ��̍�i�ɂ��Ă̘b������Ă������郉�W�I�ԑg��ʂ��Ă������B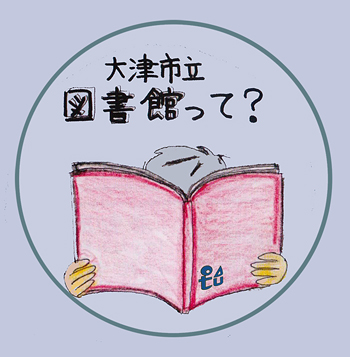 �@�Q�O�Q�O�N�x�̑傫�Ȋ����́w��Îs���}���ق��āH�x�Ƒ肷��}���ق̃��[�t���b�g��肾�����B����́A�������̉�̒��N�̖��Ƃł��������g�݂������B����ƁA���ꂪ�������Ďs���̊F����̌��ɓ͂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ƃ�{���Ɋ������v���B
�@�Q�O�Q�O�N�x�̑傫�Ȋ����́w��Îs���}���ق��āH�x�Ƒ肷��}���ق̃��[�t���b�g��肾�����B����́A�������̉�̒��N�̖��Ƃł��������g�݂������B����ƁA���ꂪ�������Ďs���̊F����̌��ɓ͂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ƃ�{���Ɋ������v���B �@2012�N12���ɂ��S���Ȃ�ɂȂ����Ē��M�Y����́A�����D�����������m�̈�l�ł���B�j��ŔN����50�Ŗ��l�ʂ����A�Ō�ɂ͓��{�����A��������߂�ꂽ�B�{�l�͔ے肵�Ă��邪�A�Ē�����̌��t�Ƃ��ėL���Ȃ̂́A�u�Z�B�R�l�͓����������瓌��֍s�����B�����͓����ǂ����珫���w���ɂȂ����v������B
�@2012�N12���ɂ��S���Ȃ�ɂȂ����Ē��M�Y����́A�����D�����������m�̈�l�ł���B�j��ŔN����50�Ŗ��l�ʂ����A�Ō�ɂ͓��{�����A��������߂�ꂽ�B�{�l�͔ے肵�Ă��邪�A�Ē�����̌��t�Ƃ��ėL���Ȃ̂́A�u�Z�B�R�l�͓����������瓌��֍s�����B�����͓����ǂ����珫���w���ɂȂ����v������B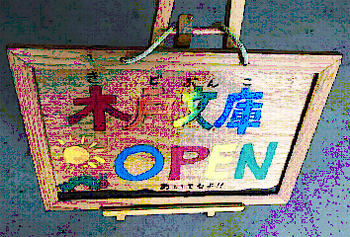 �@�����Ȗ،˕��ɂ́A�ΐ����u��w���~��ĂT���قǂ̏��A�����̐_�ЎQ�����̖،ˉ�ق̒��ɂ���B���Ɉ��A�P�O�����`�P�P�����܂ŊJ�قƂ��������ȕ��ɂ��B�O���̂R�O���͂��b��A�㔼�͖{�����E�I�Ԏ��Ԃ��B���ʑ傫�Ȑ�`������Ă��Ȃ��ŁA������S�~�J�����_�[���ɉ����[���\�肪�����Ă���B��ق̌��ւ����Ǝ���̕��ɂ̎D���u���Ă���B�m��l���m�镶�ɁA���R�~�ŗ��p�҂��ʂ��Ă��镶�ɂ��B
�@�����Ȗ،˕��ɂ́A�ΐ����u��w���~��ĂT���قǂ̏��A�����̐_�ЎQ�����̖،ˉ�ق̒��ɂ���B���Ɉ��A�P�O�����`�P�P�����܂ŊJ�قƂ��������ȕ��ɂ��B�O���̂R�O���͂��b��A�㔼�͖{�����E�I�Ԏ��Ԃ��B���ʑ傫�Ȑ�`������Ă��Ȃ��ŁA������S�~�J�����_�[���ɉ����[���\�肪�����Ă���B��ق̌��ւ����Ǝ���̕��ɂ̎D���u���Ă���B�m��l���m�镶�ɁA���R�~�ŗ��p�҂��ʂ��Ă��镶�ɂ��B �@���̍D���ȗ���Ƃ̈�l�Ɍj ����������������B
�@���̍D���ȗ���Ƃ̈�l�Ɍj ����������������B �@�����B���̃X�e�[�V�����u�،ˏ��w�Z�v���B�l�̏Z��ł���a玐}���ق́A��Îs�ƍ�������O�Ɂu���ꌧ�����U����v�̈�Ƃ��Č��Ă�ꂽ�B��ǎR�n��]�ސ}���قŗL�����B���ƁA���̍����炩�c�o�����������o���āA�c�o��������}���قƂ��Ȃ����B
�@�����B���̃X�e�[�V�����u�،ˏ��w�Z�v���B�l�̏Z��ł���a玐}���ق́A��Îs�ƍ�������O�Ɂu���ꌧ�����U����v�̈�Ƃ��Č��Ă�ꂽ�B��ǎR�n��]�ސ}���قŗL�����B���ƁA���̍����炩�c�o�����������o���āA�c�o��������}���قƂ��Ȃ����B �@�l�̖��O�́u�~�b�P���v�B�{���́A������ƒ����āu��Îs���a玈ړ��}���ك~�b�P�����v�ƌ����B�����͘a玐}���ق̑q�ɂɂ��邯�ǁA�u�T�̐��j���ߌ�ɊO�ɔ�яo���B�l�̂����ɖ�Q�O�O�O���̖{�����đ���B
�@�l�̖��O�́u�~�b�P���v�B�{���́A������ƒ����āu��Îs���a玈ړ��}���ك~�b�P�����v�ƌ����B�����͘a玐}���ق̑q�ɂɂ��邯�ǁA�u�T�̐��j���ߌ�ɊO�ɔ�яo���B�l�̂����ɖ�Q�O�O�O���̖{�����đ���B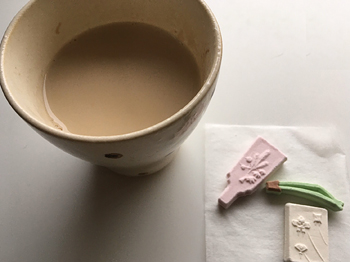 �@���͌ܖ؊��V����̏����͓ǂL�����Ȃ��B���A�u�S������v�ɏ����ꂽ����̂����ɂ��Ă̕��͓͂ǂ��Ƃ͂���B�܂��ANHK�̃��W�I�[��ւł̌����ǃA�i�E���T�[�̐{�����Í]����Ƃ̐l���Ɖ̂Ƃ��e�[�}�ɂ����Βk�ԑg�͍D���ł悭�����Ă����B
�@���͌ܖ؊��V����̏����͓ǂL�����Ȃ��B���A�u�S������v�ɏ����ꂽ����̂����ɂ��Ă̕��͓͂ǂ��Ƃ͂���B�܂��ANHK�̃��W�I�[��ւł̌����ǃA�i�E���T�[�̐{�����Í]����Ƃ̐l���Ɖ̂Ƃ��e�[�}�ɂ����Βk�ԑg�͍D���ł悭�����Ă����B �@2020�N4��11����NHK�̔ԑg�u�u���^�����v�̃e�[�}�͖@�����ł������B�@�����ƌ����u�������q�v�������Ɏv���o�����B�ԑg�߂Ȃ���A���ēǂu�������q�͂��Ȃ������v�i�V���I���A�J��i��j���v���o���Ă����B
�@2020�N4��11����NHK�̔ԑg�u�u���^�����v�̃e�[�}�͖@�����ł������B�@�����ƌ����u�������q�v�������Ɏv���o�����B�ԑg�߂Ȃ���A���ēǂu�������q�͂��Ȃ������v�i�V���I���A�J��i��j���v���o���Ă����B �@�e���r��ʂŁu�r���⊶�ɑ����܂��v�ƌ������t�ƂƂ��ɓ���������l�����ʂ��Ă���̂�����ƁA���̐l���͂��l�т����Ă���̂��A����Ƃ��v���ʂ�ɂȂ炸�c�O�ȋC�����������Ă���̂��A��̔�������߂ċC�ɂȂ�B
�@�e���r��ʂŁu�r���⊶�ɑ����܂��v�ƌ������t�ƂƂ��ɓ���������l�����ʂ��Ă���̂�����ƁA���̐l���͂��l�т����Ă���̂��A����Ƃ��v���ʂ�ɂȂ炸�c�O�ȋC�����������Ă���̂��A��̔�������߂ċC�ɂȂ�B �@�ꎞ���A���̃v���ł͂Ȃ��A�}�`���A�A������җ���߂����l�����������C�O�l���s�̖{���y�����ǂ��Ƃ�����B�l�ōs���C�O�̗��ɂ��Čv��i�K�ł��낢�뎎�s���낷��ߒ��⌻���̗��ł̂��ꂱ��A�X�ɂ͂��ꂼ��̐l���o�����瓾��ꂽ�m����l���������肰�Ȃ���I�����̂������[���ǂ��̂ł���B
�@�ꎞ���A���̃v���ł͂Ȃ��A�}�`���A�A������җ���߂����l�����������C�O�l���s�̖{���y�����ǂ��Ƃ�����B�l�ōs���C�O�̗��ɂ��Čv��i�K�ł��낢�뎎�s���낷��ߒ��⌻���̗��ł̂��ꂱ��A�X�ɂ͂��ꂼ��̐l���o�����瓾��ꂽ�m����l���������肰�Ȃ���I�����̂������[���ǂ��̂ł���B �@�ŋ߂ł͂��܂茩�����Ȃ��Ȃ������A���Ă͂��낢��ȏo�ŎЂ���V���[�Y���̐��E���w�S�W���悭�o�ł���Ă����B����ނ̑S�W���������̂��A���ꂪ�S�����ƕۏ͂ł��Ȃ����A������ƒ��ׂ��Ƃ���1960�N�ォ�猻�݂Ɏ���܂�14��ނ̐��E���w�S�W���o�ł���Ă���B���E���w�S�W�Ƃ͖������Ă��Ȃ�������81���́u���E�̖����v������B
�@�ŋ߂ł͂��܂茩�����Ȃ��Ȃ������A���Ă͂��낢��ȏo�ŎЂ���V���[�Y���̐��E���w�S�W���悭�o�ł���Ă����B����ނ̑S�W���������̂��A���ꂪ�S�����ƕۏ͂ł��Ȃ����A������ƒ��ׂ��Ƃ���1960�N�ォ�猻�݂Ɏ���܂�14��ނ̐��E���w�S�W���o�ł���Ă���B���E���w�S�W�Ƃ͖������Ă��Ȃ�������81���́u���E�̖����v������B �u�p���ōł��L���ȁA�������̐l���O�l�́H�v�ƕ����ꂽ�Ƃ��A���Ȃ��͂ǂ��������ɂȂ邾�낤���B�n�����b�g�͂����ɓ��ɕ����Ԃ��A��̓�l�͂��āH
�u�p���ōł��L���ȁA�������̐l���O�l�́H�v�ƕ����ꂽ�Ƃ��A���Ȃ��͂ǂ��������ɂȂ邾�낤���B�n�����b�g�͂����ɓ��ɕ����Ԃ��A��̓�l�͂��āH �@�L�����͐}�^�ɂ��āu�G�E�}�Ȃǂ���̂Ƃ��ĕҏW���������v�Ɛ������Ă���B���ꂩ�珑�����Ƃ��Ă��镶�͂́A���p�ق┎���ق̃~���[�W�A���E�V���b�v�Ŕ����Ă���W����̐}�^�ɂ��Ăł���B
�@�L�����͐}�^�ɂ��āu�G�E�}�Ȃǂ���̂Ƃ��ĕҏW���������v�Ɛ������Ă���B���ꂩ�珑�����Ƃ��Ă��镶�͂́A���p�ق┎���ق̃~���[�W�A���E�V���b�v�Ŕ����Ă���W����̐}�^�ɂ��Ăł���B �@�Ƃ���������Ղ��ďo�錾�t������B�N���̎��ɂ��������ܒ��̕��͂Łu���l�X�ƈՐ��́A�������i�قƂ�j�ɘȂ݂āA�߂����̂ӑs�m����v�A�����čŌ�̕��́u���l�X�ƈՐ��ɁA�ԎU��t�͗���ǂ��A�s�m�ӂ����ъ҂藈���v�ł���B
�@�Ƃ���������Ղ��ďo�錾�t������B�N���̎��ɂ��������ܒ��̕��͂Łu���l�X�ƈՐ��́A�������i�قƂ�j�ɘȂ݂āA�߂����̂ӑs�m����v�A�����čŌ�̕��́u���l�X�ƈՐ��ɁA�ԎU��t�͗���ǂ��A�s�m�ӂ����ъ҂藈���v�ł���B �@�O�����̎�ɂȂ�啔�̎O����u�v���n�̏t�v�u�x�������̏H�v�u�E�B�[���̓~�v�i�t�]���A��������W�p�Ёj������B�Ȃ��ł����`�F�R�X���o�L�A��g�ٍΒ��Ɏ����ɑ������A�\�A�R�N�U�̑����œd�����Ƃ������҂̌o�������Ƃɏ�����Ă���u�v���n�̏t�v�����|�I�ɖʔ����B
�@�O�����̎�ɂȂ�啔�̎O����u�v���n�̏t�v�u�x�������̏H�v�u�E�B�[���̓~�v�i�t�]���A��������W�p�Ёj������B�Ȃ��ł����`�F�R�X���o�L�A��g�ٍΒ��Ɏ����ɑ������A�\�A�R�N�U�̑����œd�����Ƃ������҂̌o�������Ƃɏ�����Ă���u�v���n�̏t�v�����|�I�ɖʔ����B �@���{��ł́g�@����́h�Ƃ����̂��낤���A�G���^�[�e�C�������g�Ƃ��čٔ���i�@���x�A�ٌ�m�̊����E�����Ƃ����i���삪����B���������{�̍�Ƃ������̕���̍�i�𑽂������A�f���炵����i������B�����A�\���́A�\�z�͂Ƃ����_�ł͎c�O�Ȃ���A�����J�̍�Ƃɕ����Ă���悤�Ɋ����Ă���B���̌��ʂƂ��ăA�����J�̍�Ƃ̍�i�ɂ͑�삪�����A���𐘂��ēǂދC�͂��K�v�ƂȂ�B
�@���{��ł́g�@����́h�Ƃ����̂��낤���A�G���^�[�e�C�������g�Ƃ��čٔ���i�@���x�A�ٌ�m�̊����E�����Ƃ����i���삪����B���������{�̍�Ƃ������̕���̍�i�𑽂������A�f���炵����i������B�����A�\���́A�\�z�͂Ƃ����_�ł͎c�O�Ȃ���A�����J�̍�Ƃɕ����Ă���悤�Ɋ����Ă���B���̌��ʂƂ��ăA�����J�̍�Ƃ̍�i�ɂ͑�삪�����A���𐘂��ēǂދC�͂��K�v�ƂȂ�B �@�V�^�R���i�E�C���X�����\�h�̂���2020�N2�����{�ȍ~�A������ʋ@�ւɏ���Ă��Ȃ��B�F�l���̃��[���ɏ�k�Ɂu�d�Ԃ̏�����Y��Ă��܂����v�Ə������قǂł���B�O�o����̂́A�����̗[���P���Ԃ̃E�I�[�L���O�ƌ��ɂP��̈�Ғʂ������ƂȂ����B
�@�V�^�R���i�E�C���X�����\�h�̂���2020�N2�����{�ȍ~�A������ʋ@�ւɏ���Ă��Ȃ��B�F�l���̃��[���ɏ�k�Ɂu�d�Ԃ̏�����Y��Ă��܂����v�Ə������قǂł���B�O�o����̂́A�����̗[���P���Ԃ̃E�I�[�L���O�ƌ��ɂP��̈�Ғʂ������ƂȂ����B �@����[���G���́A�o�����p�ُ����̍���G���ł���B���ق̃z�[���y�[�W�ɂ��Ɓu���8�N�i866�N�j�[3��10���ɋN�������V��̉�����߂����[���E���P�j�̉A�d�A���̘I���Ǝ��r�̕�����A���������ƕ`�����G���ł��B(�ȉ���)�v�Ƃ���B���͂��̊G���𑼂̎����i�ƂƂ��ɏo�����p�قŌ����͂������A�G���ɂ��Ă��܂�S������Ă��Ȃ��������ׂ������o���Ă��Ȃ��B
�@����[���G���́A�o�����p�ُ����̍���G���ł���B���ق̃z�[���y�[�W�ɂ��Ɓu���8�N�i866�N�j�[3��10���ɋN�������V��̉�����߂����[���E���P�j�̉A�d�A���̘I���Ǝ��r�̕�����A���������ƕ`�����G���ł��B(�ȉ���)�v�Ƃ���B���͂��̊G���𑼂̎����i�ƂƂ��ɏo�����p�قŌ����͂������A�G���ɂ��Ă��܂�S������Ă��Ȃ��������ׂ������o���Ă��Ȃ��B �@CNN�����̓����ʖ�t��ʂŃA�����J�哝�̑I���߂Ă����B50�B���ԂƐɓh�蕪������̂����A�e�B�̈ʒu�W�₻�ꂼ��̓����ɂ��Ă��܂�ɂ����R����m���A�u�����炸�Ƃ����ǂ������炸�v���x�̔F�������L���Ă��Ȃ��̂ɉ��߂ċC���t�����B
�@CNN�����̓����ʖ�t��ʂŃA�����J�哝�̑I���߂Ă����B50�B���ԂƐɓh�蕪������̂����A�e�B�̈ʒu�W�₻�ꂼ��̓����ɂ��Ă��܂�ɂ����R����m���A�u�����炸�Ƃ����ǂ������炸�v���x�̔F�������L���Ă��Ȃ��̂ɉ��߂ċC���t�����B �@���́A�Ⴂ�����猾�t�╶�͂ɋ����S������Ă����悤���B���ɂɂ͏��a�R�T�N���s�̕��c�P�����u���̚��ꋳ���v���n�߂Ƃ��āu���͓ǖ{�v�Ƒ肳�ꂽ��[�N���A�J�菁��Y�A�O���R�I�v�A�ےJ�ˈ�A���Ђ������̏���������ł���B�ےJ�ˈ�́u���{��̂��߂Ɂv�u��������Ȃ�����{��v��n�ӏ���́u���{��̂�����v������B�S�Ăɖڂ�ʂ����͂������A�o���Ă��邱�Ƃ͏��Ȃ��B�Ƃ������قƂ�NjL�����Ă��Ȃ��B
�@���́A�Ⴂ�����猾�t�╶�͂ɋ����S������Ă����悤���B���ɂɂ͏��a�R�T�N���s�̕��c�P�����u���̚��ꋳ���v���n�߂Ƃ��āu���͓ǖ{�v�Ƒ肳�ꂽ��[�N���A�J�菁��Y�A�O���R�I�v�A�ےJ�ˈ�A���Ђ������̏���������ł���B�ےJ�ˈ�́u���{��̂��߂Ɂv�u��������Ȃ�����{��v��n�ӏ���́u���{��̂�����v������B�S�Ăɖڂ�ʂ����͂������A�o���Ă��邱�Ƃ͏��Ȃ��B�Ƃ������قƂ�NjL�����Ă��Ȃ��B �@�m���\���N�O���Ǝv�����ANHK�e���r�Ŗ��{���p�قƂ����ԑg�����f����Ă����B�L�����m���߂邽�߂ɃE�B�L�y�f�B�A���`�F�b�N�����Ƃ���A�u�G��̒��ɕ`���ꂽ�l�X�ȃG�s�\�[�h����ɁA���̊G��ɕ`���ꂽ�l�X�Ȕ閧�����N�C�Y�`���ʼn����������Ă������̂ŁA�G��ӏ��S�҂ł��y���߂�悤�ȓ��e�ł���v�Ƃ������B�m���ɏ㎿�̃N�C�Y�ԑg�̎���������B
�@�m���\���N�O���Ǝv�����ANHK�e���r�Ŗ��{���p�قƂ����ԑg�����f����Ă����B�L�����m���߂邽�߂ɃE�B�L�y�f�B�A���`�F�b�N�����Ƃ���A�u�G��̒��ɕ`���ꂽ�l�X�ȃG�s�\�[�h����ɁA���̊G��ɕ`���ꂽ�l�X�Ȕ閧�����N�C�Y�`���ʼn����������Ă������̂ŁA�G��ӏ��S�҂ł��y���߂�悤�ȓ��e�ł���v�Ƃ������B�m���ɏ㎿�̃N�C�Y�ԑg�̎���������B �@���{��Ƃł��蕶���M�͎�͂̓��R�@����ƌ������̑�\��̈�u���v���v�������ׂ�l���������낤���A���́u�N���v�Ɓu������e����lj�v�ł���B
�@���{��Ƃł��蕶���M�͎�͂̓��R�@����ƌ������̑�\��̈�u���v���v�������ׂ�l���������낤���A���́u�N���v�Ɓu������e����lj�v�ł���B �@���ɂ����Ă������Ԍ��C���́u�����Օ����v�i�W��V�Ёj���ڂɕt�����B���������ɍ�Ƃ��~�߂Ď�Ɏ��A���ւɎ������B�T�����[�}�����������߂ĊԂ��Ȃ��̍��ɁA�w����������������v�����������̂ł���B���������X���o���Ă���B
�@���ɂ����Ă������Ԍ��C���́u�����Օ����v�i�W��V�Ёj���ڂɕt�����B���������ɍ�Ƃ��~�߂Ď�Ɏ��A���ւɎ������B�T�����[�}�����������߂ĊԂ��Ȃ��̍��ɁA�w����������������v�����������̂ł���B���������X���o���Ă���B �@���J���I����́u�C���h���s�L1�v�i���~�ɕ��Ɂj��ǂB�s���}���ق́u�{���ԋp���ꂽ�{�v���ꎞ�ۊǂ���I�̋��ɒu����Ă����̂���o�������̂ł���B���́A���D�Ƃ��Ă̒��J����ɂ��Ă͂قƂ�ǒm��Ȃ����A�C���h�𗷍s��Ƃ��Đ^�ʖڂɍl�������Ƃ��Ȃ��B�^�[�W�}�n����ɕ����ԋ{�a�z�e���ɂ͎�̊S������Ă��邪�A���̒i�K�Ŏ~�܂��Ă���B
�@���J���I����́u�C���h���s�L1�v�i���~�ɕ��Ɂj��ǂB�s���}���ق́u�{���ԋp���ꂽ�{�v���ꎞ�ۊǂ���I�̋��ɒu����Ă����̂���o�������̂ł���B���́A���D�Ƃ��Ă̒��J����ɂ��Ă͂قƂ�ǒm��Ȃ����A�C���h�𗷍s��Ƃ��Đ^�ʖڂɍl�������Ƃ��Ȃ��B�^�[�W�}�n����ɕ����ԋ{�a�z�e���ɂ͎�̊S������Ă��邪�A���̒i�K�Ŏ~�܂��Ă���B �@���͈��v�I�Ƃ����l�����悭�m��Ȃ��B�쎌�Ƃł���A���U�ɍ쎌�����Ȃ�5,000�ȏ゠��A�Ƃ������Ƃ������ނɂ��Ă̒m���ł���B�����m���Ă���ނ̎��͐l�̐S��ł�����A�l�����l����������A�E�C�Â���ꂽ��A���t�̑I���������Ȃ��̂������B
�@���͈��v�I�Ƃ����l�����悭�m��Ȃ��B�쎌�Ƃł���A���U�ɍ쎌�����Ȃ�5,000�ȏ゠��A�Ƃ������Ƃ������ނɂ��Ă̒m���ł���B�����m���Ă���ނ̎��͐l�̐S��ł�����A�l�����l����������A�E�C�Â���ꂽ��A���t�̑I���������Ȃ��̂������B �@���̓|�[�����h�ɂ��ĉ���m���Ă���̂��낤�B�|�[�����h�Ƃ������t���玄�������Ɏv�������ׂ�̂́A�����V�������@�\�A�A�E�V���r�b�c�i�I�V�t�B�G���`���j�A�����T�ψ����Ɓg�A�сh���x�ł���B���Ƃ̓V���p���ƃL�����[�v�l�ƃR�y���j�N�X�B����Ɉꎞ���D���������Y�u���b�J�i�̃o�C�\���O���X��Ђ����E�I�b�J�j�ł���B���������A��X��̃��[�}�@�����n�l�E�p�E��2���ƃf�N�G�A�������A�����������|�[�����h�o�g�������B�m���Ă��邱�Ƃ͂��܂�ɂ����Ȃ��B
�@���̓|�[�����h�ɂ��ĉ���m���Ă���̂��낤�B�|�[�����h�Ƃ������t���玄�������Ɏv�������ׂ�̂́A�����V�������@�\�A�A�E�V���r�b�c�i�I�V�t�B�G���`���j�A�����T�ψ����Ɓg�A�сh���x�ł���B���Ƃ̓V���p���ƃL�����[�v�l�ƃR�y���j�N�X�B����Ɉꎞ���D���������Y�u���b�J�i�̃o�C�\���O���X��Ђ����E�I�b�J�j�ł���B���������A��X��̃��[�}�@�����n�l�E�p�E��2���ƃf�N�G�A�������A�����������|�[�����h�o�g�������B�m���Ă��邱�Ƃ͂��܂�ɂ����Ȃ��B �@���쎵������ƌ����ΑS15���i�V�����ɂł͑S43���j�́u���[�}�l�̕���v�ł���B���̉��삳��Ɂg���j�T�X�y���X�E���}���h�Ƃ��̂��ׂ��R���̒���������B�u��F�̃��F�l�c�B�A ���}���R�E�l�����v�u��F�̃t�B�����c�F ���f�B�`�ƎE�l�����v�u�����̃��[�} �@�����E�l�����v�i������������V���Ёj�̎O���삪����ł���B
�@���쎵������ƌ����ΑS15���i�V�����ɂł͑S43���j�́u���[�}�l�̕���v�ł���B���̉��삳��Ɂg���j�T�X�y���X�E���}���h�Ƃ��̂��ׂ��R���̒���������B�u��F�̃��F�l�c�B�A ���}���R�E�l�����v�u��F�̃t�B�����c�F ���f�B�`�ƎE�l�����v�u�����̃��[�} �@�����E�l�����v�i������������V���Ёj�̎O���삪����ł���B �@���ꎫ�T�́u�I�ѕ��v�ł͂Ȃ��u�V�ѕ��v�ł���B�u�w�Z�ł͋����Ă���Ȃ��I�v�Ƃ̕��肪�t���ꂽ�T���L���[�^�c�I���̂��̖{�́A�ӂƂ������ƂŎ��̒m��Ƃ���ƂȂ����B
�@���ꎫ�T�́u�I�ѕ��v�ł͂Ȃ��u�V�ѕ��v�ł���B�u�w�Z�ł͋����Ă���Ȃ��I�v�Ƃ̕��肪�t���ꂽ�T���L���[�^�c�I���̂��̖{�́A�ӂƂ������ƂŎ��̒m��Ƃ���ƂȂ����B �@���Ắu�f�ǁv�Ƃ������t���悭�g���Ă����悤�����A���݂ł͎���ɂȂ����̂��낤���B���̗c�t���ŗ�����m��̎����Ï�����Ƃ�����������Ă��邱�Ƃ���V���L�����o���Ă��邪�A���݂ł��s���Ă���̂��낤���B
�@���Ắu�f�ǁv�Ƃ������t���悭�g���Ă����悤�����A���݂ł͎���ɂȂ����̂��낤���B���̗c�t���ŗ�����m��̎����Ï�����Ƃ�����������Ă��邱�Ƃ���V���L�����o���Ă��邪�A���݂ł��s���Ă���̂��낤���B �@��370��̖�̉Ԃ��Љ��Ă���u��̉Ԃ���ې}�Ӂv�i���J��N�Y�A�z�n���فj�́u�܂������v�ɂ́A�u�ق�2�T�Ԃ��ƂɈڂ�ς����{�̋G�߂̕ω���ǂ��āA�g�߂Ɍ�����A����t��Ԃ����łȂ��c����Ԃ̒f�ʁA���Ȃǂ��܂߂ďЉ�܂����v�Ƃ���B�g����Ў�ɁA�ǂ�ŁA���߂Ď��Ɋy�����}�ӂł���B
�@��370��̖�̉Ԃ��Љ��Ă���u��̉Ԃ���ې}�Ӂv�i���J��N�Y�A�z�n���فj�́u�܂������v�ɂ́A�u�ق�2�T�Ԃ��ƂɈڂ�ς����{�̋G�߂̕ω���ǂ��āA�g�߂Ɍ�����A����t��Ԃ����łȂ��c����Ԃ̒f�ʁA���Ȃǂ��܂߂ďЉ�܂����v�Ƃ���B�g����Ў�ɁA�ǂ�ŁA���߂Ď��Ɋy�����}�ӂł���B �@��Îs���}���قɂ͂��̎��Ƃ̈�Ƃ��āu�}���ً��c��v���ݒu����Ă���B����́A�O�z�s���̂��Ƃ� ����24�N8��23���ɐݒu���ꂽ�B
�@��Îs���}���قɂ͂��̎��Ƃ̈�Ƃ��āu�}���ً��c��v���ݒu����Ă���B����́A�O�z�s���̂��Ƃ� ����24�N8��23���ɐݒu���ꂽ�B �@���{�ɂ�����t�����X���w�E�����̌����ҁA�]�_�Ƃł���A���s��w�l���Ȋw�����������߁A�����M�͂�W�I���h�k�[���M�͂���͂��ꂽ�K�����v����i���邢�͂��̈⑰����j���s�s�Ɋ��ꂽ�������A�ۊǏꏊ��]�X�Ƃ�����A�p�����ꂽ���Ƃ��������A���ɂȂ������Ƃ�����B
�@���{�ɂ�����t�����X���w�E�����̌����ҁA�]�_�Ƃł���A���s��w�l���Ȋw�����������߁A�����M�͂�W�I���h�k�[���M�͂���͂��ꂽ�K�����v����i���邢�͂��̈⑰����j���s�s�Ɋ��ꂽ�������A�ۊǏꏊ��]�X�Ƃ�����A�p�����ꂽ���Ƃ��������A���ɂȂ������Ƃ�����B �@�O�R����Â����S���Ȃ�ɂȂ����B96�������B2020�N8��7���̒����e���́u�w�v�l�̐����w�x���x�X�g�Z���[�ɂȂ����p���w�҂ł����̐����q�喼�_�����̊O�R����Ái�Ƃ�܁E�����Ђ��j����7��30���A�_�ǂ���Ŏ����v�ƕ��B�����āu90�Α�ɂȂ��Ă������Ɏ��M���d�ˁA�V�����n�ǂ��Đ��̒��̏���ȂǁA�m�I�D��S������Ȃ��������ł����ڂ��W�߂��v�Ƃ��B�ނ�ł����������F�肷��B
�@�O�R����Â����S���Ȃ�ɂȂ����B96�������B2020�N8��7���̒����e���́u�w�v�l�̐����w�x���x�X�g�Z���[�ɂȂ����p���w�҂ł����̐����q�喼�_�����̊O�R����Ái�Ƃ�܁E�����Ђ��j����7��30���A�_�ǂ���Ŏ����v�ƕ��B�����āu90�Α�ɂȂ��Ă������Ɏ��M���d�ˁA�V�����n�ǂ��Đ��̒��̏���ȂǁA�m�I�D��S������Ȃ��������ł����ڂ��W�߂��v�Ƃ��B�ނ�ł����������F�肷��B �@����́u�{�Ƃ킽���v�ł͂Ȃ��A�{���\�����Ă��镶���Ɋւ��u�H��̕����v�Ƒ肵�čŋߊ����Ă��邱�Ƃ������B
�@����́u�{�Ƃ킽���v�ł͂Ȃ��A�{���\�����Ă��镶���Ɋւ��u�H��̕����v�Ƒ肵�čŋߊ����Ă��邱�Ƃ������B �@�قƂ�ǂ̕��́u�G�F�i�s�F�����[�j�v�ƕ����āu�ȂɁH�v�Ǝv���邾�낤�B���́A�����͓����u�͓��̑Βk������ׂ��H�ׂ�v�ɂ���B
�@�قƂ�ǂ̕��́u�G�F�i�s�F�����[�j�v�ƕ����āu�ȂɁH�v�Ǝv���邾�낤�B���́A�����͓����u�͓��̑Βk������ׂ��H�ׂ�v�ɂ���B �@�E�l�Ƃ������t�͎���ɂȂ����̂��낤���B�ŋ߂��̌��t�������Ƃ��Ȃ��B�������A�E�l�̋Z�p�͎��B�̒m��Ȃ��Ƃ���œ`������Ă���ɈႢ�Ȃ��B���s���������قł̊G��W�ϗ��̌�A���s�}�o�ق��ē��t���Ō��w���Ă��̂悤�Ɏv�����B
�@�E�l�Ƃ������t�͎���ɂȂ����̂��낤���B�ŋ߂��̌��t�������Ƃ��Ȃ��B�������A�E�l�̋Z�p�͎��B�̒m��Ȃ��Ƃ���œ`������Ă���ɈႢ�Ȃ��B���s���������قł̊G��W�ϗ��̌�A���s�}�o�ق��ē��t���Ō��w���Ă��̂悤�Ɏv�����B �@�ǂȂ����������낤���B�G�b�Z�C�̒��Łu�{�ƁZ�Z�͐l�ɑ݂��ׂ��ł͂Ȃ��v�Ə����ꂽ�̂́B���������������̂��͊o���Ă��Ȃ��B
�@�ǂȂ����������낤���B�G�b�Z�C�̒��Łu�{�ƁZ�Z�͐l�ɑ݂��ׂ��ł͂Ȃ��v�Ə����ꂽ�̂́B���������������̂��͊o���Ă��Ȃ��B �@���ɂŏ������ׂ��{��I�яo���Ă����Ƃ��A���������V���̘_���劲���������R�K�Y���̒����u�C���[�W�E�A�b�v�@���ۊ��o����Ă邽�߂Ɂv�i1989�N�A�����V���Д��s�j�ɋC���t�����B�p���p���ƃy�[�W���߂����Ă���ƌu���y���̃T�C�h���C����������Ă�������������B���̌o�߂ƂƂ��ɔ����Ȃ��Ă��邻�̃T�C�h���C�����A�u�����͂��̂悤�ȋL�q�Ɋ��S�����̂��v�u���ꂪ�Ⴉ�肵���ɐS�ɗ��߂����̌����������̂��v�u�l�����̈�̃q���g�Ƃ����̂��낤���v�ȂǂƉ����������߂��B
�@���ɂŏ������ׂ��{��I�яo���Ă����Ƃ��A���������V���̘_���劲���������R�K�Y���̒����u�C���[�W�E�A�b�v�@���ۊ��o����Ă邽�߂Ɂv�i1989�N�A�����V���Д��s�j�ɋC���t�����B�p���p���ƃy�[�W���߂����Ă���ƌu���y���̃T�C�h���C����������Ă�������������B���̌o�߂ƂƂ��ɔ����Ȃ��Ă��邻�̃T�C�h���C�����A�u�����͂��̂悤�ȋL�q�Ɋ��S�����̂��v�u���ꂪ�Ⴉ�肵���ɐS�ɗ��߂����̌����������̂��v�u�l�����̈�̃q���g�Ƃ����̂��낤���v�ȂǂƉ����������߂��B �@�\���ɂ͂��ǂ남�ǂ낵���t�B���E�C���X�i���Ǝv���j�̓d�q�������ʐ^�������f�ڂ���Ă���u�z�b�g�E�]�[���v�i��E���j�i���`���[�h�E�v���X�g�����A���� �_��A�V�Ёj��ǂB�����ɂ���z�b�g�E�]�[���Ƃ́u�i�����ǂ̗��s�n��픚�n�Ȃǂ́j�g�̂Ɉ��e�����y�ڂ����̂ƐڐG����댯�����������v���Ӗ����錾�t�ł���B
�@�\���ɂ͂��ǂ남�ǂ낵���t�B���E�C���X�i���Ǝv���j�̓d�q�������ʐ^�������f�ڂ���Ă���u�z�b�g�E�]�[���v�i��E���j�i���`���[�h�E�v���X�g�����A���� �_��A�V�Ёj��ǂB�����ɂ���z�b�g�E�]�[���Ƃ́u�i�����ǂ̗��s�n��픚�n�Ȃǂ́j�g�̂Ɉ��e�����y�ڂ����̂ƐڐG����댯�����������v���Ӗ����錾�t�ł���B �@���@�����̖��ւ��Ԃ߂邽�߂ɁA���ēǂݖʔ����������Ƃ������L�����Ă����F���̖{2�����ēǂ����B���ی����s�i�u�k�Ёj�Ƌ`�o���E�^(�u�k��)�ł���B
�@���@�����̖��ւ��Ԃ߂邽�߂ɁA���ēǂݖʔ����������Ƃ������L�����Ă����F���̖{2�����ēǂ����B���ی����s�i�u�k�Ёj�Ƌ`�o���E�^(�u�k��)�ł���B �@���邭�Ȃ��P������ׂ������ӂ͂Ȃ��B�����������肸���ƎႢ���ɒm������i�Ɏg���Ă��錾�t�ł���B
�@���邭�Ȃ��P������ׂ������ӂ͂Ȃ��B�����������肸���ƎႢ���ɒm������i�Ɏg���Ă��錾�t�ł���B �@���n�l�X�E�t�F�����[���̖��O��m�����̂́A������40���N�O�ł���B���^�[�o���������A�^��̎���������������̔��g����`���������悪��y�̉Ƃ̉��ڊԂɏ����Ă����B
�@���n�l�X�E�t�F�����[���̖��O��m�����̂́A������40���N�O�ł���B���^�[�o���������A�^��̎���������������̔��g����`���������悪��y�̉Ƃ̉��ڊԂɏ����Ă����B �@�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����䂪���ő����n�߂����A50�N�߂��O�ɂȂ�1972�N10���ɔ������ꂽ���������̂��̖{��m��A�}���Ŏs���}���ق̑������������A�\�����ꂽ�B�}���͑ݏo���ŗ\��ԍ���1�Ԃ��������A�قǂȂ��}���ق͕قƂȂ����B�ً}���Ԑ錾���������ꂽ������ɓ��肵�A�u孋���v�̐����ł��邱�Ƃ��������œǂݏI�����B
�@�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����䂪���ő����n�߂����A50�N�߂��O�ɂȂ�1972�N10���ɔ������ꂽ���������̂��̖{��m��A�}���Ŏs���}���ق̑������������A�\�����ꂽ�B�}���͑ݏo���ŗ\��ԍ���1�Ԃ��������A�قǂȂ��}���ق͕قƂȂ����B�ً}���Ԑ錾���������ꂽ������ɓ��肵�A�u孋���v�̐����ł��邱�Ƃ��������œǂݏI�����B �u�H�n�v�Ƃ͉������������̌��t�ł���B�Ƃ͌����Ă������g�͗c�����ɘH�n�ŗV�Ƃ����L���͂Ȃ��B
�u�H�n�v�Ƃ͉������������̌��t�ł���B�Ƃ͌����Ă������g�͗c�����ɘH�n�ŗV�Ƃ����L���͂Ȃ��B �u�����q�ɂ͗���������v�Ƃ������t�́u���ɂ���Đ��̒��̐h����ꂵ�݂��o�����邱�Ƃɂ��l�Ƃ��Ă̐��������҂����v���Ƃ��Ӗ����Ă���B�������̈ړ���u�n�̏��邱�Ƃ��ɂ߂č����������ɂ͂��̌��t�͐^���ł���A�����̐l�̋��������t���������낤�B
�u�����q�ɂ͗���������v�Ƃ������t�́u���ɂ���Đ��̒��̐h����ꂵ�݂��o�����邱�Ƃɂ��l�Ƃ��Ă̐��������҂����v���Ƃ��Ӗ����Ă���B�������̈ړ���u�n�̏��邱�Ƃ��ɂ߂č����������ɂ͂��̌��t�͐^���ł���A�����̐l�̋��������t���������낤�B �@��w�ʐ^��OB���Ԃ̃��[�����O�E���X�g�Ɂu�w�K�̉ԁx�A���A�䂪�L�z��ɍ炢�Ă��܂��B�ƂĂ��ǂ����肪���܂��B���̐�Ɂw������܂�x������܂��B������́A���^�{�Z���ȌO��B����̑唫�ł́A����A�w�N�`�i�V�x�̍ŏ��̉Ԃ��炫�܂����B������͔Z���ȓ��������܂��ˁB�݂�ȁA�����Ԃł��v�]�X�Ƃ������[�����f�ڂ��ꂽ�B
�@��w�ʐ^��OB���Ԃ̃��[�����O�E���X�g�Ɂu�w�K�̉ԁx�A���A�䂪�L�z��ɍ炢�Ă��܂��B�ƂĂ��ǂ����肪���܂��B���̐�Ɂw������܂�x������܂��B������́A���^�{�Z���ȌO��B����̑唫�ł́A����A�w�N�`�i�V�x�̍ŏ��̉Ԃ��炫�܂����B������͔Z���ȓ��������܂��ˁB�݂�ȁA�����Ԃł��v�]�X�Ƃ������[�����f�ڂ��ꂽ�B �@���肪�u�����̍\���Ɛl�ނ̍K���v�Ƃ���u�T�s�G���X�S�j�v�㉺�Q���i�͏o���[�V�ЁA�����@���E�m�A�E�n�������A�ēc�T�V��j�́A���̂悤�Ȃ������Ŏ����m�邱�ƂƂȂ����B�n�������̓C�X���G���l�Ńw�u���C��w�ŗ��j�w�������Ă���B
�@���肪�u�����̍\���Ɛl�ނ̍K���v�Ƃ���u�T�s�G���X�S�j�v�㉺�Q���i�͏o���[�V�ЁA�����@���E�m�A�E�n�������A�ēc�T�V��j�́A���̂悤�Ȃ������Ŏ����m�邱�ƂƂȂ����B�n�������̓C�X���G���l�Ńw�u���C��w�ŗ��j�w�������Ă���B �p�i�����j�ꂽ�鉀�ɓ��ݓ���
�p�i�����j�ꂽ�鉀�ɓ��ݓ���|
���̂P |
�^���|�|�̉Ԃ��Ԃт炪��������傫�ȉԂƎv���Ă���l�́A��200���i�Z�C���E�^���|�|�j���邢�͖�100���i�J���T�C�^���|�|�A�J���g�E�^���|�|�j�Ɠ�����B |
|
���̂Q |
�^���|�|�̉Ԃ͏����ȉԂ��W�܂��ďo���Ă��邱�Ƃ�m���Ă���A�Ԃт�̈ꖇ�ꖇ����̏����ȉԂ̉Ԃт炾�ƒm���Ă���l�́A�Ԃт�̐��͂P�����Ɠ�����B |
|
���̂R |
����ɂ��̂P���̏����ȉԂт�́A����̉Ԃт炪�������ĂP���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�m���Ă���l�́A�Ԃт�̐��͂T���ł���A�Ɠ����邾�낤�ƁB |
 �@2019�N1��14���A�S�Ẵ}�X�R�~�́A�u�Ǝ��̌Ñ�j�_�ȂǂŒm��ꕝ�L������Ŕ����A���M�����𑱂����N�w�҂ŕ����M�͎�͎҂̔~���ҁi���߂͂�E�������j����12���ߌ�4��35���A�x���̂��ߋ��s�s���̎���Ŏ��������B93�������v�Ƒ傫�����B
�@2019�N1��14���A�S�Ẵ}�X�R�~�́A�u�Ǝ��̌Ñ�j�_�ȂǂŒm��ꕝ�L������Ŕ����A���M�����𑱂����N�w�҂ŕ����M�͎�͎҂̔~���ҁi���߂͂�E�������j����12���ߌ�4��35���A�x���̂��ߋ��s�s���̎���Ŏ��������B93�������v�Ƒ傫�����B �@���I�ɂ͎ʐ^�����S�̊O���̊ό��n�Ŕ������{��20��������ł���B�������ȓ��{��̖{�����邪�����ǂ߂Ȃ����̍��̌��t�ŏ����ꂽ�{������B�����̖{�͎ʐ^�B�e���֎~����Ă���ꏊ��K�ꂽ�Ƃ��ɊG�t���̑���ɔ������Ƃ��������A�Ⴂ������S�������Ă����ꏊ��K�ꂽ���Ɏv�킸�������{������B�������c�u���O�̋{�a�Ƌ{��뉀�ɂ��Ă�204�ł̓��{��̖{�͑O�҂ł���A�J���J�b�\���k�ɂ��Ẵt�����X��̖{�͌�҂ɑ�����B
�@���I�ɂ͎ʐ^�����S�̊O���̊ό��n�Ŕ������{��20��������ł���B�������ȓ��{��̖{�����邪�����ǂ߂Ȃ����̍��̌��t�ŏ����ꂽ�{������B�����̖{�͎ʐ^�B�e���֎~����Ă���ꏊ��K�ꂽ�Ƃ��ɊG�t���̑���ɔ������Ƃ��������A�Ⴂ������S�������Ă����ꏊ��K�ꂽ���Ɏv�킸�������{������B�������c�u���O�̋{�a�Ƌ{��뉀�ɂ��Ă�204�ł̓��{��̖{�͑O�҂ł���A�J���J�b�\���k�ɂ��Ẵt�����X��̖{�͌�҂ɑ�����B �@���̖{�Ɋւ���b�ɂ͑���������B���̖{����10�N�قǂ��������A���x�ڂ��̖k���o�����������B�Z�p�A�o�_����������ɏI���A���b�v�A�b�v�E�~�[�e�B���O���ς܂����Ō�̗[�H�̏�ŁA��������̎В��������̗\����Ă����B���͋A���ւ�12�����̏o���\��Ȃ̂ł���܂ł�1�`2���Ԃ��u�k���I�ӓ��v�ɍs�����肾�Ɠ������B
�@���̖{�Ɋւ���b�ɂ͑���������B���̖{����10�N�قǂ��������A���x�ڂ��̖k���o�����������B�Z�p�A�o�_����������ɏI���A���b�v�A�b�v�E�~�[�e�B���O���ς܂����Ō�̗[�H�̏�ŁA��������̎В��������̗\����Ă����B���͋A���ւ�12�����̏o���\��Ȃ̂ł���܂ł�1�`2���Ԃ��u�k���I�ӓ��v�ɍs�����肾�Ɠ������B �u�}���ق��l�����Îs���̉�v�ł́A2019�N�x�̑傫�Ȏ��g�݂Ƃ��āu�A���w�K��@���b���ƈӌ��𗬁v���J�����B�u�t�Ɍ����ꌧ���}���يْ��̊ݖ{�x������������������B
�u�}���ق��l�����Îs���̉�v�ł́A2019�N�x�̑傫�Ȏ��g�݂Ƃ��āu�A���w�K��@���b���ƈӌ��𗬁v���J�����B�u�t�Ɍ����ꌧ���}���يْ��̊ݖ{�x������������������B �u�}���ق��l�����Îs���̉�v�ł́A2019�N�x�̑傫�Ȏ��g�݂Ƃ��āu�A���w�K�� ���b���ƈӌ��𗬁v���J�����B�u�t�Ɍ����ꌧ���}���يْ��̊ݖ{�x������������������B
�u�}���ق��l�����Îs���̉�v�ł́A2019�N�x�̑傫�Ȏ��g�݂Ƃ��āu�A���w�K�� ���b���ƈӌ��𗬁v���J�����B�u�t�Ɍ����ꌧ���}���يْ��̊ݖ{�x������������������B �@DONDUG�́g�ǂ��h�ƓǂށB�I�����_��� Zontag ���]���������̂œ��j����x�������Ӗ����錾�t���������B
�@DONDUG�́g�ǂ��h�ƓǂށB�I�����_��� Zontag ���]���������̂œ��j����x�������Ӗ����錾�t���������B �@�N�Ɉ�x�A�s�̒����}���قŏ����Q�����̑势�a���T�ɂ��ڂɂ�����B���̎��T�ɂ��Ẳ���ł́u�e�����T���]���A�n��T�R���]������^�������E�ő�̊��a���T�v�Ƃ���Ă���B�����P�R�����������A��b�����A�⊪���o����A���݂ł͑S�P�T���\���ƂȂ��Ă���B�ƂĂ��d���A�}���ق̒I������o�����Ƃ���Ƃ��Ȃ�̗͂�����B�������肷��Ə��ɗ��Ƃ����˂Ȃ��B
�@�N�Ɉ�x�A�s�̒����}���قŏ����Q�����̑势�a���T�ɂ��ڂɂ�����B���̎��T�ɂ��Ẳ���ł́u�e�����T���]���A�n��T�R���]������^�������E�ő�̊��a���T�v�Ƃ���Ă���B�����P�R�����������A��b�����A�⊪���o����A���݂ł͑S�P�T���\���ƂȂ��Ă���B�ƂĂ��d���A�}���ق̒I������o�����Ƃ���Ƃ��Ȃ�̗͂�����B�������肷��Ə��ɗ��Ƃ����˂Ȃ��B �@�������ɂ͉Ƒ�������ĕS�l���ŗV�Ԃ̂��P��A�Ƃ������ƒ�́A���݂ǂ�قǂ���̂��낤�B�q���B�⑷�B���c�����́u�V��߂���v�A�����ď��w�Z�ɓ�������u�U�炵�ǂ�v��u��������v���y���ނ̂��悭�m��ꂽ���i���������B
�@�������ɂ͉Ƒ�������ĕS�l���ŗV�Ԃ̂��P��A�Ƃ������ƒ�́A���݂ǂ�قǂ���̂��낤�B�q���B�⑷�B���c�����́u�V��߂���v�A�����ď��w�Z�ɓ�������u�U�炵�ǂ�v��u��������v���y���ނ̂��悭�m��ꂽ���i���������B �@Luster�͉p�a���T�ł́u����A�h���A�����v�Ȃǂ̖t����Ă���B���҂��܂������Łu���Ƃ̉��A���Ƃ�luster�v�Ə����Ă���Ƃ��������ƁA�����ł�luster�́u���v���Ӗ����Ă���悤���B
�@Luster�͉p�a���T�ł́u����A�h���A�����v�Ȃǂ̖t����Ă���B���҂��܂������Łu���Ƃ̉��A���Ƃ�luster�v�Ə����Ă���Ƃ��������ƁA�����ł�luster�́u���v���Ӗ����Ă���悤���B �@���̎�ϓI���f�ł́A�����g�͓��N�y�̕��ϓI�Ȓj���ɔ䂵�A���p�ق�K�₵���p�x�A���p�W�ɍs�����͔�r�I�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���p�قɍs���͍̂D���������p�W������̂��D�������A�V���Г�����Â܂��͋��Â��A�S���\�_�̍�i���W������Ă�������̑傫�Ȕ��p�قł̓W����́A���E�̕�Ƃ��������i���ӏ܂ł���`�����X���������A�����ȈӖ��Łu����v�̂ōŋ߂ł́u������Ɖ����������v�C����������B
�@���̎�ϓI���f�ł́A�����g�͓��N�y�̕��ϓI�Ȓj���ɔ䂵�A���p�ق�K�₵���p�x�A���p�W�ɍs�����͔�r�I�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���p�قɍs���͍̂D���������p�W������̂��D�������A�V���Г�����Â܂��͋��Â��A�S���\�_�̍�i���W������Ă�������̑傫�Ȕ��p�قł̓W����́A���E�̕�Ƃ��������i���ӏ܂ł���`�����X���������A�����ȈӖ��Łu����v�̂ōŋ߂ł́u������Ɖ����������v�C����������B �@���E�j�A���Ƀ��[���b�p�j�̊�b�I�Ȓm���̌��@���������ƂɂȂ������̒p���������b����B
�@���E�j�A���Ƀ��[���b�p�j�̊�b�I�Ȓm���̌��@���������ƂɂȂ������̒p���������b����B �@������Ƃӂ��������ł͂��邪�A����͐���L�����M�ɂȂ鏑���i2014�N�A�C�[�X�g�E�v���X�j�̃^�C�g���ł���B�������́u�o�E����T���ā\�n���̕Ћ��ɓ`���閧�̉́v�i2013�N�A���~�Ɂj�ŐV�c���Y���w�܂���܂���Ă���B
�@������Ƃӂ��������ł͂��邪�A����͐���L�����M�ɂȂ鏑���i2014�N�A�C�[�X�g�E�v���X�j�̃^�C�g���ł���B�������́u�o�E����T���ā\�n���̕Ћ��ɓ`���閧�̉́v�i2013�N�A���~�Ɂj�ŐV�c���Y���w�܂���܂���Ă���B �@�m�g�j�̃��W�I�ԑg�ɁA�ߌ�P�P���T�����痂���̂T���܂ŕ��������u���W�I�[��ցv�Ƃ����̂�����B1990�N�ɕ������J�n�������������A�L����H��ƁA�J�n���炻�������Ȃ���������m���Ă����悤���B�P�g���C���̃z�e���Z�܂��◾�����Ő^�钆�ɖڂ��o�߂��Ƃ��Ƀ_�C�������A���R�ɒm�����̂��낤�B
�@�m�g�j�̃��W�I�ԑg�ɁA�ߌ�P�P���T�����痂���̂T���܂ŕ��������u���W�I�[��ցv�Ƃ����̂�����B1990�N�ɕ������J�n�������������A�L����H��ƁA�J�n���炻�������Ȃ���������m���Ă����悤���B�P�g���C���̃z�e���Z�܂��◾�����Ő^�钆�ɖڂ��o�߂��Ƃ��Ƀ_�C�������A���R�ɒm�����̂��낤�B �@�H�É���Ƃ͂������O���B�������ˋ�̉���ł���B���̖��̓����R���̏����̑��݂�m�����̂́A�y���́A60�N�߂��O�̍��Z���̍��������B�����A���c��H���ҏW�������Ă����G���u���v�ŕҏW���̉��c���炪�M�����������s�G�b�Z�C�Œm�����ƋL�����Ă���B�ނ́u�H�É���̃��f���͉��R���̉��É���ł���v�Ə����A翂т����Ɛ������Ă����B
�@�H�É���Ƃ͂������O���B�������ˋ�̉���ł���B���̖��̓����R���̏����̑��݂�m�����̂́A�y���́A60�N�߂��O�̍��Z���̍��������B�����A���c��H���ҏW�������Ă����G���u���v�ŕҏW���̉��c���炪�M�����������s�G�b�Z�C�Œm�����ƋL�����Ă���B�ނ́u�H�É���̃��f���͉��R���̉��É���ł���v�Ə����A翂т����Ɛ������Ă����B �@�{�ɂ��Č��̂͊y�����B�܂��Ă��̑��肪�Ǐ��Ƃł���Ȃ�����ł���B������2�l�Ō�����3�l�ł��ꂼ��̎v����l�����q�����̂́A�����Ɗy�����B�t�����X�̌Ì��ɂ́u��l�̉�̓[���̉�A��l�̉�͐_�̉�A�O�l�̉�͉��̉�A�l�l�̉�͈����̉�v�Ƃ����̂����邻�����B�C�k�͉��̉�Ȃ̂��B
�@�{�ɂ��Č��̂͊y�����B�܂��Ă��̑��肪�Ǐ��Ƃł���Ȃ�����ł���B������2�l�Ō�����3�l�ł��ꂼ��̎v����l�����q�����̂́A�����Ɗy�����B�t�����X�̌Ì��ɂ́u��l�̉�̓[���̉�A��l�̉�͐_�̉�A�O�l�̉�͉��̉�A�l�l�̉�͈����̉�v�Ƃ����̂����邻�����B�C�k�͉��̉�Ȃ̂��B �@���ɂ͊���̌Ó�������B���Ƃ͒m�炸�A�匴�X���A���։z�A�ޗNJX���A�|�c�X���A�����X���A�����X���A���R�X���Ȃǂ̖����o�����B�ǂ�����n�܂�ǂ��ŏI���A�Ƃ��������Ƃ͑S���m��Ȃ��B���ꂼ��̊X���̖��O�Ɋ���̏�����l�����邢�͎�X�G���ȃG�s�\�[�h�����т��Ă��邾���ł���B
�@���ɂ͊���̌Ó�������B���Ƃ͒m�炸�A�匴�X���A���։z�A�ޗNJX���A�|�c�X���A�����X���A�����X���A���R�X���Ȃǂ̖����o�����B�ǂ�����n�܂�ǂ��ŏI���A�Ƃ��������Ƃ͑S���m��Ȃ��B���ꂼ��̊X���̖��O�Ɋ���̏�����l�����邢�͎�X�G���ȃG�s�\�[�h�����т��Ă��邾���ł���B �u���ȏ���Q�l���́A�����܂߂ċ�������܂ŁA�Ō�̉��t�܂ł�������Ɠǂނ��̂��v�Ƌ�����ꂽ�̂͂��N���炾�������낤���B�����̖{�œǂ̂��낤���B
�u���ȏ���Q�l���́A�����܂߂ċ�������܂ŁA�Ō�̉��t�܂ł�������Ɠǂނ��̂��v�Ƌ�����ꂽ�̂͂��N���炾�������낤���B�����̖{�œǂ̂��낤���B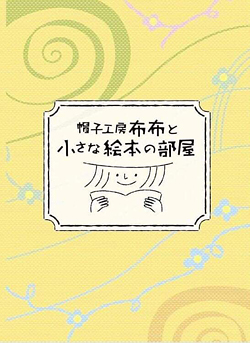 �u�����A�����ȕ��ɂ���肽���v���݂����Șb�ŁA�q�ǂ��̖{���������W�߂Ă����B�ł��A�����������낳�ɋ����͍s���A����Ɏ��Ԃ̖����ŁA���̕��ɂ̖��͂ǂ����ɉ�������Ă����B�d�����痣���ƁA�̖̂��͏�������яo���Ă������A���當�ɂ𗧂��グ��͎͂c���Ă��Ȃ������B
�u�����A�����ȕ��ɂ���肽���v���݂����Șb�ŁA�q�ǂ��̖{���������W�߂Ă����B�ł��A�����������낳�ɋ����͍s���A����Ɏ��Ԃ̖����ŁA���̕��ɂ̖��͂ǂ����ɉ�������Ă����B�d�����痣���ƁA�̖̂��͏�������яo���Ă������A���當�ɂ𗧂��グ��͎͂c���Ă��Ȃ������B �@�H�ו��̖���\�����邱�Ƃ͂ƂĂ�����A�Ƃ����������͓K�ɂ��̖���\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�H�ו��̖���\�����邱�Ƃ͂ƂĂ�����A�Ƃ����������͓K�ɂ��̖���\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@���N�̓~�Ƀp�u���b�N�R�����g����ꂽ��Îs�̐}���ى^�c���j�̒���
�@���N�̓~�Ƀp�u���b�N�R�����g����ꂽ��Îs�̐}���ى^�c���j�̒��� �@��҂͕Ďq�s�̉i�c�x��q����A�I�҂͖����̒d�̎@�O���B�I�҂̕]�́u���Ĉ��ǂ������ɖ{�Ȃǂ��J���ƁA���̊������悭�����Ȃ������̂��Ƌ����B����߂ĕ��Ր������Q�����v
�@��҂͕Ďq�s�̉i�c�x��q����A�I�҂͖����̒d�̎@�O���B�I�҂̕]�́u���Ĉ��ǂ������ɖ{�Ȃǂ��J���ƁA���̊������悭�����Ȃ������̂��Ƌ����B����߂ĕ��Ր������Q�����v �@���Ǐ��Ƃ������t�͍ŋ߂ł��g���Ă���̂��낤���B�u���Ȃ��̈��Ǐ��͉��H�v�u���ł��v�ȂǂƂ�������b�͂���̂��낤���B
�@���Ǐ��Ƃ������t�͍ŋ߂ł��g���Ă���̂��낤���B�u���Ȃ��̈��Ǐ��͉��H�v�u���ł��v�ȂǂƂ�������b�͂���̂��낤���B �@�W�����E�W�I�m�̒Z�ҁu��A�����j�v��ǂ͉̂��\�N�O���������낤���B�v�����@���X�̍r��n�ɁA��40�N�ɘj���Ė̎�����������A�R�S�̂�ɕς����u�t�B�G�V�l�̘b�͎Ⴉ�������̐S�������B
�@�W�����E�W�I�m�̒Z�ҁu��A�����j�v��ǂ͉̂��\�N�O���������낤���B�v�����@���X�̍r��n�ɁA��40�N�ɘj���Ė̎�����������A�R�S�̂�ɕς����u�t�B�G�V�l�̘b�͎Ⴉ�������̐S�������B �@�S��������X�}�z�ɕς����B�����ǂ��g���Ă����̂����킩�炸�A�����Α��q�⑷�ɕ����ẮA�u�ւ�Ȃ��ƂɂȂ����B�ǂ������炢���H�v
�@�S��������X�}�z�ɕς����B�����ǂ��g���Ă����̂����킩�炸�A�����Α��q�⑷�ɕ����ẮA�u�ւ�Ȃ��ƂɂȂ����B�ǂ������炢���H�v �@���āu�Ⴋ�i���̈ӌ��v�i2018�N11��14���t�̂��̗��j�Łu�厖�Ȃ��Ƃ͑S�Ĉ�����ɂ��m�炳���B�c������ǂޔ\�͂��K�́A�g�D�I�ɁA�{���A�b���A�ۂ��A�[�߂邽�߂̑��u�͏����ł���v�Ə������̎Ⴋ�i���̈ӌ����Љ���B
�@���āu�Ⴋ�i���̈ӌ��v�i2018�N11��14���t�̂��̗��j�Łu�厖�Ȃ��Ƃ͑S�Ĉ�����ɂ��m�炳���B�c������ǂޔ\�͂��K�́A�g�D�I�ɁA�{���A�b���A�ۂ��A�[�߂邽�߂̑��u�͏����ł���v�Ə������̎Ⴋ�i���̈ӌ����Љ���B �@�������̖ʔ����G�A�y�����G�A�������G���`����Ă���C���h�l�V�A��A�^�C��A�m���E�F�[��A�C�^���A��A�t�����X��A�p��̊G�{�����ɂ̉��ɕۑ�����Ă���B�o���ł����̍���K�ꂽ�ۂɁA�Z���������d���̍��Ԃ̂ق�̏����̗]�T���Ԃ��g���āA���X�ɍs���A�������߂����̂ł���B
�@�������̖ʔ����G�A�y�����G�A�������G���`����Ă���C���h�l�V�A��A�^�C��A�m���E�F�[��A�C�^���A��A�t�����X��A�p��̊G�{�����ɂ̉��ɕۑ�����Ă���B�o���ł����̍���K�ꂽ�ۂɁA�Z���������d���̍��Ԃ̂ق�̏����̗]�T���Ԃ��g���āA���X�ɍs���A�������߂����̂ł���B �u�c�P�u���̃R�[�q�[�v�Ƃ͂Ȃ�B
�u�c�P�u���̃R�[�q�[�v�Ƃ͂Ȃ�B �u�z��H�̂ƂȂ�v�Ƃ́H�@�Ō�ɊG���������܂ʼn���Ȃ������B
�u�z��H�̂ƂȂ�v�Ƃ́H�@�Ō�ɊG���������܂ʼn���Ȃ������B �@�v���U��ɍ䉮���ꎁ�̏�������Ɏ�����B�}���ق́u�{���ԋp���ꂽ�{�v�̒I�ɒu����Ă����u�c��̏H�v�ł���B
�@�v���U��ɍ䉮���ꎁ�̏�������Ɏ�����B�}���ق́u�{���ԋp���ꂽ�{�v�̒I�ɒu����Ă����u�c��̏H�v�ł���B �@���Ă͏��X�̃��W�̖T�Ɉ�ʓǎҌ����̖����̐V���ē�����u����Ă������A�߂��̏��X�ł͂��̍����炩���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B���݂ł����s����Ă���̂��낤���B
�@���Ă͏��X�̃��W�̖T�Ɉ�ʓǎҌ����̖����̐V���ē�����u����Ă������A�߂��̏��X�ł͂��̍����炩���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B���݂ł����s����Ă���̂��낤���B �@�F�����Ӗ�����R�X���X�icosmos�j�ł͂Ȃ��B�H���Ə������R�X���X�ł���B�R�X���X���H���ƕ\�L���邱�Ƃɂ��ăE�B�L�y�f�B�A�ł́u���̕\�L�́A�����܂������쎌��Ȃ����y�ȁw�H��(�R���S�b�̋�)�x�ŏ��߂ėp�����A�Ȍ㕶�w�I�\���Ƃ��Ďg���邱�Ƃ������Ȃ����v�Ə����Ă��邪�A����͌��ł���B
�@�F�����Ӗ�����R�X���X�icosmos�j�ł͂Ȃ��B�H���Ə������R�X���X�ł���B�R�X���X���H���ƕ\�L���邱�Ƃɂ��ăE�B�L�y�f�B�A�ł́u���̕\�L�́A�����܂������쎌��Ȃ����y�ȁw�H��(�R���S�b�̋�)�x�ŏ��߂ėp�����A�Ȍ㕶�w�I�\���Ƃ��Ďg���邱�Ƃ������Ȃ����v�Ə����Ă��邪�A����͌��ł���B �@�}���ق̃z�[���y�[�W�Ŗ{�̌���������B
�@�}���ق̃z�[���y�[�W�Ŗ{�̌���������B �@�ǂ����čŋ߂̏��w�����邢�͒��w���̓ǂݕ��Ƀ��r���U���Ă��Ȃ��̂��A���́A�^��Ɏv���Ă���B�����q���̍��ɓǂ����̏����ɂ̓��r���U���A����ɂ��w�Z�ł͏K���Ă��Ȃ������̓ǂݕ����o�����悤�ɋL�����Ă���B
�@�ǂ����čŋ߂̏��w�����邢�͒��w���̓ǂݕ��Ƀ��r���U���Ă��Ȃ��̂��A���́A�^��Ɏv���Ă���B�����q���̍��ɓǂ����̏����ɂ̓��r���U���A����ɂ��w�Z�ł͏K���Ă��Ȃ������̓ǂݕ����o�����悤�ɋL�����Ă���B �@�茳��FRONT PAGE�Ƃ����\��̏c32.5cm�~��23.5cm�~��2.5�p �̑啔�Ȗ{������B�L���ɂ��Ƃ��̖{�͔��s�シ���ɒ����V���̏��]���ł��Ȃ�̃X�y�[�X������ďЉ��Ă����B
�@�茳��FRONT PAGE�Ƃ����\��̏c32.5cm�~��23.5cm�~��2.5�p �̑啔�Ȗ{������B�L���ɂ��Ƃ��̖{�͔��s�シ���ɒ����V���̏��]���ł��Ȃ�̃X�y�[�X������ďЉ��Ă����B �@���^�C�A���ĉ��N�Ԃ����o�߂������A�u��Ђ̔����ۂ���������̂͂����������낤�v�Ǝv���A�Ɩ��W�̎蒠��S�ď��������B
�@���^�C�A���ĉ��N�Ԃ����o�߂������A�u��Ђ̔����ۂ���������̂͂����������낤�v�Ǝv���A�Ɩ��W�̎蒠��S�ď��������B �@�`�����l����͂ŕ��f����Ă��钆������́u�O���u Three Kingdoms�v���Ȃ����Ă��邱�Ƃ�m��A�������n�߂��B���Ȃ�o���Ă���̎������������A�ŏI��ł���X�T�b�܂ő����Ď����B
�@�`�����l����͂ŕ��f����Ă��钆������́u�O���u Three Kingdoms�v���Ȃ����Ă��邱�Ƃ�m��A�������n�߂��B���Ȃ�o���Ă���̎������������A�ŏI��ł���X�T�b�܂ő����Ď����B �@���܂Łu�}���قƂ킽���v�ɂ��Ċ���̕��͂��f�ڂ��đՂ����B�}���قƖ{�Ƃ́A���Ă���Ȃ��W�ɂ���B���̗��̖��̂��u�}���قƂ킽���@�{�Ƃ킽���v�ł���B�u�}���قƂ킽���v�̎��́u�{�Ƃ킽���v�̌W�������낢��U��Ԃ��Ă݂悤�Ǝv���B
�@���܂Łu�}���قƂ킽���v�ɂ��Ċ���̕��͂��f�ڂ��đՂ����B�}���قƖ{�Ƃ́A���Ă���Ȃ��W�ɂ���B���̗��̖��̂��u�}���قƂ킽���@�{�Ƃ킽���v�ł���B�u�}���قƂ킽���v�̎��́u�{�Ƃ킽���v�̌W�������낢��U��Ԃ��Ă݂悤�Ǝv���B �@�����ԁA���b����ɎQ�����Ă����B���́A�u���b���v�͂��Ȃ��̂ł����ς畷�����A�����ĉ��̔��������Ƃɂ��Ċ��z��`������������B
�@�����ԁA���b����ɎQ�����Ă����B���́A�u���b���v�͂��Ȃ��̂ł����ς畷�����A�����ĉ��̔��������Ƃɂ��Ċ��z��`������������B �u�m�s�ɂ͂������Ȃ��c�����ȂƂ���A���݂̂m�s�͂��܂�ɂ����̂����ǂ��������Ă���ƌ��킴��Ȃ��B�~�}�Z���^�[�������������A�s�c�Z����V�������Ă��邵�A���ݏ����{�݂��g�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ɁA�}���قȂǂƂ������̑����ɂ��Ȃ�ʕ����{�݂ɏ��Ȃ���ʗ\�Z���Ԃ����ނƂ͖{���]�|���͂Ȃ͂������B���s�������̏�Ȃ��B�c�ݏo�̎��т����Ă��A�w���}���̈ꗗ�����Ă��A������A�����ݖ{���ł͂Ȃ����B����Ȏd���Ȃ�킴�킴�����̂�����킸��킹�邱�Ƃ͂Ȃ��B�c�v�i�����ЁA���c��u���������̖{�́v100�Łj
�u�m�s�ɂ͂������Ȃ��c�����ȂƂ���A���݂̂m�s�͂��܂�ɂ����̂����ǂ��������Ă���ƌ��킴��Ȃ��B�~�}�Z���^�[�������������A�s�c�Z����V�������Ă��邵�A���ݏ����{�݂��g�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ɁA�}���قȂǂƂ������̑����ɂ��Ȃ�ʕ����{�݂ɏ��Ȃ���ʗ\�Z���Ԃ����ނƂ͖{���]�|���͂Ȃ͂������B���s�������̏�Ȃ��B�c�ݏo�̎��т����Ă��A�w���}���̈ꗗ�����Ă��A������A�����ݖ{���ł͂Ȃ����B����Ȏd���Ȃ�킴�킴�����̂�����킸��킹�邱�Ƃ͂Ȃ��B�c�v�i�����ЁA���c��u���������̖{�́v100�Łj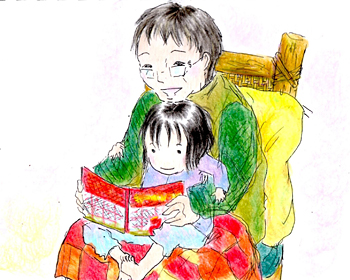 �@���ɂ́A���l�̑������܂��B�߂��ɂ��鑷�����́A�䂪�Ƃɂ���Ă��ẮA�Ƃ������Ђ������A�u�ǂ�Ł@�ǂ�ŁI�v�Ɩ{�������Ă��܂��B
�@���ɂ́A���l�̑������܂��B�߂��ɂ��鑷�����́A�䂪�Ƃɂ���Ă��ẮA�Ƃ������Ђ������A�u�ǂ�Ł@�ǂ�ŁI�v�Ɩ{�������Ă��܂��B �@���݂̌����}���ق́A��{�I�ɑ��݂ɖ���������������߂��Ă���B����́A�Ⴆ�A�����}���ق��l�C���Ђ����w�����݂��o���Ƃ����T�[�r�X��w�������K�̂��߂Ɍ����}���ق̉{���Ȃ�Ɛ肷��Ƃ��������ۂɑ��Ď�X�̈ӌ����ՓˁA�������Ă���Ƃ������Ⴉ����f����B
�@���݂̌����}���ق́A��{�I�ɑ��݂ɖ���������������߂��Ă���B����́A�Ⴆ�A�����}���ق��l�C���Ђ����w�����݂��o���Ƃ����T�[�r�X��w�������K�̂��߂Ɍ����}���ق̉{���Ȃ�Ɛ肷��Ƃ��������ۂɑ��Ď�X�̈ӌ����ՓˁA�������Ă���Ƃ������Ⴉ����f����B �@��P��ڂ̂��b��́A�݂�ȂŊo������V�сu���肠���сv�����b��̃v���O�����ɓ���A���b�w������Ƃ����̂���ǂ�x�A�w�ӂ���͂Ƃ������x�A�G�{�w�������������x�ł����B�Q���Ҏq�ǂ��i�O�˂���R�ˁj�V�l�A���ƂȂP�S���łQ�P���̎Q���ҁB�ŏ��ɂ��Ă͑�R�Q���҂�����܂����B
�@��P��ڂ̂��b��́A�݂�ȂŊo������V�сu���肠���сv�����b��̃v���O�����ɓ���A���b�w������Ƃ����̂���ǂ�x�A�w�ӂ���͂Ƃ������x�A�G�{�w�������������x�ł����B�Q���Ҏq�ǂ��i�O�˂���R�ˁj�V�l�A���ƂȂP�S���łQ�P���̎Q���ҁB�ŏ��ɂ��Ă͑�R�Q���҂�����܂����B �@���������A�}���ي֘A�̓��v�͂ǂ��ɂ���̂��A���܂ōl�������Ƃ��Ȃ������B���v�����͕����Ȋw�Ȃ̎Љ�瓝�v�i�Љ�璲�����j�̒��ɂ������B3�N���Ɏ��{����Ă��邱�̒����́A����27�N�x�������ʂ��ŐV�̂��̂ł���B
�@���������A�}���ي֘A�̓��v�͂ǂ��ɂ���̂��A���܂ōl�������Ƃ��Ȃ������B���v�����͕����Ȋw�Ȃ̎Љ�瓝�v�i�Љ�璲�����j�̒��ɂ������B3�N���Ɏ��{����Ă��邱�̒����́A����27�N�x�������ʂ��ŐV�̂��̂ł���B �@�ŏ��ɁA�V�������b��𗧂��グ��ׂ̌v��𗧂Ă܂����B���b��n�݂̕K�{�����ł��B�܂��͂��b������Ă��ꂻ���Ȑl�W�߂���n�߂܂����B���͓����T�[�N�����Ԃŋ��Z���Ԃ������F�l�������m�l�ɁA���̎v���ƌv���������܂����B����ƁA���̒m�l�����l���Љ�Ă���܂����B
�@�ŏ��ɁA�V�������b��𗧂��グ��ׂ̌v��𗧂Ă܂����B���b��n�݂̕K�{�����ł��B�܂��͂��b������Ă��ꂻ���Ȑl�W�߂���n�߂܂����B���͓����T�[�N�����Ԃŋ��Z���Ԃ������F�l�������m�l�ɁA���̎v���ƌv���������܂����B����ƁA���̒m�l�����l���Љ�Ă���܂����B �@�ŋ߂̎�҂͗F�l�Ƃ̑ҍ��킹�ꏊ���ǂ̂悤�ɑI��ł���̂��낤���B�X�}�[�g�t�H������g���Ă���ނ�ޏ���́A���Ԃɒx�ꂻ���ɂȂ�����A�ꏊ��������Ȃ��Ȃ����肵���璼���ɓd�b�������A���邢�̓��C���ŘA������荇���ɈႢ�Ȃ��B��ʂɒn�}���Ăяo�����̈ē��ɏ]����������Ȃ��B�����̌��ʂƂ��đ҂����킹�ꏊ�ɂ��Ă͂��܂�C�������Ă��Ȃ��̂����m��Ȃ��B
�@�ŋ߂̎�҂͗F�l�Ƃ̑ҍ��킹�ꏊ���ǂ̂悤�ɑI��ł���̂��낤���B�X�}�[�g�t�H������g���Ă���ނ�ޏ���́A���Ԃɒx�ꂻ���ɂȂ�����A�ꏊ��������Ȃ��Ȃ����肵���璼���ɓd�b�������A���邢�̓��C���ŘA������荇���ɈႢ�Ȃ��B��ʂɒn�}���Ăяo�����̈ē��ɏ]����������Ȃ��B�����̌��ʂƂ��đ҂����킹�ꏊ�ɂ��Ă͂��܂�C�������Ă��Ȃ��̂����m��Ȃ��B �w�N�ɂT�����o��r�U���g���āA�l�p�[���ɑ؍݂������B�N���z������P�O�����̃r�U�ɂȂ�x
�w�N�ɂT�����o��r�U���g���āA�l�p�[���ɑ؍݂������B�N���z������P�O�����̃r�U�ɂȂ�x �@���͑ސE����O����A�߂��̐}���قł��b���������Ń{�����e�B�A���������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B��������R�}���قɓ���ƁA�������˂̊Ԃł��b�������Ă��܂����B�G�{�̓ǂݕ������Ǝ��ŋ��ł����B�J�E���^�[�ł��̉�̑�\�҂������Ă��炢�A�����܂����B
�@���͑ސE����O����A�߂��̐}���قł��b���������Ń{�����e�B�A���������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B��������R�}���قɓ���ƁA�������˂̊Ԃł��b�������Ă��܂����B�G�{�̓ǂݕ������Ǝ��ŋ��ł����B�J�E���^�[�ł��̉�̑�\�҂������Ă��炢�A�����܂����B �@�U�O�˂��߂��Ă���A�a�C�Ƃ������̐N���҂����̑̂ƐS�ɓ��荞��ł��܂��܂����B
�@�U�O�˂��߂��Ă���A�a�C�Ƃ������̐N���҂����̑̂ƐS�ɓ��荞��ł��܂��܂����B �u�����́����Ȃ̂��v�ƌ����^�C�g���́A�Â��ǂ�����̃A�����J�̎�҂̏��X�Ɋւ���ƂĂ��V�N�ȃG�b�Z�C��ǂ̂͂Q�O�Α�̂��Ƃ������B��̓I�ȓ��e�͖ܘ_�A���́����⒘�Җ���������w�͂��Ă��������v���o���Ȃ��̂͋ɂ߂Ďc�O�����A���̃^�C�g���ɕ킦�u�d�ԁi�̍��ȁj�͐}���فi�̉{�����j�Ȃ̂��v�Ƃ͎v���B
�u�����́����Ȃ̂��v�ƌ����^�C�g���́A�Â��ǂ�����̃A�����J�̎�҂̏��X�Ɋւ���ƂĂ��V�N�ȃG�b�Z�C��ǂ̂͂Q�O�Α�̂��Ƃ������B��̓I�ȓ��e�͖ܘ_�A���́����⒘�Җ���������w�͂��Ă��������v���o���Ȃ��̂͋ɂ߂Ďc�O�����A���̃^�C�g���ɕ킦�u�d�ԁi�̍��ȁj�͐}���فi�̉{�����j�Ȃ̂��v�Ƃ͎v���B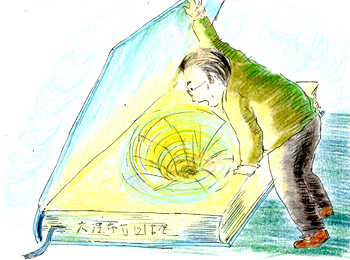 �@�}���ق̃z�[���y�[�W�ȂǁA�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��Ă͏o��Ȃ��{������B
�@�}���ق̃z�[���y�[�W�ȂǁA�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��Ă͏o��Ȃ��{������B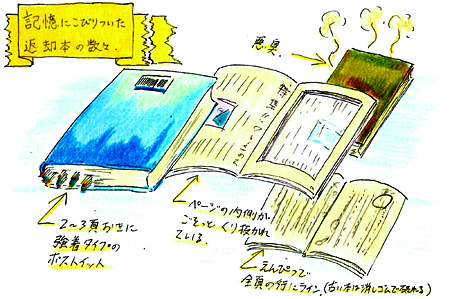 �@�}���ق̖{���u�����v���ƂɊւ��鏔�X���A�v���t���܂������߂�B
�@�}���ق̖{���u�����v���ƂɊւ��鏔�X���A�v���t���܂������߂�B �@���͌Ö{�����u���̐}���فv�Ə���Ɏv���Ă����B�����悤�ȈӖ��ł�����́u���̐}���فv���������̂��e���r��ʂ��v���o�����Ă��ꂽ�B
�@���͌Ö{�����u���̐}���فv�Ə���Ɏv���Ă����B�����悤�ȈӖ��ł�����́u���̐}���فv���������̂��e���r��ʂ��v���o�����Ă��ꂽ�B �@�����Ԃ��������Ă��܂����B
�@�����Ԃ��������Ă��܂����B �@��Ƃ��Ă��郉�P�b�g�{�[�����y���ނ��߁A�T�ɂQ��A�Г��P���ԋ��̎��Ԃ������Ēr�c�s�ɂ���X�|�[�c�N���u�ɒʂ��Ă���B�}�C�i�[�ȃX�|�[�c�ł��郉�P�b�g�{�[���̃R�[�g�͑��{���ł������m�����S���������Ȃ��A�䂪�Ƃ����ԋ߂��R�[�g�ւ̏��v���Ԃ��Г��P���ԋ��Ƃ����킯�ł���B
�@��Ƃ��Ă��郉�P�b�g�{�[�����y���ނ��߁A�T�ɂQ��A�Г��P���ԋ��̎��Ԃ������Ēr�c�s�ɂ���X�|�[�c�N���u�ɒʂ��Ă���B�}�C�i�[�ȃX�|�[�c�ł��郉�P�b�g�{�[���̃R�[�g�͑��{���ł������m�����S���������Ȃ��A�䂪�Ƃ����ԋ߂��R�[�g�ւ̏��v���Ԃ��Г��P���ԋ��Ƃ����킯�ł���B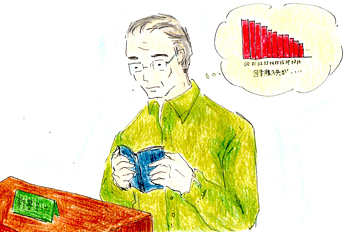 �@�P���ɍs��ꂽ�u���쐣�����u����v�ɎQ�����܂����B���쐣���A�}���قŖ��₳�ꑽ���̖{�ɐe���ޒ��ŋ����ƊS�������A�l�X�Ȓm�����������b���āA���߂Đ}���ق̑���������܂����B
�@�P���ɍs��ꂽ�u���쐣�����u����v�ɎQ�����܂����B���쐣���A�}���قŖ��₳�ꑽ���̖{�ɐe���ޒ��ŋ����ƊS�������A�l�X�Ȓm�����������b���āA���߂Đ}���ق̑���������܂����B �@�R���̏��{�̂��ƁA�}���ق̂Q�K�Ŕ��R�ƕ��ɖ{��I��ł��܂����B
�@�R���̏��{�̂��ƁA�}���ق̂Q�K�Ŕ��R�ƕ��ɖ{��I��ł��܂����B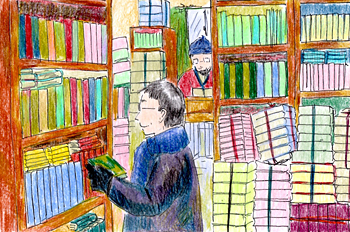 �@��������ꂸ�ɐ}���قƏ������B�I�ɐ������̐V�i�ł͂Ȃ����Ђ�����ł���Ƃ���͐}���قɎ��Ă��邪�A�{���͐}���قł͂Ȃ��B�Ï��Ђ���������ł���B���Ă͉䂪�Ƃ�������ĂP�O���ȓ��̂Ƃ���ɂR���̂��̂悤�ȓX���������B
�@��������ꂸ�ɐ}���قƏ������B�I�ɐ������̐V�i�ł͂Ȃ����Ђ�����ł���Ƃ���͐}���قɎ��Ă��邪�A�{���͐}���قł͂Ȃ��B�Ï��Ђ���������ł���B���Ă͉䂪�Ƃ�������ĂP�O���ȓ��̂Ƃ���ɂR���̂��̂悤�ȓX���������B �@�d�Ԃɏ��ƁA���̐l����������ǂ�ł��邩���C�ɂȂ�B�قƂ�ǂ��X�}�z���̂����Ă��钆�ŁA�V����ǂ�ł���l��{��ǂ�ł���̂�����ƃz�b�Ƃ���B
�@�d�Ԃɏ��ƁA���̐l����������ǂ�ł��邩���C�ɂȂ�B�قƂ�ǂ��X�}�z���̂����Ă��钆�ŁA�V����ǂ�ł���l��{��ǂ�ł���̂�����ƃz�b�Ƃ���B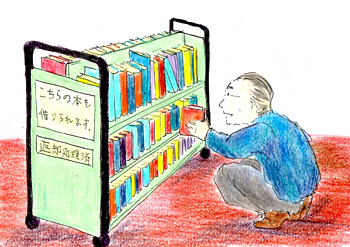 �@�I�̒����A�Ƃ����������ɒu����Ă���{�A���������邢�͐����Ԗ��ɕς��u�ό����݂̖{�I�v�̂��b�ł���B
�@�I�̒����A�Ƃ����������ɒu����Ă���{�A���������邢�͐����Ԗ��ɕς��u�ό����݂̖{�I�v�̂��b�ł���B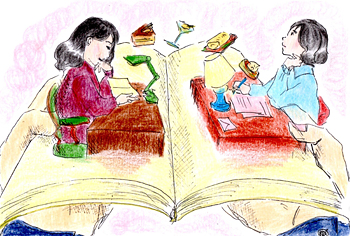 �@�Βk��{�ɂ��Ă��邱�Ƃ��i�\�������������ł́j������Ȃ����̂�����B
�@�Βk��{�ɂ��Ă��邱�Ƃ��i�\�������������ł́j������Ȃ����̂�����B �@�ӂӂӁc�ƁA���X���݂Ȃ���ǂ�ł��܂��܂����B�����������A���쎅����́u�c�o�L����X�v��N���N�G�X�g���āA����Ɛ挎�P�O�����{�Ɂu�\��{�A�m�ۂ��Ă��܂��v�Ƃ����A�������������āA�P�O�����Ԗ{�����{�ł����B
�@�ӂӂӁc�ƁA���X���݂Ȃ���ǂ�ł��܂��܂����B�����������A���쎅����́u�c�o�L����X�v��N���N�G�X�g���āA����Ɛ挎�P�O�����{�Ɂu�\��{�A�m�ۂ��Ă��܂��v�Ƃ����A�������������āA�P�O�����Ԗ{�����{�ł����B �w�݂��o���𒆐S�Ƃ����}���فx�̈Ӗ���m�����̂́A�����ꌧ���}���ْ��A�O��P�Y���́u�}���ٍu���v���Ă���ł����B
�w�݂��o���𒆐S�Ƃ����}���فx�̈Ӗ���m�����̂́A�����ꌧ���}���ْ��A�O��P�Y���́u�}���ٍu���v���Ă���ł����B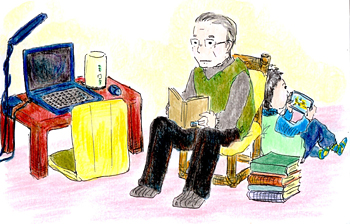 �@���x���ʐM�l�b�g���[�N���\�z���ꂽ����Љ�ɂ����āA���}�̎�̂̐}���ق͂ǂ��Ȃ�̂��낤���A�܂��d�q���Ƃ̊W�ł͐}���ق͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����҂���邱�ƂɂȂ�̂��낤���B
�@���x���ʐM�l�b�g���[�N���\�z���ꂽ����Љ�ɂ����āA���}�̎�̂̐}���ق͂ǂ��Ȃ�̂��낤���A�܂��d�q���Ƃ̊W�ł͐}���ق͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����҂���邱�ƂɂȂ�̂��낤���B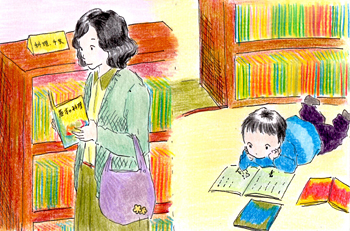 �u�ɂ��킢�̂���}���فv�u�ۑ�����^�}���فv�u�w�K���̂���}���فv�u�i���R�[�i�[�̂���}���فv�u���邭�Ă��ꂢ�Ȑ}���فv�u�����֗̕��ȂƂ���ɂ���}���فv�u�Â��Ȍ����̒��ɂ���}���فv�u�����Ă�����Ƃ���ɂ���}���فv�u�V�����{�̂����Ղ肠��}���فv�u�ÓT����w�p���\��w�̂悤�Ȑ}���فv�u�n��̓��F����}���فv�u�����̖L���Ȑ}���فv�u�e�Ȏi������̂���}���فv�u�n���[���[�N�̂悤�Ȏd����{���q���g�������}���فv�u�N�Ƃɖ𗧂}���فv�u�����T�[�r�X�̍s���͂����}���فv�u�R���T�[�g��[�N�V���b�v�������āA���̂����}���فv�u�傫�Ȋ����̖{�̂���}���فv�u�n���f�B�L���b�v�������Ă��g���₷���}���فv�u���S�n�̂����}���فv�c�c
�u�ɂ��킢�̂���}���فv�u�ۑ�����^�}���فv�u�w�K���̂���}���فv�u�i���R�[�i�[�̂���}���فv�u���邭�Ă��ꂢ�Ȑ}���فv�u�����֗̕��ȂƂ���ɂ���}���فv�u�Â��Ȍ����̒��ɂ���}���فv�u�����Ă�����Ƃ���ɂ���}���فv�u�V�����{�̂����Ղ肠��}���فv�u�ÓT����w�p���\��w�̂悤�Ȑ}���فv�u�n��̓��F����}���فv�u�����̖L���Ȑ}���فv�u�e�Ȏi������̂���}���فv�u�n���[���[�N�̂悤�Ȏd����{���q���g�������}���فv�u�N�Ƃɖ𗧂}���فv�u�����T�[�r�X�̍s���͂����}���فv�u�R���T�[�g��[�N�V���b�v�������āA���̂����}���فv�u�傫�Ȋ����̖{�̂���}���فv�u�n���f�B�L���b�v�������Ă��g���₷���}���فv�u���S�n�̂����}���فv�c�c �@�m�g�j�̑�̓h���}�⒩�̃h���}���n�߂Ƃ��ăe���r�h���}�Ƃ͉��̂Ȃ����ł��邪�A����Ƃ��A�V���̃e���r�ԑg�ē����Ő�������Ă����u�c�o�L����X�v�������B�W�b�����̃V���[�Y�̑�U�b�������B�h���}�̓��e�͖ܘ_�A����̎Ⴂ�����̘Ȃ܂����C�ɓ���V�b�A�W�b�ƌ��邱�ƂɂȂ����B
�@�m�g�j�̑�̓h���}�⒩�̃h���}���n�߂Ƃ��ăe���r�h���}�Ƃ͉��̂Ȃ����ł��邪�A����Ƃ��A�V���̃e���r�ԑg�ē����Ő�������Ă����u�c�o�L����X�v�������B�W�b�����̃V���[�Y�̑�U�b�������B�h���}�̓��e�͖ܘ_�A����̎Ⴂ�����̘Ȃ܂����C�ɓ���V�b�A�W�b�ƌ��邱�ƂɂȂ����B �@���̒n�ɏZ�ނ悤�ɂȂ��āA�l�X�ȓǂݕ��������̊�����m�����B���������O�Ƃ��ĎQ�������Ă�����Ă���B�F���A�q�ǂ������̓Ǐ��������x���A����Ɏ���̊����Ƃ���簐i����Ă��邱�Ƃɓ���������B
�@���̒n�ɏZ�ނ悤�ɂȂ��āA�l�X�ȓǂݕ��������̊�����m�����B���������O�Ƃ��ĎQ�������Ă�����Ă���B�F���A�q�ǂ������̓Ǐ��������x���A����Ɏ���̊����Ƃ���簐i����Ă��邱�Ƃɓ���������B �@�����Z��ł���s�̐}���ُ��₻��ɕt�ъ֘A����}���يǗ��^�c�Ɋւ���K���A�يO�ݏo�K���Ȃǂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�ʔ������Ȃ�������ł��邾�����낤�Ƃ͎v�����A��x���炢�ڂ�ʂ��Ă����̂����������킩��Ȃ��A�Ɛ}���ق̃z�[���y�[�W���N���b�N�����B
�@�����Z��ł���s�̐}���ُ��₻��ɕt�ъ֘A����}���يǗ��^�c�Ɋւ���K���A�يO�ݏo�K���Ȃǂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B�ʔ������Ȃ�������ł��邾�����낤�Ƃ͎v�����A��x���炢�ڂ�ʂ��Ă����̂����������킩��Ȃ��A�Ɛ}���ق̃z�[���y�[�W���N���b�N�����B �@������A�O�\�N���炢�O�̂��鑺�̘b���B
�@������A�O�\�N���炢�O�̂��鑺�̘b���B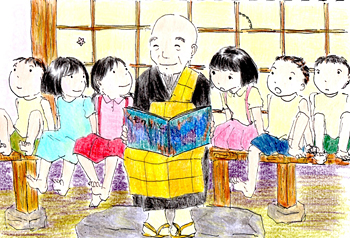 �@����A�}���قōs��ꂽ�Â��ɎQ�����܂����B
�@����A�}���قōs��ꂽ�Â��ɎQ�����܂����B �@���s�̐}���ق���̃��[���}�K�W�������Ă���Ɓፑ������}���ق��炨�������������܂�����Ƃ����L�����ڂɕt�����B
�@���s�̐}���ق���̃��[���}�K�W�������Ă���Ɓፑ������}���ق��炨�������������܂�����Ƃ����L�����ڂɕt�����B �@���ԓ��̃u���O�A�Ƃ����Ă����Ȃ�̐l�����Q������A�e�r��ړI�Ƃ���g�D�̂����A���͂��̉^�c�S�������Ă���B
�@���ԓ��̃u���O�A�Ƃ����Ă����Ȃ�̐l�����Q������A�e�r��ړI�Ƃ���g�D�̂����A���͂��̉^�c�S�������Ă���B �@�����@����p�q����I
�@�����@����p�q����I �@���̗��̓ǎ҂Ȃ�u���܂���A���������Ă���̂��B�Q���������Ă���̂��v�ƕ�����邱�Ƃ��낤���A���ɂƂ��Ă͐V�����ł������B
�@���̗��̓ǎ҂Ȃ�u���܂���A���������Ă���̂��B�Q���������Ă���̂��v�ƕ�����邱�Ƃ��낤���A���ɂƂ��Ă͐V�����ł������B �@����A�䂪�Ƃ̖{�I�����Ă������̂��Ƃ��B�P�O�N�O�ɂ�����ֈ����z���Ă���ۂɒi�{�[���������\�ɂ��Ȃ�قǂ̖{���̂ĂĂ����̂ɁA���̊Ԃɂ��{�������Ă��āA�܂����I�̐�����������Ȃ��Ȃ����B�Ö{���ւƂ̎��̒�Ăɂ�������炸�A���ǁA�Ɛl�̋����咣�Ŗ����P��̔p�i����ɏo�����Ƃɂ����B�܂�A��发�͔���ɒl�����Ƃ̍l���ƁA���ǂ܂Ȃ�����̐�������Ɠǂ܂Ȃ����낤�Ƃ������Ɍ����������炾�B
�@����A�䂪�Ƃ̖{�I�����Ă������̂��Ƃ��B�P�O�N�O�ɂ�����ֈ����z���Ă���ۂɒi�{�[���������\�ɂ��Ȃ�قǂ̖{���̂ĂĂ����̂ɁA���̊Ԃɂ��{�������Ă��āA�܂����I�̐�����������Ȃ��Ȃ����B�Ö{���ւƂ̎��̒�Ăɂ�������炸�A���ǁA�Ɛl�̋����咣�Ŗ����P��̔p�i����ɏo�����Ƃɂ����B�܂�A��发�͔���ɒl�����Ƃ̍l���ƁA���ǂ܂Ȃ�����̐�������Ɠǂ܂Ȃ����낤�Ƃ������Ɍ����������炾�B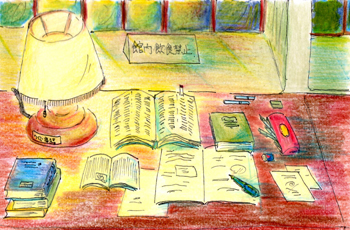 �@���W�I���������ɖS���Ȃ����y�M�[�t�R����́u�w������v������ė����B���̉̎��̈�Ԃɂ́u�H�̓��́@�}���ق́@�m�[�g�ƃC���N�̓����v�Ƒ�w�̐}���ق��������Ă���B�����g�͑�w�̐}���قŕ������Ƃ����L���͂Ȃ����A���̉̂ɂ������Ă���悤�Ȑt�̎v���o�����l�B������������������̂��낤�A���̉̂��D�ސl�͑����悤���B
�@���W�I���������ɖS���Ȃ����y�M�[�t�R����́u�w������v������ė����B���̉̎��̈�Ԃɂ́u�H�̓��́@�}���ق́@�m�[�g�ƃC���N�̓����v�Ƒ�w�̐}���ق��������Ă���B�����g�͑�w�̐}���قŕ������Ƃ����L���͂Ȃ����A���̉̂ɂ������Ă���悤�Ȑt�̎v���o�����l�B������������������̂��낤�A���̉̂��D�ސl�͑����悤���B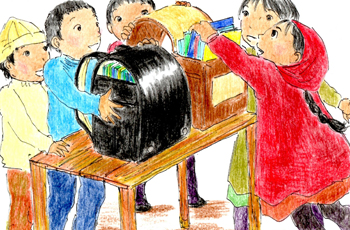 �@�����O�ɎO�N������Œf�̗������܂����B�V��̃V���v���Ȑ��������邽�߂̈����z����Ƃł����B
�@�����O�ɎO�N������Œf�̗������܂����B�V��̃V���v���Ȑ��������邽�߂̈����z����Ƃł����B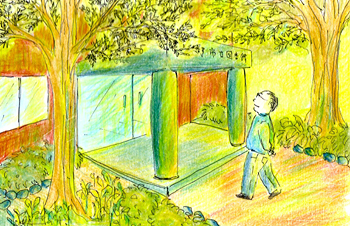 �u�}���ق� ��蓹������ �l�����ȁv
�u�}���ق� ��蓹������ �l�����ȁv �@�}���ق̈֎q�ɍ����āA�����ّz�B�ӂƁA�V���R�[�i�[�̋L�����ڂɂ��܂����B�u���������v�v�ŋ߁A���X�ڂɂ��錾�t�ł��B���������v�ˁc�c�B
�@�}���ق̈֎q�ɍ����āA�����ّz�B�ӂƁA�V���R�[�i�[�̋L�����ڂɂ��܂����B�u���������v�v�ŋ߁A���X�ڂɂ��錾�t�ł��B���������v�ˁc�c�B �@�`���`���Ɛ�̕���������A�C���^�[�l�b�g���g���Ďs���}���ق̑����̎�o���\������Ă���Ƃ��ɁA���ق��u���[���}�K�W���v�s���Ă��邱�ƂɋC�t�����B������ƋC�ɂȂ�A���ɂ�������悤�Ƀp�\�R���̐ݒ��ύX�����B
�@�`���`���Ɛ�̕���������A�C���^�[�l�b�g���g���Ďs���}���ق̑����̎�o���\������Ă���Ƃ��ɁA���ق��u���[���}�K�W���v�s���Ă��邱�ƂɋC�t�����B������ƋC�ɂȂ�A���ɂ�������悤�Ƀp�\�R���̐ݒ��ύX�����B �@�l���Ă݂�ƁA���܂ł̕�炵�̒��Ő}���فE�{�͂����Ǝ����̐g�߂ȂƂ���ɂ���܂����B���̎��X�ɂԂ������ۑ�̂��鎞�ɁA�����Ԃ�Ə�����ꂽ�Ƃ����v��������܂��B
�@�l���Ă݂�ƁA���܂ł̕�炵�̒��Ő}���فE�{�͂����Ǝ����̐g�߂ȂƂ���ɂ���܂����B���̎��X�ɂԂ������ۑ�̂��鎞�ɁA�����Ԃ�Ə�����ꂽ�Ƃ����v��������܂��B| �� |
��Îs���̐}���وē��̃p���t���b�g����������Ȃ��B���ꂼ��̐}���ق̓��F�̐����Ƃ��n�}�Ƃ��B�����ƁA�����ƍs�������Ȃ�ɂ������Ȃ��B |
| �� |
��Îs�̐}���ق̕��݂�}���ً��c��̎����Ȃǂ����˂ɔz�u���ė~�����ȁB |
| �� |
��Îs�̂��Ƃ������ƒm�肽���ȁB�ʐ^�W�A�G��W�A�̘b�̌��A�u����J�ÂȂǂ�����ꂵ���ȁB |
| �� |
���ɖ{�Ɠ��l�A�V���������߂Ă�������T���₷���B |
| �� |
�ȑO�́A���ւ̌f���ɓǏ��N�Ǔ��̊���������Ă���c�̈ꗗ�\���������Ƃ����L�����B��̖������邩������Ȃ����ǁA�����̋@��ɒm�肽���B |
| �� |
�}���ق��̂��̂��������炩�A�Ȃ��Ȃ��v�]���o���ɂ����B |
 �@���͖������邱�Ƃ̏��Ȃ��l�Ԃ��Ǝv���Ă��邪�A�����A��̖����݂��B�i�u�ǂ̂悤�Ȑl���ł����邢�����̖������Ă���A����������L�����Ă��Ȃ��������v�Ƃ̐��ɏ]���A�u�ڊo�߂����ɑO��̖��̈���͂�����Ǝv���o�������钩���������v�Ə����̂��������̂��낤���B�j
�@���͖������邱�Ƃ̏��Ȃ��l�Ԃ��Ǝv���Ă��邪�A�����A��̖����݂��B�i�u�ǂ̂悤�Ȑl���ł����邢�����̖������Ă���A����������L�����Ă��Ȃ��������v�Ƃ̐��ɏ]���A�u�ڊo�߂����ɑO��̖��̈���͂�����Ǝv���o�������钩���������v�Ə����̂��������̂��낤���B�j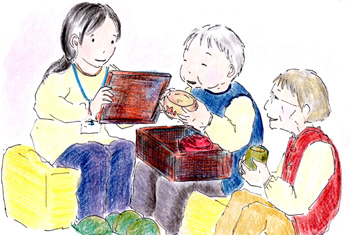 �@�����Q�N�O�ɂȂ��Ă��܂������A���m���c���s���}���ق̌��ْ��A�X������̍u��������A�c�u�c�ł��c���s���}���ق̏Љ�������B�����{�݂̑f���炵�������Ɛ}���ٌo�c�̂��b�����f������������A��x���w�ɍs���Ă݂����Ǝv�����B�����A���ɂȂ�������ł��Ă��Ȃ��B
�@�����Q�N�O�ɂȂ��Ă��܂������A���m���c���s���}���ق̌��ْ��A�X������̍u��������A�c�u�c�ł��c���s���}���ق̏Љ�������B�����{�݂̑f���炵�������Ɛ}���ٌo�c�̂��b�����f������������A��x���w�ɍs���Ă݂����Ǝv�����B�����A���ɂȂ�������ł��Ă��Ȃ��B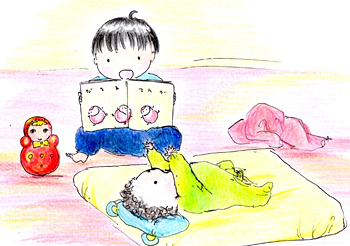 �@�G�{�̂���q��ẴR�������������Ă�����āA�������O��ڂɂȂ�܂����B�ǂݕԂ��Ă݂�ƁA��̑�Ȉ玙�L�^�ł��B
�@�G�{�̂���q��ẴR�������������Ă�����āA�������O��ڂɂȂ�܂����B�ǂݕԂ��Ă݂�ƁA��̑�Ȉ玙�L�^�ł��B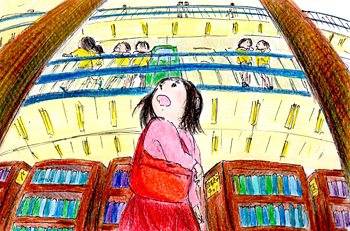 �@�w�Z�ɂ́A�}����������܂��B
�@�w�Z�ɂ́A�}����������܂��B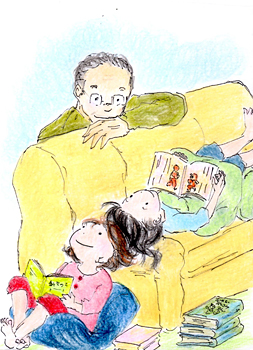 �@�}���ق̒�`�ɂ͑S�����ěƂ܂炸�A�܂��ǂ̂悤�Ɋg����߂��Ă��l���ɂƂ������Ȃ��A�����ȏ����Ȗ{�I�̘b�ł���B
�@�}���ق̒�`�ɂ͑S�����ěƂ܂炸�A�܂��ǂ̂悤�Ɋg����߂��Ă��l���ɂƂ������Ȃ��A�����ȏ����Ȗ{�I�̘b�ł���B �@���̏Z���n�̎s���Z���^�[�́A��Îs���̑��n�������r�I�ɗ��p�x�������ƌ����Ă���B����I�ȗ��p�͎��O�ɓo�^�����Ă����Ďg�p����O�ɐ\�����K�v���B�������Ȃ����́A���r�[�ʼn�c�����邱�Ƃ�����B���r�[�ɂ͊ی^�̊��ƈ֎q�����r������B
�@���̏Z���n�̎s���Z���^�[�́A��Îs���̑��n�������r�I�ɗ��p�x�������ƌ����Ă���B����I�ȗ��p�͎��O�ɓo�^�����Ă����Ďg�p����O�ɐ\�����K�v���B�������Ȃ����́A���r�[�ʼn�c�����邱�Ƃ�����B���r�[�ɂ͊ی^�̊��ƈ֎q�����r������B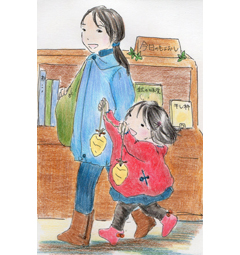 �@��Ð}���٘a玊ق̃T�[�N���ɎQ�������Ă�����Đ��N�ɂȂ�B�����������Ŏؗp�ł��āA�}���قɊW���鎄�����T�[�N���̏W�܂�ɂ͑�ς��肪�����B���̕��A�����ł��Ԃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ə�Ɏv���Ă���B
�@��Ð}���٘a玊ق̃T�[�N���ɎQ�������Ă�����Đ��N�ɂȂ�B�����������Ŏؗp�ł��āA�}���قɊW���鎄�����T�[�N���̏W�܂�ɂ͑�ς��肪�����B���̕��A�����ł��Ԃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ə�Ɏv���Ă���B
 �@�}���قɍs���Ė{��I�ԂƂ��A�܂��薼�Ɏ䂩��Ė{�����o�����Ƃ������B��҂��A�ǂ����Ă���ȑ薼��t�����̂��A��������������B
�@�}���قɍs���Ė{��I�ԂƂ��A�܂��薼�Ɏ䂩��Ė{�����o�����Ƃ������B��҂��A�ǂ����Ă���ȑ薼��t�����̂��A��������������B �@�}���قɓ���ƁA���̎��̕K�v�ɔ����Ă���Q�l�����~�����ꍇ�́A�܂����̏��˂Ɍ������B
�@�}���قɓ���ƁA���̎��̕K�v�ɔ����Ă���Q�l�����~�����ꍇ�́A�܂����̏��˂Ɍ������B �@�ŋߐ}���ق֍s�����̂́A�ߏ��̕��ɕa�C��������A�����g���[��������w����T����悤�ɎԂő����Ă������Ƃ��ł����B�Ⴂ����̓l�b�g�Œ��ׂ��܂����A�N�z�̕��͂�͂�{����������ǂ݂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�v���Ԃ�ɖK�ꂽ�}���ق͖{�Ƃ̏o�������y����ł�������X�Ŋ��C�����ӂ�Ă���悤�Ɍ����܂����B�����v���Ԃ�ɎG���̃o�b�N�i���o�[����ɂ��Ċy���݂܂����B
�@�ŋߐ}���ق֍s�����̂́A�ߏ��̕��ɕa�C��������A�����g���[��������w����T����悤�ɎԂő����Ă������Ƃ��ł����B�Ⴂ����̓l�b�g�Œ��ׂ��܂����A�N�z�̕��͂�͂�{����������ǂ݂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�v���Ԃ�ɖK�ꂽ�}���ق͖{�Ƃ̏o�������y����ł�������X�Ŋ��C�����ӂ�Ă���悤�Ɍ����܂����B�����v���Ԃ�ɎG���̃o�b�N�i���o�[����ɂ��Ċy���݂܂����B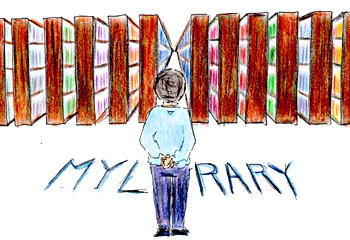 �@���s�̐}���قő啝�ȃV�X�e�����V���s��ꂽ�B��o���E�ԋp�葱���̋@�B���ɍ��킹�āA����̃p�\�R����ɁuMy���C�u�����[�v����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�}���ق��������Ă��鏑�Ђ̂����A�S�̂�����́A�ǂ����Ǝv���Ă�����́A�C�ɂȂ��Ă�����̂Ȃǂ��l�̃p�\�R����̖{�I�Ƀ��X�g�A�b�v���Ă�����Ƃ������̂ł���B�����ł́A10��ނ̒I�Ɋe100���A���v��1000���܂Ń��X�g�A�b�v�ł���Ƃ����B
�@���s�̐}���قő啝�ȃV�X�e�����V���s��ꂽ�B��o���E�ԋp�葱���̋@�B���ɍ��킹�āA����̃p�\�R����ɁuMy���C�u�����[�v����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�}���ق��������Ă��鏑�Ђ̂����A�S�̂�����́A�ǂ����Ǝv���Ă�����́A�C�ɂȂ��Ă�����̂Ȃǂ��l�̃p�\�R����̖{�I�Ƀ��X�g�A�b�v���Ă�����Ƃ������̂ł���B�����ł́A10��ނ̒I�Ɋe100���A���v��1000���܂Ń��X�g�A�b�v�ł���Ƃ����B �w�N�ɂT�����o��r�U���g���āA�l�p�[���ɑ؍݂������B�N���z������P�O�����̃r�U�ɂȂ�B���ꂪ�A���̃l�p�[���؍݂̖��x
�w�N�ɂT�����o��r�U���g���āA�l�p�[���ɑ؍݂������B�N���z������P�O�����̃r�U�ɂȂ�B���ꂪ�A���̃l�p�[���؍݂̖��x �@�}���قɂ͏��Ђ�G���A�V�������łȂ��u�r�f�I�e�[�v�A�J�Z�b�g�e�[�v��CD�ADVD�̗ނ��ݏo�p�ɏ�������Ă���v�Ƃ������Ƃ�m�����̂́A���N�O�������B�ǂ̂悤�ȃe�[�v��f�B�X�N������̂��낤�A�Ƌ����{�ʂŒI��X�g�߂��Ƃ���A�r�f�I�e�[�v�ł͎q�������̉f��␢�E��Y���Љ��悤�Ȃ��̂��ڂɕt�����B�Â����{�f���O���f����������悤�Ɋo���Ă��邪�A��̓I�ȃ^�C�g���͎v���o���Ȃ��B�J�Z�b�g�e�[�v��CD�ł͂�����ƌÂ��̗w�ȁA�C�[�W�[���X�j���O��N���V�b�N���y�ɉ����čŋ߂͂��̎��̎�̂��̂��������悤���B���������A���l��搂�ꂽ�̐l�̗���Ƃ�u�ߎt�̑S�W�Ȃǂ��������B
�@�}���قɂ͏��Ђ�G���A�V�������łȂ��u�r�f�I�e�[�v�A�J�Z�b�g�e�[�v��CD�ADVD�̗ނ��ݏo�p�ɏ�������Ă���v�Ƃ������Ƃ�m�����̂́A���N�O�������B�ǂ̂悤�ȃe�[�v��f�B�X�N������̂��낤�A�Ƌ����{�ʂŒI��X�g�߂��Ƃ���A�r�f�I�e�[�v�ł͎q�������̉f��␢�E��Y���Љ��悤�Ȃ��̂��ڂɕt�����B�Â����{�f���O���f����������悤�Ɋo���Ă��邪�A��̓I�ȃ^�C�g���͎v���o���Ȃ��B�J�Z�b�g�e�[�v��CD�ł͂�����ƌÂ��̗w�ȁA�C�[�W�[���X�j���O��N���V�b�N���y�ɉ����čŋ߂͂��̎��̎�̂��̂��������悤���B���������A���l��搂�ꂽ�̐l�̗���Ƃ�u�ߎt�̑S�W�Ȃǂ��������B �@�A�C�������h�Ɏ䂩��āA���K�ꂽ�B�k�A�C�������h����A��ցB�Ō�̓s�s�̓A�C�������h���a����s�̃_�u�����B�����ɂ́A�g���j�e�B�J���b�W�Ƃ����A�C�������h�ŌÂ̑�w������B
�@�A�C�������h�Ɏ䂩��āA���K�ꂽ�B�k�A�C�������h����A��ցB�Ō�̓s�s�̓A�C�������h���a����s�̃_�u�����B�����ɂ́A�g���j�e�B�J���b�W�Ƃ����A�C�������h�ŌÂ̑�w������B �@���͂��܂�ӎ��������Ƃ͂Ȃ��������A�V���L���Ȃǂ��琄������ƁA�}���قł͌l����v���C�o�V�[�ی�̊ϓ_���炢�낢��ƍl���A��肪�N����Ȃ��悤�ɗ��ӂ���Ă���悤���B
�@���͂��܂�ӎ��������Ƃ͂Ȃ��������A�V���L���Ȃǂ��琄������ƁA�}���قł͌l����v���C�o�V�[�ی�̊ϓ_���炢�낢��ƍl���A��肪�N����Ȃ��悤�ɗ��ӂ���Ă���悤���B ���������}����(�����l�s�������}����)
���������}����(�����l�s�������}����) �u�}���فv�Ƃ������t���L�[���[�h�ɎO�̋L���Ɏc���Ă��镶�͂┭���������A�˂�B
�u�}���فv�Ƃ������t���L�[���[�h�ɎO�̋L���Ɏc���Ă��镶�͂┭���������A�˂�B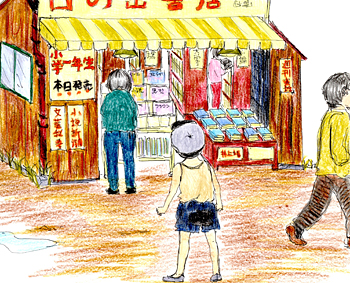 �@�Ƃ́A�{���ɕn���������B
�@�Ƃ́A�{���ɕn���������B �@���s�̐}���ق̃z�[���y�[�W�߂Ă��ċ��R�Ɂu���ɎU��c�A�[�w������Ə��ɂ܂Łx�v���v�悳��Ă���̂�m�����B���ܗ��s�̃o�b�N���[�h�E�c�A�[�̈�킾�낤�Ǝv���A�w�肳�ꂽ�����̏����O�Ɏ�t�����֍s�����B
�@���s�̐}���ق̃z�[���y�[�W�߂Ă��ċ��R�Ɂu���ɎU��c�A�[�w������Ə��ɂ܂Łx�v���v�悳��Ă���̂�m�����B���ܗ��s�̃o�b�N���[�h�E�c�A�[�̈�킾�낤�Ǝv���A�w�肳�ꂽ�����̏����O�Ɏ�t�����֍s�����B �@��Îs���a玐}���قɒʂ��n�߂Đ��N�ɂȂ�B
�@��Îs���a玐}���قɒʂ��n�߂Đ��N�ɂȂ�B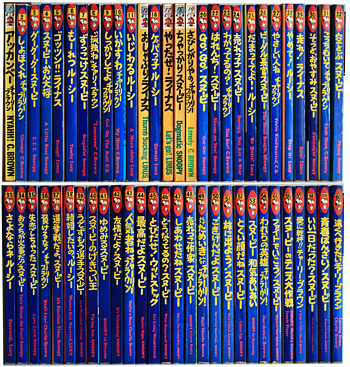 �@���m���̍H��ɓ]���Ă���́A�x���ɖ��É��s�܂ŏo�����āA�f�p�[�g�����������A�{����`�����肷��̂������Ȃ�܂����B
�@���m���̍H��ɓ]���Ă���́A�x���ɖ��É��s�܂ŏo�����āA�f�p�[�g�����������A�{����`�����肷��̂������Ȃ�܂����B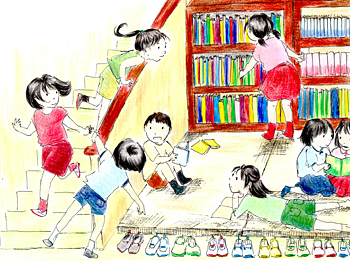 �@�w�Z�ɋΖ����Ă������A�������̍Z�������������Ă��܂����B�����ɂ��āA�q�ǂ������̊w�тɍ������������邩�Ƃ����d���ł��B���ԍ͔|���玑�����̐����A�}�����̐����܂ŁA���̎d�����e�́A�����L�����̂ł����B
�@�w�Z�ɋΖ����Ă������A�������̍Z�������������Ă��܂����B�����ɂ��āA�q�ǂ������̊w�тɍ������������邩�Ƃ����d���ł��B���ԍ͔|���玑�����̐����A�}�����̐����܂ŁA���̎d�����e�́A�����L�����̂ł����B| �P |
�@�������X�y�[�X�ɁA���u�ɂ������O��قǕ~���i�ȑO�A�a�������������̊w�Z�ɂ́A�c���Ă��܂����j�B |
| �Q |
�@�p�����ꂽ�{�����̃X�y�[�X�ɒu���B�Â��{�I��T���Ă��Đݒu����B |
| �R |
�@�u���ꂽ�{�́A���R�ɓǂ�ł����B�d�������Ƃ����A������Ǝw������B |
 �@�������Ă��镶�ɂ�A����̃����o�[�ƈꏏ�ɁA���邢�͈�l�ŁA�����Ȑ}���ق����w���Ă��܂����B���̈ꕔ�����Љ�����Ǝv���܂��B
�@�������Ă��镶�ɂ�A����̃����o�[�ƈꏏ�ɁA���邢�͈�l�ŁA�����Ȑ}���ق����w���Ă��܂����B���̈ꕔ�����Љ�����Ǝv���܂��B �@������Ƃ͌Â��đ傫�������B���w�Z�ɓ��鎞�܂őc��Əf��ɗa�����A��l����ĂĂ��ꂽ�B
�@������Ƃ͌Â��đ傫�������B���w�Z�ɓ��鎞�܂őc��Əf��ɗa�����A��l����ĂĂ��ꂽ�B �@��Îs�̐}���ٗ��p�҂̍ŋ߂̓��v������ƁA���ꌧ���̑��s�ɔ�ׂđݏo������������Ă���B�������E���̖����傫�����A�}���ق�g�߂Ɋ����Ă��Ȃ��l���܂��܂���R���邱�Ƃ����̐����̒��Ŋ����Ă���B
�@��Îs�̐}���ٗ��p�҂̍ŋ߂̓��v������ƁA���ꌧ���̑��s�ɔ�ׂđݏo������������Ă���B�������E���̖����傫�����A�}���ق�g�߂Ɋ����Ă��Ȃ��l���܂��܂���R���邱�Ƃ����̐����̒��Ŋ����Ă���B �@���́A�{��ǂނƂ��̐��E�ɓ��肽���Ƃ����Ɏv���q�ǂ��ł����B�ȑO�o�����u�����ɂȂ肽���v�ɑ����āu�d���ɉ�����v�Ǝv���������b�ł��B
�@���́A�{��ǂނƂ��̐��E�ɓ��肽���Ƃ����Ɏv���q�ǂ��ł����B�ȑO�o�����u�����ɂȂ肽���v�ɑ����āu�d���ɉ�����v�Ǝv���������b�ł��B �@�f�������ƌ��삪�ǂ݂����Ȃ�A�{��ǂނƉf��ɂȂ��ĂȂ����ƒT���B����Ɖf��̈Ⴂ���ׂ�̂���ς������낢�B
�@�f�������ƌ��삪�ǂ݂����Ȃ�A�{��ǂނƉf��ɂȂ��ĂȂ����ƒT���B����Ɖf��̈Ⴂ���ׂ�̂���ς������낢�B �@�}���ق͉p��ł̓��C�u�����[�iLibrary�j�Ƃ������A���̌��t����v���o������̐}���ق�����B
�@�}���ق͉p��ł̓��C�u�����[�iLibrary�j�Ƃ������A���̌��t����v���o������̐}���ق�����B �@�Ď��Îq���S���Ȃ�ꂽ�B���̕���Đ}���قցB���ꂾ���̍�ƂȂ���u�ނ�Łc�v���炢�̒Ǔ��������ꉺ�����ĂȂ����Ǝv�����B���̎��A�o��������}���ق̒Ǔ����̂悤�ɁB�c�c�e���`���Ȃ������B
�@�Ď��Îq���S���Ȃ�ꂽ�B���̕���Đ}���قցB���ꂾ���̍�ƂȂ���u�ނ�Łc�v���炢�̒Ǔ��������ꉺ�����ĂȂ����Ǝv�����B���̎��A�o��������}���ق̒Ǔ����̂悤�ɁB�c�c�e���`���Ȃ������B �@�q���̍�����u�Ȃ�ł��H�v�Ǝv�����Ƃ������A�����N�����Ė����ɂ��̐����͎���Ȃ��ǂ��납�A�܂��܂��i��ł��܂����B
�@�q���̍�����u�Ȃ�ł��H�v�Ǝv�����Ƃ������A�����N�����Ė����ɂ��̐����͎���Ȃ��ǂ��납�A�܂��܂��i��ł��܂����B �@���q���c�t���̍��������낤���B�}���Ńg�C���ɓ��������Ǝv���ƁA�����o���Ă��o�Ă���l�q�͂Ȃ��B
�@���q���c�t���̍��������낤���B�}���Ńg�C���ɓ��������Ǝv���ƁA�����o���Ă��o�Ă���l�q�͂Ȃ��B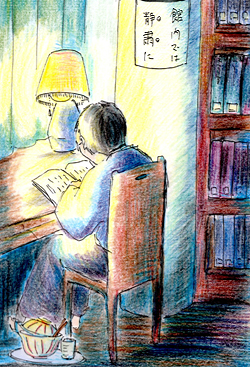 �@�����ǂ���}���قɏZ�w�҂̘b��ǂ��Ƃ�����B�Z���悭�Ȃ����̘b�ł���B�C�O���w����A����������̎�茤���҂ł������ނ́A�u�肵�đ�w�}���ق̏Z�ݍ��ݏh�����ɂȂ����������B�����Ŕނ͐^�钆�̐}���قƂ����ɂ߂��ґ�ȋ�ԂāA�����ɂ���S�Ă̐}�����䂪���Ƃ��A�Ǐ��A�����A�v���ɖv�������Ƃ����B
�@�����ǂ���}���قɏZ�w�҂̘b��ǂ��Ƃ�����B�Z���悭�Ȃ����̘b�ł���B�C�O���w����A����������̎�茤���҂ł������ނ́A�u�肵�đ�w�}���ق̏Z�ݍ��ݏh�����ɂȂ����������B�����Ŕނ͐^�钆�̐}���قƂ����ɂ߂��ґ�ȋ�ԂāA�����ɂ���S�Ă̐}�����䂪���Ƃ��A�Ǐ��A�����A�v���ɖv�������Ƃ����B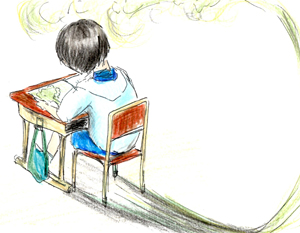 �@���܂��܂ȓǏ��O���[�v�Ƃ��A�w�Z�Łu�G�{�̓ǂݕ����������v��u���̓Ǐ������v���W�J����Ă���B���̔N��ɍ��킹�āA�u�����{���q�ǂ������Ɂv�̊肢�ōs���Ă��邱�Ƃ́A�q��Ă�����e�Ƃ��đ�ς��ꂵ�����Ƃ��B
�@���܂��܂ȓǏ��O���[�v�Ƃ��A�w�Z�Łu�G�{�̓ǂݕ����������v��u���̓Ǐ������v���W�J����Ă���B���̔N��ɍ��킹�āA�u�����{���q�ǂ������Ɂv�̊肢�ōs���Ă��邱�Ƃ́A�q��Ă�����e�Ƃ��đ�ς��ꂵ�����Ƃ��B �@�ǂ�ȏ����ł��o��l���̕\������āA���̍�Ƃ͂ǂ�Ȏ��ɂ��̍�i���������̂��낤���ƁA�����ÁX�̓��ɓǂݎn�߂�Ƃ��ꂪ���̊Ԃɂ��D���ȍ�ƂɂȂ�����A��i�̈ꕔ�����Y����Ȃ����̂ɂȂ����肷��B
�@�ǂ�ȏ����ł��o��l���̕\������āA���̍�Ƃ͂ǂ�Ȏ��ɂ��̍�i���������̂��낤���ƁA�����ÁX�̓��ɓǂݎn�߂�Ƃ��ꂪ���̊Ԃɂ��D���ȍ�ƂɂȂ�����A��i�̈ꕔ�����Y����Ȃ����̂ɂȂ����肷��B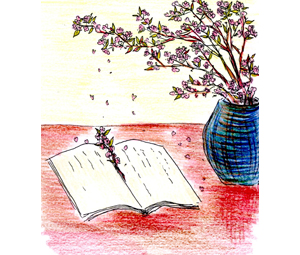 �@������������{��ǂނ��Ƃ͍D���������B
�@������������{��ǂނ��Ƃ͍D���������B �@�O�̍�����G�{�̂��ň�ĂĂ����䂪�q�B�P�W�����ɂȂ�܂����B�����̎q�Ɣ�ׂĂ��G�{���D���Ȏq�Ɉ���Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@�O�̍�����G�{�̂��ň�ĂĂ����䂪�q�B�P�W�����ɂȂ�܂����B�����̎q�Ɣ�ׂĂ��G�{���D���Ȏq�Ɉ���Ă���悤�Ɏv���܂��B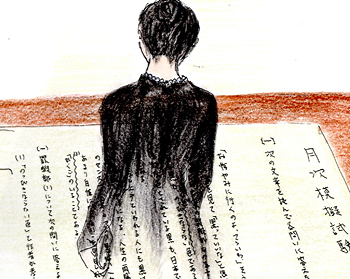 �@�Y����Ȃ��G�b�Z�C���������B
�@�Y����Ȃ��G�b�Z�C���������B �@���ܗ��ق����ɂ��₩�Ȑa�m�ŁA�m�����������\�����ޕ��������܂����B�����܂��Ⴉ�������ɂ܂ŖX�q������ē��������A�u���肢���܂��v�ƌ����ċA����悤�ȕ��ł����B�ƂĂ����Ă��Ȃ������܂Ȃ̂ł����A���N�G�X�g�����{�͂ǂ���m���̐�发�ŁA����́�����w�����A�������́~�~�̎{�݂ɂ���A�ȂǂƎ����w�肵�Ă��������āA����Ƃ��ǂ����悤�ȗL�l�ł����B�͂����{�����Ă����̕���Ȃ̂�����悭�킩�炸�A�p��ȊO�̌���̂��̂������Đ��Ȃ����L��������܂��B
�@���ܗ��ق����ɂ��₩�Ȑa�m�ŁA�m�����������\�����ޕ��������܂����B�����܂��Ⴉ�������ɂ܂ŖX�q������ē��������A�u���肢���܂��v�ƌ����ċA����悤�ȕ��ł����B�ƂĂ����Ă��Ȃ������܂Ȃ̂ł����A���N�G�X�g�����{�͂ǂ���m���̐�发�ŁA����́�����w�����A�������́~�~�̎{�݂ɂ���A�ȂǂƎ����w�肵�Ă��������āA����Ƃ��ǂ����悤�ȗL�l�ł����B�͂����{�����Ă����̕���Ȃ̂�����悭�킩�炸�A�p��ȊO�̌���̂��̂������Đ��Ȃ����L��������܂��B �@�c�݂̑��o���̖{�̒��ɁA�������q��u�C�g�E�̗��v�Ƃ����{������܂����B�������q����̖{�́A�D���Ȗ{�̂����A�����Ƃs���I��œ���Ă����������B
�@�c�݂̑��o���̖{�̒��ɁA�������q��u�C�g�E�̗��v�Ƃ����{������܂����B�������q����̖{�́A�D���Ȗ{�̂����A�����Ƃs���I��œ���Ă����������B �@�܂��Ă������̏��w������́A����������ƐS���Ă���܂����B
�@�܂��Ă������̏��w������́A����������ƐS���Ă���܂����B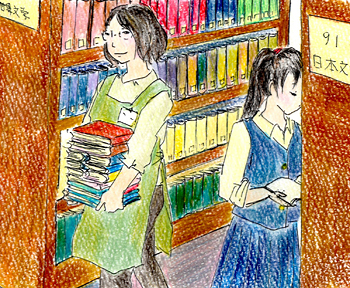 �u��������l�̎i���ł����ꂾ���̎d������ꂽ�̂Ɂc�c�v
�u��������l�̎i���ł����ꂾ���̎d������ꂽ�̂Ɂc�c�v �@���z�[���y�[�W�̋L����q�ǂ��邽�тɁA�l���������邱�Ƃ������B���̈�́u���K�E���A�i�����v�̂��Ƃł���B�l�����������Ƃ͑厖�����A����Ƌ��Ɏi���̎����͏d�v����Ƃ��v���Ă��܂��B
�@���z�[���y�[�W�̋L����q�ǂ��邽�тɁA�l���������邱�Ƃ������B���̈�́u���K�E���A�i�����v�̂��Ƃł���B�l�����������Ƃ͑厖�����A����Ƌ��Ɏi���̎����͏d�v����Ƃ��v���Ă��܂��B �@�a玐}���ٗ��p�҂ł��B������܂�Ƃ��Ă��āA�������D���Ȃ̂ł悭���p���܂��B�����ɗ��p�҂̐����������āA�S�����炢�낢�땨�c���������Ă��铊�����\���Ă���܂��B�������̂܂o���Ƃ����̂́A�}���ق̗E�C�������܂��B���̒��ő����̂��A�{�ɕ����Ă����ԋp�N�������m�点�̂͂��~�߂ɂȂ������Ƃɂ��Ă̈ӌ��ł����B����Ȏ��ɁA�F�l������Ă��āA������Ă���{�����Č������̂ł��B
�@�a玐}���ٗ��p�҂ł��B������܂�Ƃ��Ă��āA�������D���Ȃ̂ł悭���p���܂��B�����ɗ��p�҂̐����������āA�S�����炢�낢�땨�c���������Ă��铊�����\���Ă���܂��B�������̂܂o���Ƃ����̂́A�}���ق̗E�C�������܂��B���̒��ő����̂��A�{�ɕ����Ă����ԋp�N�������m�点�̂͂��~�߂ɂȂ������Ƃɂ��Ă̈ӌ��ł����B����Ȏ��ɁA�F�l������Ă��āA������Ă���{�����Č������̂ł��B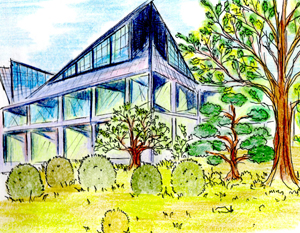 �@���]��߂铇�������}���ق̘b����������A�̋��̓Ǐ���D���ȕ�����A���̐}���ق̘b����������ł��܂����B
�@���]��߂铇�������}���ق̘b����������A�̋��̓Ǐ���D���ȕ�����A���̐}���ق̘b����������ł��܂����B �@��ǎR�n�̂��ƁA��Îs�̌ΐ��ɏZ�݂����āu�a玐}���فv�ɒʂ��n�߂��B
�@��ǎR�n�̂��ƁA��Îs�̌ΐ��ɏZ�݂����āu�a玐}���فv�ɒʂ��n�߂��B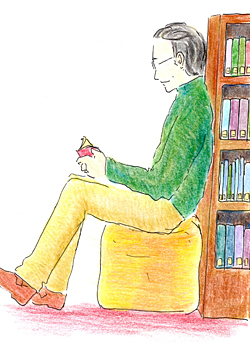 �@��N�ސE�����āA�R�O�N�Ԃ�ɐ}���ْʂ����n�߂��B�ȑO�̐}���ْʂ��́A�q�ǂ������ƈꏏ�ɓy�j�����P�Ⴞ�����B�����������ċA��Ďq�ǂ������͖{��ǂ݂ӂ������B
�@��N�ސE�����āA�R�O�N�Ԃ�ɐ}���ْʂ����n�߂��B�ȑO�̐}���ْʂ��́A�q�ǂ������ƈꏏ�ɓy�j�����P�Ⴞ�����B�����������ċA��Ďq�ǂ������͖{��ǂ݂ӂ������B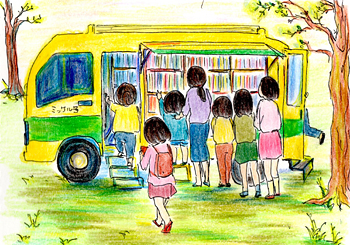 �u�˂ˁB�~�b�P�������ĂȂ��Ɂv
�u�˂ˁB�~�b�P�������ĂȂ��Ɂv �@�ŋ߁A�e�n�̐}���ق̗l�q����ϋC�ɂȂ��Ă���B�����̗p�ő��s�֏o������ƁA�߂��ɐ}���ق���������A�Z���Ԃł��̂����Ă݂����Ȃ�B
�@�ŋ߁A�e�n�̐}���ق̗l�q����ϋC�ɂȂ��Ă���B�����̗p�ő��s�֏o������ƁA�߂��ɐ}���ق���������A�Z���Ԃł��̂����Ă݂����Ȃ�B �@���w�Z�̎��A�K���}�����Ŗ{����Ă����B�����́A��R�̖{�̒�����D���Ȃ��̂����R�ɑI�ׂ�K���̋�Ԃ������B�{�̒��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���̗V�т����Ă������ʂ̎q���������A�{���ǂ�ł���Ƃ��������������B
�@���w�Z�̎��A�K���}�����Ŗ{����Ă����B�����́A��R�̖{�̒�����D���Ȃ��̂����R�ɑI�ׂ�K���̋�Ԃ������B�{�̒��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���̗V�т����Ă������ʂ̎q���������A�{���ǂ�ł���Ƃ��������������B �@��Îs�ɏZ��ł��Ȃ���A��Î����̂��Ƃ��悭�m��Ȃ������B����A�x�������q����́u�̓�v���݂�ȂœǂB��Î����ɂ��Ă͉��l���������Ă��邪�A�u�̓�v�́A��ԐV������i�Ɉʒu�Â������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�x�����b�q����͔��i�ΔȂɈڂ�Z��ł��̏����������ꂽ�B���̂��߂ɂт�Ύ��ӂ̂�������i�F��r�A���J�A�ԉΑ��A�����猩����O��R�A�ѐA�A�M����A�����w�Ƃ������w���̓S���������A���ɐg�߂ȕ��i����̂������������B�܂��V�����Óc�O����Ō��������O���̏��Ȃ����p���ĔƐl�Óc�O���̉Ƒ���e���A�m�l�Ȃǂ̐����A�j�R���C���L����݂��j�R���C�c���q�≤�܂̂��ƁA�����ĕ����ɓd�C���̑��q�^�r�g���炭��莆�̘b���������A���݂��N���蓾�鉽���Ƃ��̎���⎖���Ƃ��������Ȃ���̓W�J������Ă����B
�@��Îs�ɏZ��ł��Ȃ���A��Î����̂��Ƃ��悭�m��Ȃ������B����A�x�������q����́u�̓�v���݂�ȂœǂB��Î����ɂ��Ă͉��l���������Ă��邪�A�u�̓�v�́A��ԐV������i�Ɉʒu�Â������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�x�����b�q����͔��i�ΔȂɈڂ�Z��ł��̏����������ꂽ�B���̂��߂ɂт�Ύ��ӂ̂�������i�F��r�A���J�A�ԉΑ��A�����猩����O��R�A�ѐA�A�M����A�����w�Ƃ������w���̓S���������A���ɐg�߂ȕ��i����̂������������B�܂��V�����Óc�O����Ō��������O���̏��Ȃ����p���ĔƐl�Óc�O���̉Ƒ���e���A�m�l�Ȃǂ̐����A�j�R���C���L����݂��j�R���C�c���q�≤�܂̂��ƁA�����ĕ����ɓd�C���̑��q�^�r�g���炭��莆�̘b���������A���݂��N���蓾�鉽���Ƃ��̎���⎖���Ƃ��������Ȃ���̓W�J������Ă����B �@�G�{�ǂݕ���A�}�ӎ����Ŏ��̎q�ǂ������͈炿�܂����B�q���M�����̈�Ԃ̎v���o�́A���ӐQ��O�̓ǂݕ����������������ł��B���̌҂̊Ԃɂ͂܂荞��ł��b�����̂��K�����������Č����Ă܂��B���Ԃ͌��邱�Ƃ��y���݁A��́A�����đz�����邱�Ƃ��y����ł��������ł��B
�@�G�{�ǂݕ���A�}�ӎ����Ŏ��̎q�ǂ������͈炿�܂����B�q���M�����̈�Ԃ̎v���o�́A���ӐQ��O�̓ǂݕ����������������ł��B���̌҂̊Ԃɂ͂܂荞��ł��b�����̂��K�����������Č����Ă܂��B���Ԃ͌��邱�Ƃ��y���݁A��́A�����đz�����邱�Ƃ��y����ł��������ł��B �@�ǂ�Ȑ}���قɂ��炪����B�ŋߌ��݂��ꂽ�}���ق͂܂�ŏ��X�̂悤���B����肸���ƎႩ�肵���́A�}���قƊւ���Ă������Ƃ���A��������Ƃ��̒��i�X�j�̐}���قɗ���������B�}���يW�҂Œm�荇���ɂȂ������ƍĉ�Ă��b���邱�Ƃ��y���݂����A���������̕����ǂ�ȕ��ɓ����Ă��邩����������M�����Ƃ��傢�ɕ��ɂȂ����B���˂̔z��A�J�E���^�[����A�E���̓����A���p�҂̗l�q�A�����\���A���̒��ł��Q�l���̎�ނ͓��ɋC�ɂȂ����B�����Ȑ}���ققǎQ�l�������Ȃ��B�����}���قɂ����l�X�ȎQ�l����u���ׂ����Ǝv���Ă���B
�@�ǂ�Ȑ}���قɂ��炪����B�ŋߌ��݂��ꂽ�}���ق͂܂�ŏ��X�̂悤���B����肸���ƎႩ�肵���́A�}���قƊւ���Ă������Ƃ���A��������Ƃ��̒��i�X�j�̐}���قɗ���������B�}���يW�҂Œm�荇���ɂȂ������ƍĉ�Ă��b���邱�Ƃ��y���݂����A���������̕����ǂ�ȕ��ɓ����Ă��邩����������M�����Ƃ��傢�ɕ��ɂȂ����B���˂̔z��A�J�E���^�[����A�E���̓����A���p�҂̗l�q�A�����\���A���̒��ł��Q�l���̎�ނ͓��ɋC�ɂȂ����B�����Ȑ}���ققǎQ�l�������Ȃ��B�����}���قɂ����l�X�ȎQ�l����u���ׂ����Ǝv���Ă���B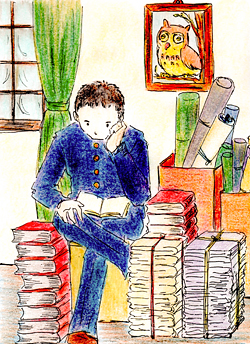 �@�P�X�T�R�N�A�ڂ��͓����E���c�J�旧���w�Z�̂Q�N���������B�w�Z�ɂ́A�}���ق͂��납�}�������Ȃ������B������̂��Ɛ搶����A�Â����ނ�狳�ނ�炪�G���ɐς܂�Ă��镔���łȂɂ��̎�`��������悤�Ɍ���ꂽ�B
�@�P�X�T�R�N�A�ڂ��͓����E���c�J�旧���w�Z�̂Q�N���������B�w�Z�ɂ́A�}���ق͂��납�}�������Ȃ������B������̂��Ɛ搶����A�Â����ނ�狳�ނ�炪�G���ɐς܂�Ă��镔���łȂɂ��̎�`��������悤�Ɍ���ꂽ�B �@���͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����㖜���������́u��㍑�ێ������w�فv�i���݂́A�{���}���قɊԎ��ԁj�A�����֎��X���ɂ̂��ǂ������Ɖ��������˂Č��w�ɍs���Ă��܂����B������Ƒ傫���q�́A�~�`�̏��˂̂܂{�Ɉ͂܂�āA�����킹�����ɍ��荞��ł��܂����B���̐}���ق̂������Ƃ���́A�q�ǂ��̕����Ɋւ��邢���Ȏ������W�߂Ă��邱�ƂŁA�ƂĂ��L���ł����B
�@���͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����㖜���������́u��㍑�ێ������w�فv�i���݂́A�{���}���قɊԎ��ԁj�A�����֎��X���ɂ̂��ǂ������Ɖ��������˂Č��w�ɍs���Ă��܂����B������Ƒ傫���q�́A�~�`�̏��˂̂܂{�Ɉ͂܂�āA�����킹�����ɍ��荞��ł��܂����B���̐}���ق̂������Ƃ���́A�q�ǂ��̕����Ɋւ��邢���Ȏ������W�߂Ă��邱�ƂŁA�ƂĂ��L���ł����B �@�����Ζ������n�̊e�w�Z�ɂ́A�s����u�q�ǂ������̐S��L���ɂ�����g�݁v�̂��߂Ɂ��\���~���̗\�Z���z������Ă����B���ꂼ��̊w�Z�̓��F������H�̂��߂Ɏ��R�Ɏg���Ă����Ƃ������̂������B
�@�����Ζ������n�̊e�w�Z�ɂ́A�s����u�q�ǂ������̐S��L���ɂ�����g�݁v�̂��߂Ɂ��\���~���̗\�Z���z������Ă����B���ꂼ��̊w�Z�̓��F������H�̂��߂Ɏ��R�Ɏg���Ă����Ƃ������̂������B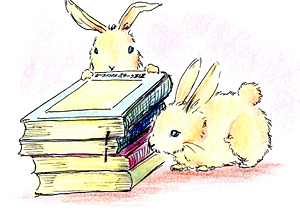 �@�����Ȋw�Ȃ̃z�[���y�[�W�ł́A�i������ɂ��āu�i���́A�s���{����s�����̌����}���ٓ��Ő}���َ����̑I���A�����y�ю��ꂩ��A���ށA�ژ^�쐬�A�ݏo�Ɩ��A�Ǐ��ē��Ȃǂ��s�����I�E���ł��v�Ɛ������Ă���B
�@�����Ȋw�Ȃ̃z�[���y�[�W�ł́A�i������ɂ��āu�i���́A�s���{����s�����̌����}���ٓ��Ő}���َ����̑I���A�����y�ю��ꂩ��A���ށA�ژ^�쐬�A�ݏo�Ɩ��A�Ǐ��ē��Ȃǂ��s�����I�E���ł��v�Ɛ������Ă���B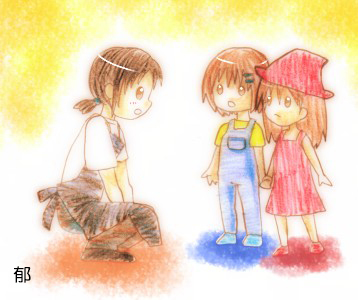 �@���w�Z�R�N���̎{���w�ŁA���N�������̊w�Z�������i���Ƃ��ċΖ�����}���قɂ����Ă���܂��B
�@���w�Z�R�N���̎{���w�ŁA���N�������̊w�Z�������i���Ƃ��ċΖ�����}���قɂ����Ă���܂��B �u�O�����p�ӂł��Ă��܂��v�}���َi���̂m���A�ɂ�����Ɣ��݂����Ă���B�����͑�Îs���k�}���قł���B���͗\��̖{�����ɗ��ق����̂��B�l���Ă݂�A���@�����Ƃ��ȊO�́A�T���͂�����K��Ă��邱�ƂɂȂ�B�����������݂̏ꏊ�Ƃ�����ł���B
�u�O�����p�ӂł��Ă��܂��v�}���َi���̂m���A�ɂ�����Ɣ��݂����Ă���B�����͑�Îs���k�}���قł���B���͗\��̖{�����ɗ��ق����̂��B�l���Ă݂�A���@�����Ƃ��ȊO�́A�T���͂�����K��Ă��邱�ƂɂȂ�B�����������݂̏ꏊ�Ƃ�����ł���B �u�ǂ�Ȗ{���D���H�@�ǂ�Ȗ{�ǂ�ł��́v
�u�ǂ�Ȗ{���D���H�@�ǂ�Ȗ{�ǂ�ł��́v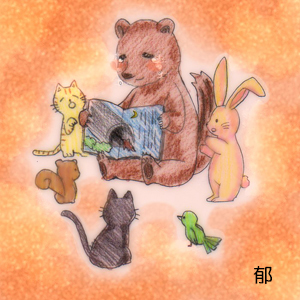 �@�����Ζ����鏬�w�Z�́A���ꂳ��B�̓ǂݕ�������������ϐ���ł��B�T�����̓Ǐ��̎��Ԃɂ́A���Ԃ����߂ēǂݕ�����������܂��B
�@�����Ζ����鏬�w�Z�́A���ꂳ��B�̓ǂݕ�������������ϐ���ł��B�T�����̓Ǐ��̎��Ԃɂ́A���Ԃ����߂ēǂݕ�����������܂��B �@��Q�̂���q�ǂ��̊w���ۈ�œ����Ă������ɂƂ��āA�u�q�ǂ������Ƃǂ�Ȗ{��ǂ������H�@�ǂ�Ȗ{���ʔ��������H�v����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���}���ق̊G�{�R�[�i�[�ʼn߂������Ƃ͊y���݂̈�ł����B�����āA�ꏏ�Ɋy���߂��{�͖{������ōw���I
�@��Q�̂���q�ǂ��̊w���ۈ�œ����Ă������ɂƂ��āA�u�q�ǂ������Ƃǂ�Ȗ{��ǂ������H�@�ǂ�Ȗ{���ʔ��������H�v����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���}���ق̊G�{�R�[�i�[�ʼn߂������Ƃ͊y���݂̈�ł����B�����āA�ꏏ�Ɋy���߂��{�͖{������ōw���I �@�{�I�̒��ɂ͎̂Ă�Ɏ̂Ă��Ȃ��Z�s�A�F���݂��{������������B���̈����
�@�{�I�̒��ɂ͎̂Ă�Ɏ̂Ă��Ȃ��Z�s�A�F���݂��{������������B���̈���� �u���������ǁA�q�ǂ������̂��߂Ɏg���Ăˁv�F�l�����ꂽ�}����������ău�b�N�I�t�ֈꑖ��B�q�ǂ��������ڂ��P�����ēǂގp��z������ƑI���ɂ��͂�����B���́A�����w�������{������āA�l�p�[���̃T�`�R�[�����֗����B
�u���������ǁA�q�ǂ������̂��߂Ɏg���Ăˁv�F�l�����ꂽ�}����������ău�b�N�I�t�ֈꑖ��B�q�ǂ��������ڂ��P�����ēǂގp��z������ƑI���ɂ��͂�����B���́A�����w�������{������āA�l�p�[���̃T�`�R�[�����֗����B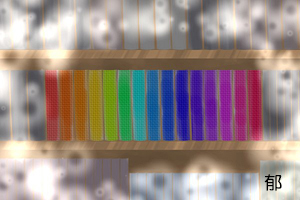 �@�}���قƂ������t����z�N���錻���̐}���ق��Q����B�ŏ��ɓ��ɕ����Ԃ̂́A�s���̒����}���قƂ��̕��قł���B�����}���ق͉䂪�Ƃ�������ĂP�O�����̂Ƃ���ɂ���ΖL���Ȍ������̂S�K���̃r���ł���A���̕��ق́A���p�҂̕ւ�}�����̂��낤�A�w�O�̃r���̂T�K�ɂ���B
�@�}���قƂ������t����z�N���錻���̐}���ق��Q����B�ŏ��ɓ��ɕ����Ԃ̂́A�s���̒����}���قƂ��̕��قł���B�����}���ق͉䂪�Ƃ�������ĂP�O�����̂Ƃ���ɂ���ΖL���Ȍ������̂S�K���̃r���ł���A���̕��ق́A���p�҂̕ւ�}�����̂��낤�A�w�O�̃r���̂T�K�ɂ���B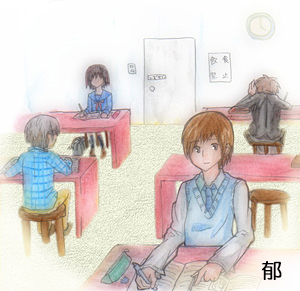 �@���m�����C�s�̍H��i�{�Ђ͋��s�j�Ō���Ζ������Ă������̂��Ƃł��B�R���s���[�^�[����̐�y����b�n�a�n�k����̓��发��Ⴂ�܂����B
�@���m�����C�s�̍H��i�{�Ђ͋��s�j�Ō���Ζ������Ă������̂��Ƃł��B�R���s���[�^�[����̐�y����b�n�a�n�k����̓��发��Ⴂ�܂����B �@�������\�N���̘̂b�ł��B�c��̐l�ԂɂƂ��Đ푈�̌o���͂��Ă��Ȃ�����ǁA�푈�̘b��f���͑�R���Ă��܂����B���������W���̏I���������Ă��܂��B���̓x�Ɏv���o���̂͏��w���T�N�̐}�����ł̏o�����B�����A���͊w���ψ��Ɛ}���ψ������Ă��������ȏ��̎q�B
�@�������\�N���̘̂b�ł��B�c��̐l�ԂɂƂ��Đ푈�̌o���͂��Ă��Ȃ�����ǁA�푈�̘b��f���͑�R���Ă��܂����B���������W���̏I���������Ă��܂��B���̓x�Ɏv���o���̂͏��w���T�N�̐}�����ł̏o�����B�����A���͊w���ψ��Ɛ}���ψ������Ă��������ȏ��̎q�B �@�ŋ߂́A���]��ǂ�ŋC�ɂȂ�{�A�{������œǂ݂����Ȃ��Ǝv�����{�Ȃǂ��A�g���ł��m�[�g�h�Ƀ������āA�������܂�ƁA�}���ق̃l�b�g�����A�\��A�A��������Ɛ}���قɎ��ɍs���B�Ƃ������@�������Ƃ��Ă���B���Ԃ̂Ȃ����́A�ƂĂ��������Ă���B
�@�ŋ߂́A���]��ǂ�ŋC�ɂȂ�{�A�{������œǂ݂����Ȃ��Ǝv�����{�Ȃǂ��A�g���ł��m�[�g�h�Ƀ������āA�������܂�ƁA�}���ق̃l�b�g�����A�\��A�A��������Ɛ}���قɎ��ɍs���B�Ƃ������@�������Ƃ��Ă���B���Ԃ̂Ȃ����́A�ƂĂ��������Ă���B �@�Ƃނ���ɂƂ��āA���傤�͑҂����������ł��B����͂Q���Ԗڂ̋x�ݎ��ԂɁA������Ԃɂ�������̖{���悹���u�ړ��}���ق����獆�v���A�w�Z�ɗ����������ł��B�����獆�́A�Q�T���̋x�ݎ��Ԃɒ���ɒ�܂�ƁA�傫�Ȕ��������Ă���܂��B
�@�Ƃނ���ɂƂ��āA���傤�͑҂����������ł��B����͂Q���Ԗڂ̋x�ݎ��ԂɁA������Ԃɂ�������̖{���悹���u�ړ��}���ق����獆�v���A�w�Z�ɗ����������ł��B�����獆�́A�Q�T���̋x�ݎ��Ԃɒ���ɒ�܂�ƁA�傫�Ȕ��������Ă���܂��B �@�a玐}���ق̊y���݂́u�V���}���v�Ɓu�����̓��W�v���B�V���̓��W�́A�V�C�����Ӑg�́u�X�|�[�c�v�ł���B���̂Ȃ��Ŗڂ��䂭�̂́A�Ԑ��쌴���w�V�l�́x���B�J�o�[�̎�F�́A�V�l��[�z�ɋ[�����ɈႢ�Ȃ��B�����͉��ƂȂ��L���ɂ��邩��A�́A�b��ɂȂ����{�炵���B
�@�a玐}���ق̊y���݂́u�V���}���v�Ɓu�����̓��W�v���B�V���̓��W�́A�V�C�����Ӑg�́u�X�|�[�c�v�ł���B���̂Ȃ��Ŗڂ��䂭�̂́A�Ԑ��쌴���w�V�l�́x���B�J�o�[�̎�F�́A�V�l��[�z�ɋ[�����ɈႢ�Ȃ��B�����͉��ƂȂ��L���ɂ��邩��A�́A�b��ɂȂ����{�炵���B �@�c�Ɉ炿�̎����A���߂āu�}���فv�Ƃ����u�{�̊فv�ɏo������̂́A���Z���ɂȂ��Ă���ł����B�T���ɍ���Ɏw�肳�ꂽ���]��B���a�S�O�N���͏��]�����̊ېՒn�Ɍ����}���ق�����܂����B�ؗ��Ɉ͂܂�āA���x�̐��ʂ߂ēǏ�����Â��ȂЂƂƂ��ɖ�������āA���X�ʂ��܂����B�ؑ��̌����ɂ��S�n�ǂ��������܂����B
�@�c�Ɉ炿�̎����A���߂āu�}���فv�Ƃ����u�{�̊فv�ɏo������̂́A���Z���ɂȂ��Ă���ł����B�T���ɍ���Ɏw�肳�ꂽ���]��B���a�S�O�N���͏��]�����̊ېՒn�Ɍ����}���ق�����܂����B�ؗ��Ɉ͂܂�āA���x�̐��ʂ߂ēǏ�����Â��ȂЂƂƂ��ɖ�������āA���X�ʂ��܂����B�ؑ��̌����ɂ��S�n�ǂ��������܂����B|
�E�ړI�Ɗ��� �@�E�}���ق��l����W�� �@�E�~�j�w�K�� |
�E�R�����u�}���قƂ킽�� ���̖{���̖{�v �E��� �E�^�c��c |
�E�Q�l���� �@�E�Q�l�}�� �@�E���̑��̎Q�l���� �E���₢���킹 |